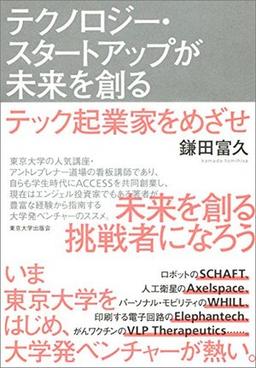ヒューマノイドの実用化をめざすSCHAFT
ロボットは実用化しないと意味がない
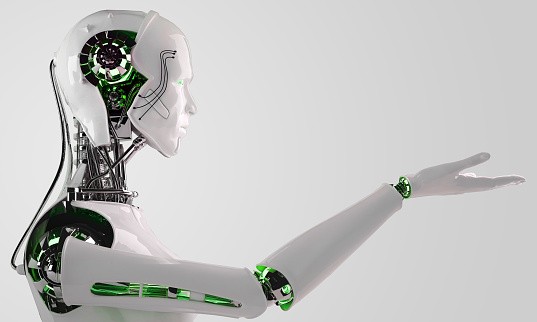
著者が注目するテクノロジー・スタートアップのストーリーのうち、ヒューマノイド、すなわちヒト型ロボットの実用化をめざすSCHAFT(シャフト)の事例を紹介する。
東京大学でヒューマノイドの研究をしていた中西雄飛氏と浦田順一氏。この分野で名の知れた若手研究者の二人が起業を決意した契機は、東日本大震災だった。福島第一原子力発電所の事故現場では、原子炉建屋の内部の状況を把握するために、無人走行するロボットが必要だった。このときすぐに役立ったのは、アメリカ製のロボット。二人は自分たちの無力さを痛感した。「ロボットは実用化しないと意味がない」。研究目的ではなく、災害の現場など、社会の中で活躍するロボットをつくるべく、スタートアップに興味のあった、研究室の後輩とともにSCHAFTを立ち上げた。
SCHAFTの技術の特徴は、強靭で柔軟な下半身、二足歩行のノウハウにある。ヒューマノイド・テクノロジーへの自信と、自分たちがやるしかないという熱意がそこにはあった。著者はSCHAFTの資金提供をして手伝うこととなった。
DARPAロボットコンテストで圧勝
2013年、タイミングよくアメリカ国防高等研究計画局(DARPA)が、災害救助ロボットコンテストを発表した。優勝賞金は200万ドル(約2億円)だ。SCHAFTは、コンテスト優勝により、ヒューマノイド・ロボットの実用化を進めるという目標を掲げた。
コンテストの内容は、現実の災害現場を想定して、ロボットがこなす必要がありそうな作業を8種目行い、その達成度で評価されるというものだ。具体的には、ブロック地面を歩く、がれきを取り除くといった作業である。NASAなどの世界の名だたる強敵と競うには、たいへんな努力と、困難を克服する忍耐強さが求められた。
しかし、SCHAFTはコンテスト一次大会で、他の有力チームに大差をつけて優勝し、世界を驚かせることとなった。勝因は、ロボットの性能だけでなく、実用化へのこだわり、泥臭い現場での対応能力で強みを発揮したことだった。
米グーグルが買収
コンテストの少し前に、米グーグルがSCHAFTを買収すると発表し、話題をさらった。この数カ月前、SCHAFTは資金調達に悩んでいた。ロボットの製品化には時間がかかるため、この段階での投資はチャレンジングだからだ。
そこでCFOの加藤崇氏は、グーグルのアンディ・ルービン氏(当時 上級副社長)に投資をしてもらえないかと依頼した。ロボット技術に精通したアンディはわざわざ来日し、興味津々でデモを見た。その後、SCHAFTの技術力を高く評価したアンディの口から出たのが、買収の提案である。世界中のロボット研究者でドリームチームをつくるというのだ。こんな話は一生に一度あるかないかだ。SCHAFTのメンバーたちは快諾し、心強いスポンサーを手にした。創業メンバーたちが東大の研究室から一歩を踏み出し、尋常とよべない開発を進めた並々ならぬ情熱が、運とチャンスを引き寄せたのである。
プロジェクト開始から約4年後、グーグルはこのプロジェクトを手放すこととなった。しかし、2017年、ソフトバンクに買収され、SCHAFTは次のステージへと向かっている。
SCHAFTのように創業間もないテクノロジー・スタートアップが大企業に買収される例は、アメリカでは一般的で、株式上場よりもはるかに件数が多い。今後、こうした事例は日本でも増えていくはずだ。
大学発イノベーションの創出
レールをつくる側にまわる

革新技術で世界初の製品やサービスを開発し、それが生活を便利にする、あるいは世界の課題解決につながっていく。これは技術者や研究者にとって最高の喜びだ。インターネットの威力とオープンなイノベーション環境により、こうしたチャンスを誰にでも引き寄せられる時代となった。
同時に、スタートアップという選択肢が以前よりも現実的になってきている。日本の若い優秀な人材が、スタートアップ側に回り、イノベーションをリードし、新しい産業をつくることは社会の要請といってもよい。