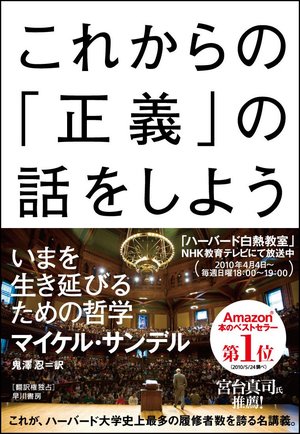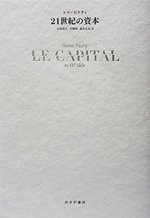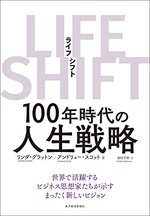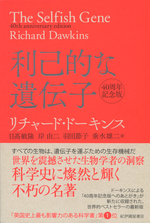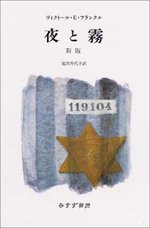これからの「正義」の話をしよう
いまを生き延びるための哲学
著者
マイケル・サンデル
1953年生まれ。ハーバード大学教授。ブランダイス大学を卒業後、オックスフォード大学にて博士号取得。専門は政治哲学。2002年から2005年にかけて大統領生命倫理評議会委員を務める。1980年代のリベラル=コミュニタリアン論争で脚光を浴びて以来、コミュニタリアニズムの代表的論者として知られる。類まれなる講義の名手としても著名で、中でもハーバード大学の学部科目「Justice(正義)」は、延べ14,000人を超す履修者数を記録。あまりの人気ぶりに、同大は建学以来初めて講義を一般公開することを決定、その模様はPBSで放送された
1953年生まれ。ハーバード大学教授。ブランダイス大学を卒業後、オックスフォード大学にて博士号取得。専門は政治哲学。2002年から2005年にかけて大統領生命倫理評議会委員を務める。1980年代のリベラル=コミュニタリアン論争で脚光を浴びて以来、コミュニタリアニズムの代表的論者として知られる。類まれなる講義の名手としても著名で、中でもハーバード大学の学部科目「Justice(正義)」は、延べ14,000人を超す履修者数を記録。あまりの人気ぶりに、同大は建学以来初めて講義を一般公開することを決定、その模様はPBSで放送された
本書の要点
- 要点1正義の意味を探るアプローチには、①幸福の最大化、②自由の尊重、③美徳の促進、の三つの観点が存在する。
- 要点2功利主義の道徳原理は幸福、すなわち苦痛に対する快楽の割合を最大化することである。この考え方の弱みは、満足の総和だけを気にしてしまうため、個人を踏みつけにしてしまう場合があることだ。
- 要点3リバタリアンが主張する自己所有権が認められれば、臓器売買や自殺幇助などの非道徳的行為もすべて容認されることになってしまう。
- 要点4われわれが自らの善について考えるには、自分のアイデンティティが結びついたコミュニティの善について考える必要がある。われわれは道徳的・宗教的信念を避けるのではなく、もっと直接的にそれらに注意を向けるべきだ。
要約
正しいことをする

Noel Hendrickson/Digital Vision/Thinkstock
正義の意味を探る三つのアプローチ
二〇〇四年夏に発生したハリケーン・チャーリーが通り過ぎた後、生活必需品や家屋の修理業者などが通常の価格よりもはるかに高い価格設定を行い、多くの市民がこれを非難した。
ところが、自由市場を支持する者は、値段が高くなれば多くの売り手が参入し、復興が早くなるとして、自由市場に干渉すべきでないと唱える。彼らに言わせれば、価格は個人が自由につけられるもので、公正な価格など存在しないのだ。また一方で、便乗値上げは単なる幸福とか自由とかの話ではなく、不道徳なものとして反対する人もいる。
この便乗値上げをめぐる論争は、道徳と法律に関する難問を提起している。商品やサービスの売り手が自然災害に乗じ、市場でつく価格であればいくらでも請求することは間違っているのだろうか。売り手と買い手が持つ取引の自由に介入することになっても、法律で便乗値上げを禁止すべきなのだろうか。
これらの問題は、個人がお互いをどう扱うべきか、法律はいかにあるべきか、社会はいかに組み立てられるべきかというテーマ、つまり「正義」に関わる問題である。正義の意味を探るアプローチには、便乗値上げ禁止法の問題で見た三つの観点、つまり幸福の最大化、自由の尊重、美徳の促進、が存在する。これらの理念はそれぞれ、正義について異なる考え方を示しており、それぞれに強みと弱みが存在する。本書ではこの幸福、自由、美徳という三つの考え方について検討し、正義についての諸問題を考察している。
最大幸福原理――功利主義

iStockphoto/Thinkstock
他の三人を救うために一人の命を犠牲にしてもよいか
まずは幸福の最大化という考え方について見てみよう。ジェレミー・ベンサムが確立した功利主義の中心概念は、道徳の至高の原理は幸福、すなわち苦痛に対する快楽の割合を最大化することだというものだ。ベンサムによれば、正しい行ないとは、快楽を生み、苦痛を防ぐもの(=「効用」)を最大化するものである。
しかし、功利主義の弱みの一つは個人の権利を尊重しないことだ。満足の総和だけを気にするため、個人を踏みつけにしてしまう場合がある。
一八八四年、四人のイギリス人の船乗りが乗っていた船が、南大西洋の沖合で嵐に遭って沈没した。四人は救命ボートで脱出したが、助かったのは三人だった。三人は雑用係の一人を食料にすることで命をつないだのだ。イギリスに戻ると三人は逮捕され起訴されたが、雑用係を殺さなければ四人全員が死んでいた。功利主義の観点から見れば、四人が死ぬより一人が犠牲になったほうが望ましいということになる。
私は私のものか?――リバタリアニズム(自由至上主義)
自由はどこまで容認されるか
続いて、正義を自由に結びつけるさまざまな理論を取り上げて検討してみよう。
リバタリアンの中心的主張は、どの人間も自由への基本的権利を有しているというものだ。彼らは、経済効率の名においてではなく人間の自由の名において、制約のない市場を支持し、「安全のためにシートベルト着用を義務づける法律」のようなパターナリズム、売春や同性愛の禁止といった道徳的法律、富裕者への課税などの所得や富の再分配を拒否する。
政府による富の再分配に反対する背景は、リバタリアンの持つ自己所有権という概念である。自分が自分を所有しているなら、自分の労働やその成果も所有しているのであるから、政府が強制的に所得の一部を徴収することは、自分が政府に所有されていることになってしまう、という理屈だ。

この続きを見るには...
残り2643/4079文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2013.10.31
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約