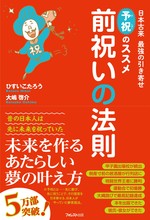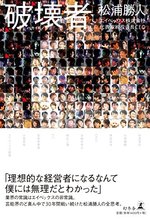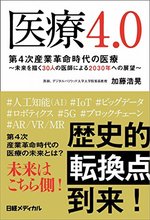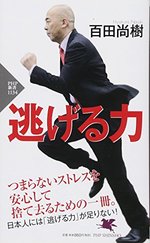耳は1分でよくなる!
薬も手術もいらない奇跡の聴力回復法
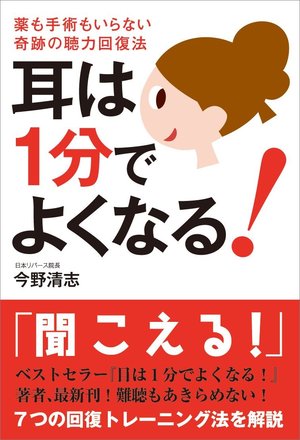
著者
今野 清志(こんの せいし)
1953年、宮城県本吉郡で軍人の父と小学校教師の母親のもとに生まれる。困っている人たちを見過ごせない父親は、毎日、人助けに明け暮れていた。ついには知人の借金の保証人になり、所有していた木材加工工場などすべてを失ってしまう。家にはお金を入れず、酒乱気味だった父だが、人望が厚く、亡くなったとき町で一番多くの人たちが葬式に集まった。著者はこの父親の生き方を見て、「人の役に立つ」人生を選択する。そんな父親をあらゆる面で「超えたい」と体を鍛え、中学では柔道で東北大会のチャンピオンとなる。高校時代も宮城県で1位となったが、高校2年のとき練習のしすぎでヘルニアになり、泣く泣く柔道を断念。代わりに勉強に励み、中央大学法学部入学。在学中は、海外文学に親しみ、演劇を目指したり、政治家を目指したりと、たくさんの可能性を探る。卒業後、予定していた演劇留学がキャンセルとなり、さまざまな運命の偶然から、慈恵医大のアイソトープ科に出向して医学を学ぶ。当時日本で初めてのRIの血液検査を紹介しながら各科の医師との交流を深め、患者を救うには予防医学が最も大切だということに開眼。薬を使わない治療法の確立を、ライフワークとするようになった。そして、中医学に出会い中国に渡り、中国北京国際針灸倍訓中心結業・中国中医研究院で研修などを行う(現在提携院)。30代から東中野・赤羽・銀座・日本橋などに整体治療院を開業。現在は日本橋茅場町本院と東中野分院に開業。
日本リバース院長 目と耳の美容室院長 目と耳の美容学院学院長
ベストセラー『目は1分でよくなる!』(自由国民社)他、著書多数。
1953年、宮城県本吉郡で軍人の父と小学校教師の母親のもとに生まれる。困っている人たちを見過ごせない父親は、毎日、人助けに明け暮れていた。ついには知人の借金の保証人になり、所有していた木材加工工場などすべてを失ってしまう。家にはお金を入れず、酒乱気味だった父だが、人望が厚く、亡くなったとき町で一番多くの人たちが葬式に集まった。著者はこの父親の生き方を見て、「人の役に立つ」人生を選択する。そんな父親をあらゆる面で「超えたい」と体を鍛え、中学では柔道で東北大会のチャンピオンとなる。高校時代も宮城県で1位となったが、高校2年のとき練習のしすぎでヘルニアになり、泣く泣く柔道を断念。代わりに勉強に励み、中央大学法学部入学。在学中は、海外文学に親しみ、演劇を目指したり、政治家を目指したりと、たくさんの可能性を探る。卒業後、予定していた演劇留学がキャンセルとなり、さまざまな運命の偶然から、慈恵医大のアイソトープ科に出向して医学を学ぶ。当時日本で初めてのRIの血液検査を紹介しながら各科の医師との交流を深め、患者を救うには予防医学が最も大切だということに開眼。薬を使わない治療法の確立を、ライフワークとするようになった。そして、中医学に出会い中国に渡り、中国北京国際針灸倍訓中心結業・中国中医研究院で研修などを行う(現在提携院)。30代から東中野・赤羽・銀座・日本橋などに整体治療院を開業。現在は日本橋茅場町本院と東中野分院に開業。
日本リバース院長 目と耳の美容室院長 目と耳の美容学院学院長
ベストセラー『目は1分でよくなる!』(自由国民社)他、著書多数。
本書の要点
- 要点1「聞こえづらさ」はコミュニケーション不良を招き、放置すると日常生活や仕事などに支障が出るばかりか、うつや認知症を発症する恐れもある。
- 要点2耳の不調は体の不調のサインだ。血行不良、内臓疾患、自律神経の乱れが聞こえづらさを招く。これは生活習慣を変えることで改善できる。
- 要点3音を聞いているのは「耳」ではなく「脳」である。脳は聞きたい音だけを選別して聞いている。自分の好きな音をたくさん聞くことで、脳の聴覚を司る部位を活性化することができる。
要約
耳は気づかないうちに悪くなる
難聴は知らず知らずのうちに進行する
誰しも、自分の視力は大体わかるはずだ。一方、多くの人は、自分の聴力を知らない。健康診断の聴力検査でも、大まかな数値しか調べない。
また、人間が話を聞くときは、聞こえてくる音だけでなく、相手の表情や口の動き、話の流れなど、他の情報と合わせて内容を判断している。そのため、多少聞こえが悪くても自覚していないことが多いのだ。こうして多くの人は、知らず知らずのうちに耳が悪くなっていく。
たとえば、難聴の自覚がなくても、呼びかけられても気づかなかったり、早口だと聞き取れなかったり、騒がしい場所だと何度も聞き返してしまったりする人は、聴力が衰え始めている可能性がある。
「聞こえづらい」を放置するリスク

bernardbodo/iStock/Thinkstock
聞こえづらいことに気づいても、「たいしたことない」「そのうち自然と治るだろう」などとそのままにしてしまう人も多い。しかし、聞こえが悪いと、人の話を正確に理解できず、何度も聞き返して相手に迷惑をかけてしまったり、重要な情報を聞き落としてしまったりするかもしれない。こうしたことが続くと、仕事にも支障が出てくるだろう。
話が通じないために口数が減り、自分の世界にこもるようになってしまう人もいる。何ごとにも無気力になり、うつのような症状が出ることも少なくない。
脳への刺激が薄れることにも注意したい。子どもならば発達障害、高齢者ならば認知症になるリスクが高くなってしまうからだ。
耳の不調と全身の不調の関係
難聴の三大原因

Lars Neumann/iStock/Thinkstock
中医学では、人間の体はパーツの寄せ集めではなく、全身がつながっているとされている。したがって、耳の働きが衰えているのは、耳以外の部分にも原因があると考えるのだ。
耳の不調を訴える人に共通する症状は、3つある。
1つ目は、血流の悪化だ。これが耳が悪くなる最大の原因である。人間の体は約37兆個の細胞からなると言われているが、この細胞の活動に必要な栄養素と酸素は、血液によって供給されている。つまり、血流が滞ると、細胞が栄養不足に陥るということだ。耳のように細かな働きをしていて、多くの栄養を必要とする細胞は、特にダメージを受けやすい。
2つ目は、内臓疾患である。中医学では、体を動かすエネルギーである「気」、血液を指す「血」、汗やリンパ液などの「水」の3つの巡りをよくすることが健康につながると考えられている。この「気」と「血」が全身を巡る12本のルートを「経路」といい、お互いに影響しあう。耳は腎臓の経路上にある器官だが、腎臓だけでなく、ほかの内臓の疾患も耳に影響を与えるのだ。西洋医学においても、内臓疾患がある人は難聴になりやすいと考えられている。糖尿病の人は難聴のリスクが3.7倍、腎臓病の人は5.9倍という報告があるほどだ。
3つ目は、自律神経の乱れだ。自律神経とは、心臓の動きや体温の調節など、生きるための体の機能をコントロールする神経だ。自律神経が乱れると、耳の働きが悪くなるだけでなく、前述の「血流の悪化」と「内臓疾患」を引き起こす原因となる。
このように、耳の不調は耳だけの問題ではない。全身の不調と密接に関わりあっている。
耳をよくするには腸をよくしろ
著者はよく、「耳をよくするには腸をよくしろ」と言う。なぜなら、

この続きを見るには...
残り2975/4315文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2018.09.30
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約