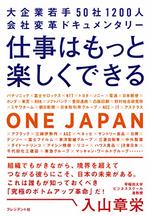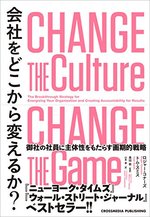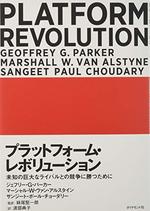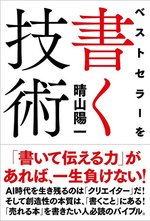パーパス・マネジメント
社員の幸せを大切にする経営
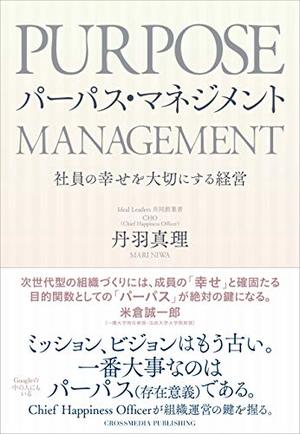
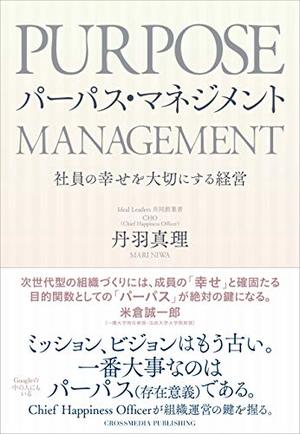
著者
丹羽 真理 (にわ まり)
Ideal Leaders株式会社 共同創業者/CHO(Chief Happiness Officer)
国際基督教大学卒業、University of Sussex大学院にてMSc取得後、2007年に株式会社野村総合研究所に入社。民間企業及び公共セクター向けのコンサルタントとして活動後、エグゼクティブコーチングと戦略コンサルティングを融合した新規事業IDELEA(イデリア)に参画。2015年4月、Ideal Leaders株式会社を設立し、CHO(Chief Happiness Officer)に就任。社員のハピネス向上をミッションとするリーダー「CHO」を日本で広めることを目指している。経営者やビジネスリーダー向けのエグゼクティブコーチング、Purposeを再構築するプロジェクト等の実績多数。特定非営利活動法人ACEの理事も務める。
URL:http://ideal-leaders.co.jp
Ideal Leaders株式会社 共同創業者/CHO(Chief Happiness Officer)
国際基督教大学卒業、University of Sussex大学院にてMSc取得後、2007年に株式会社野村総合研究所に入社。民間企業及び公共セクター向けのコンサルタントとして活動後、エグゼクティブコーチングと戦略コンサルティングを融合した新規事業IDELEA(イデリア)に参画。2015年4月、Ideal Leaders株式会社を設立し、CHO(Chief Happiness Officer)に就任。社員のハピネス向上をミッションとするリーダー「CHO」を日本で広めることを目指している。経営者やビジネスリーダー向けのエグゼクティブコーチング、Purposeを再構築するプロジェクト等の実績多数。特定非営利活動法人ACEの理事も務める。
URL:http://ideal-leaders.co.jp
本書の要点
- 要点1「働き方改革」の本質は、誰もが幸せに働ける社会を実現することにある。そのためには、労働時間の長短ではなく、社員の幸福度にフォーカスすることが重要だ。
- 要点2社員の幸福度が高いほど組織のパフォーマンスが高まり、会社の業績向上にもつながることが様々な科学的データで実証されている。
- 要点3社員の幸福度を高めるのに大切なのは、個人と組織の存在意義=Purposeを合致させることである。
- 要点4社員の幸せを組織的にデザインする「CHO=Chief Happiness Officer」の役割は、経営職でなくとも、社員一人ひとりが担うことが可能だ。
要約
会社が追求すべきは「幸せ」
働く時間が短くなっても、社員は幸せになれない

wildpixel/gettyimages
世間ではいま、「働き方改革」が大流行りである。この取り組みは、「50年後も人口1億人を維持し、職場・家庭・地域で生きがいを持って、誰もが活躍できる社会」をめざすものである。これは、「生産性革命」の実現に向けた幅広い政策パッケージでもある。
中でも長時間労働の改善は、「働き方改革」の主要な取り組みのひとつだ。労働時間に着目した取り組みには、残業時間を減らす時短やプレミアムフライデーなどもある。しかし、労働時間の短縮または残業代の減少が目的化し、「時短ハラスメント」という言葉まで生まれる結果となっている。
はたして、こうした労働時間の短縮は、社員がいきいきと働ける環境作りに有効な打ち手なのか。著者の体験からいえば、働く時間が短くなったことは自身の幸せにはつながらなかったという。著者はコンサルタントのアシスタントとして多忙な3年間を過ごした後、スタッフ部門に異動となった。同じ給料で残業時間が減ったにもかかわらず、その状況を喜ばしいとは思えなかった。むしろ「自分らしくない」と感じたほどだった。
「働き方改革」の本質は「幸せ改革」
「働き方改革」の本来の目的は、多様で柔軟な働き方を可能にして、誰もが幸せに働ける社会を実現することにある。働く時間だけが減ってその分忙しさは増していく。そのうえ残業代がなくなった分、収入が減ったのでは、社員は踏んだり蹴ったりである。真に社員がいきいきと働ける職場環境を作りたいなら、時間や賃金ではなく「幸せ」にフォーカスする必要がある。
では、仕事における「幸せ」とは何なのか。著者の場合、部門異動により残業が減っても、それを幸せだと感じられなかった。その一番の要因は、異動先での仕事の意義を見いだせなかったことであった。著者の思いは「日本をよりよい社会にしたい」というもの。そしてコンサルタントという仕事は、その実現に貢献しているという実感を与えてくれた。ところが、異動により、個人と組織の存在意義がズレてしまって、幸せを感じられなくなったのだ。
社員が仕事にやりがいを見いだし、楽しみながら、熱意を持って働くこと、それが幸せに働くということだ。肝心なのは、労働時間の長短ではない。自分と組織の存在意義(=Purpose)が一致していれば、社員はいきいきと働ける。するとパフォーマンスもおのずと向上して、会社の業績は上向いていく。「働き方改革」の本質は、誰もが幸せに働く「幸せ改革」なのである。
社員の幸せの追求が会社に利益をもたらす
「働き方改革」は「生産性革命」の実現をめざしたものである。それなのに、日本の労働生産性は、G7の中で長年最下位を記録している。こうした現状から、国は労働生産性の向上を「長時間労働の削減」と結びつけてしまっているのだ。
労働生産性とは、労働による付加価値を、労働量で割った値である。この値が大きければ、労働生産性が高いということになる。長時間労働の削減は、分母にあたる労働量を減らすため、労働生産性の向上に直結する。経営側にしても、人件費削減という目に見える効果があるため着手しやすい。しかし、このアプローチには「時短ハラスメント」になるリスクがあり、中長期的に見ると有効な打ち手とはいえない。
労働生産性を向上させるには、分子となる付加価値を大きくする方が効果的だ。そして付加価値の増大に効果的なのは、社員の幸せを追求することである。社員の幸福度が高まれば、イノベーションを生みだす力が大きくなる。ひいては会社の利益の増大につながり、労働生産性が高まる。
【必読ポイント!】 幸せとパフォーマンスの相関関係
幸せの測定

MarBom/gettyimages
「幸せ」の定義は人それぞれだ。残業時間や離職率などと違って、容易に数値化できるものではない。ところが、いま国家レベルで「幸福度」を測定しようとする動きが広がっている。

この続きを見るには...
残り2692/4295文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2018.11.26
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約