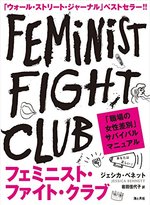セゾン
堤清二が見た未来


著者
鈴木 哲也(すずき てつや)
日本経済新聞社 企業報道部次長
1969年生まれ。1993年早稲田大学法学部卒業、同年日本経済新聞社入社。小売業、アパレル、食品メーカー、外食・サービス業など消費に関連する企業を中心に取材してきた。2003年から2007年、米州総局(ニューヨーク)で、ウォルマートなどの企業取材を担当。企業報道部次長などを経て、2015年日経BP社に出向し、「日経ビジネス」副編集長。2018年10月から現職。
日本経済新聞社 企業報道部次長
1969年生まれ。1993年早稲田大学法学部卒業、同年日本経済新聞社入社。小売業、アパレル、食品メーカー、外食・サービス業など消費に関連する企業を中心に取材してきた。2003年から2007年、米州総局(ニューヨーク)で、ウォルマートなどの企業取材を担当。企業報道部次長などを経て、2015年日経BP社に出向し、「日経ビジネス」副編集長。2018年10月から現職。
本書の要点
- 要点1本書は、セゾングループ各社の栄光と苦闘の軌跡をたどりながら、堤清二の人間像に迫っていく。
- 要点2無印良品は高級ブランドブームのアンチテーゼとして誕生した。「消費者の自由の確保」を核とした無印商品は、堤の思想の結晶といえた。
- 要点3赤字百貨店だった西武百貨店は、堤が打ち出したイメージ戦略などが奏功し、1987年度には売上高業界1位となった。しかし、堤の理想を実現するためのこだわりがコストを押し上げ、経営の足かせとなった。
要約
【必読ポイント!】 無印良品
無印良品は堤清二の「自己否定」から生まれた

Scovad/gettyimages
セゾングループが生み出した先駆企業の栄光と苦闘を、本書は克明に描き出している。無印良品を展開する良品計画、西武百貨店、パルコ、ロフトやリブロなどの専門店、グループ解体の序章となった西洋環境開発を中心としたホテル・レジャー産業。つづいて、吉野家を買収し、ファミリーマートを生みながらも、堤清二が一定の距離を置こうとしたチェーンオペレーション。本書はこうした順に構成され、最後に堤清二という人間像に迫っていく。本要約では、無印良品、西武百貨店、そしてグループ解体劇を中心にとりあげる。
では、堤が53歳という経営者人生の後半戦で生み出した無印良品が最初にくるのはなぜなのか。それは無印良品が、堤が痛烈な自己否定の精神を発揮し、その思想の結晶としてつくり上げたものだからだ。
「反体制商品」の誕生前夜
セゾン文化の絶頂期である1980年、堤が世に放ったのが無印良品である。ロゴマークがついていれば商品が高く売れる。そして高級ブランドを身につけた人を見た消費者が、焦りと羨望から真似をする――。こうした消費社会に堤は異議を申し立てた。ブランド至上主義の行き詰まりを予見した堤は、無印良品を「反体制商品」と呼んだ。無印良品は、西武百貨店を通じた高級ブランドブームの火付け役となった堤の、自己否定そのものといえた。
当時ダイエーなどが先行していた格安のノーブランド商品が想起するイメージは、「安かろう悪かろう」だった。この印象を塗り替えられなければ、いくら節約志向が浸透しても、消費者に飽きられてしまう。そんな難題の突破口となったのは、堤がクリエイティブチームとともに構築した、新しい形のノーブランド商品だった。
アートディレクターの田中一光、クリエイティブディレクターの小池一子、インテリアデザイナーの杉本貴志。クリエイティブチームには、堤の事業で才能を発揮してきた人材が集まった。堤と文化論などを語り合いながら、商品の個性とコンセプトを固めていった。
彼らの共通認識は、「ロゴマークだけが一人歩きしてしまうのは生活者の感覚から離れている」というものだった。欧州の高級ブランド全盛期に、日本のものをきちんとつくりたい。そこで生まれた案が無印良品である。ノーブランドだけど品質はよく、飾りのない日本語。堤は即決した。
こうして、無印良品は西友のPB(プライベートブランド)という位置づけでスタートした。「他のスーパーのノーブランド商品はわけありげの商品。西友のはわけあり商品」。素材の選択、工程の点検、包装の簡略化。価格を安くできる理由を、パッケージなどを通じて、消費者にきちんと説明した。これにより「品質は一流」というイメージが浸透していった。
核となるのは「消費者の自由の確保」

g-stockstudio/gettyimages
誕生から3年後、独立路面店の出店により、無印良品は一気に認知度を高めていった。1号店をオープンさせたのは青山の一等地。欧州の高級ブランドの路面店が立ち並ぶファッションの街に進出し、地味な無印良品をぶつけたい。そんな無謀な挑戦だった。センスのよい店構えでありながら、安価で飾りのない食品や雑貨が売られている。このユニークなギャップが世間の話題をさらった。商品の色やデザイン、パッケージの統一性から生まれるイメージ形成力は、無印良品の強みでもあった。
核となるコンセプトは、「消費者の自由の確保」である。アイテム数が増え、コンセプトが拡散しそうになるたびに、堤らは商品と向き合い、創業時のテーゼを愚直に確認してきた。
しかし、事業を軌道に乗せるマネジメント力が軽視されがちだったことは否めない。堤の掲げる理念と現実のビジネスのはざまで苦労したのが、1985年、無印良品事業部の初代部長に起用された木内政雄だ。「品質を良くし、品ぞろえをしっかりとさせる。問屋取引をやめて粗利を高める。それで確実に利益は上がる」。そんな信念のもと、硬直化しつつあった西友の影響が及ばぬよう、無印良品の分社化を実現。事業を拡大させた木内は1993年、良品計画の社長に就任した。
売却、業績悪化を乗り越え、商品の原点へ
バブル崩壊後、セゾングループも銀行団からの圧力によって巨額負債への対応を迫られた。挙句には、西友が、ファミリーマートと良品計画の株式売却にまで追い込まれた。セゾングループの「突然死」は避けられたものの、堤に対し、社内外で「セゾングループを経営難に陥れたオーナー経営者」という印象が強まっていった。

この続きを見るには...
残り2719/4571文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2018.12.07
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約