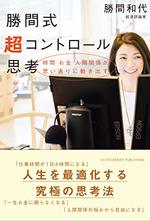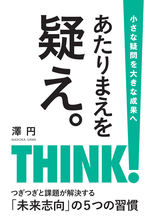スタンフォード大学西野教授が教える
間違いだらけの睡眠常識
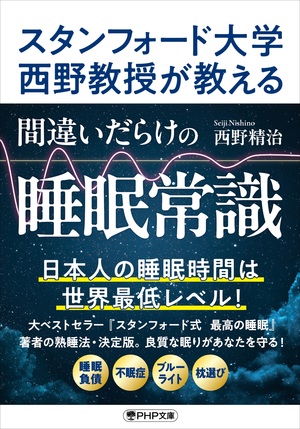
著者
西野精治(にしの せいじ)
スタンフォード大学医学部精神科教授、同大学睡眠生体リズム研究所(SCNL)所長。医師、医学博士、日本睡眠学会専門医。1955年、大阪府出身。大阪医科大学卒業。1987年、大阪医科大学大学院4年在学中、スタンフォード大学精神科睡眠研究所に留学。
突然眠りに落ちてしまう、慢性の原発性過眠症である「ナルコレプシー」の病態生理・病因の解明の研究に主として携わっており、1999年、家族性イヌナルコレプシーでその原因遺伝子(ハイポクレチン/オレキシン受容体)を発見、2000年にはナルコレプシーの
発生メカニズムを突き止めた。2005年にSCNLの所長に就任。睡眠・覚醒のメカニズムを、分子・遺伝子レベルから個体レベルまでの幅広い視野で研究している。日本人として初のスタンフォード大学医学部教授。
株式会社ブレインスリープ、創業者兼最高研究顧問。著書に「睡眠負債」の実態と対策を明らかにしベストセラーとなった『スタンフォード式 最高の睡眠』 (サンマーク出版)、『スタンフォード式お金と人材が集まる仕事術』 (文春新書)等。2022年、シフトワーカーのウェルビーイングをテーマにNOBシフトワーク研究会を設立し会長に就任する。
スタンフォード大学医学部精神科教授、同大学睡眠生体リズム研究所(SCNL)所長。医師、医学博士、日本睡眠学会専門医。1955年、大阪府出身。大阪医科大学卒業。1987年、大阪医科大学大学院4年在学中、スタンフォード大学精神科睡眠研究所に留学。
突然眠りに落ちてしまう、慢性の原発性過眠症である「ナルコレプシー」の病態生理・病因の解明の研究に主として携わっており、1999年、家族性イヌナルコレプシーでその原因遺伝子(ハイポクレチン/オレキシン受容体)を発見、2000年にはナルコレプシーの
発生メカニズムを突き止めた。2005年にSCNLの所長に就任。睡眠・覚醒のメカニズムを、分子・遺伝子レベルから個体レベルまでの幅広い視野で研究している。日本人として初のスタンフォード大学医学部教授。
株式会社ブレインスリープ、創業者兼最高研究顧問。著書に「睡眠負債」の実態と対策を明らかにしベストセラーとなった『スタンフォード式 最高の睡眠』 (サンマーク出版)、『スタンフォード式お金と人材が集まる仕事術』 (文春新書)等。2022年、シフトワーカーのウェルビーイングをテーマにNOBシフトワーク研究会を設立し会長に就任する。
本書の要点
- 要点1睡眠は謎が多い分野だ。適正な睡眠時間や、どの程度の睡眠不足があるかもはっきりわかっていない。
- 要点2人それぞれ、適正な睡眠時間がある。睡眠時間がそれに満たなければ、「睡眠負債」として睡眠の借金がたまっていく。睡眠負債は眠ることでしか解消できない。
- 要点3睡眠の質を向上させるには、寝入りばなのノンレム睡を深くしっかりと眠れるようにすることが重要だ。このとき、細胞の増殖や正常な代謝の促進などの役割を果たす「グロースホルモン(成長ホルモン)」の70~80%が分泌される。
要約
間違いだらけの睡眠常識
努力すれば「ショートスリーパー」になれる?
睡眠時間を削ることを「美徳」と捉えがちな日本人は、睡眠時間を短縮できたらもっとパフォーマンスを上げられると考える人が少なくない。ナポレオンやエジソンは睡眠時間が短くても平気な「ショートスリーパー」として有名で、3〜4時間睡眠だったといわれている。
まず知っておきたいのは、睡眠時間の長短は遺伝的資質に規定されるところが大きいということだ。「トレーニングすれば誰でもショートスリーパーになれる」と主張する人もいる。だが、短時間睡眠の因子をもっていない人がそれをやろうとしても、睡眠負債がたまっていくだけだ。本当に睡眠時間が短くても大丈夫なショートスリーパーは、じつは全体の1%未満にすぎない。
睡眠は謎だらけ?

Kkolosov/gettyimages
かつて睡眠は受動的な意識消失状態と考えられていて、魅力的な研究対象ではなかった。睡眠が研究対象として注目されるようになった契機は、1953年のレム睡眠の発見だ。レム睡眠の発見とほぼ同時期に、睡眠・覚醒は脳の自発的な活動によって引き起こされているという概念が提唱され、研究が進められるようになった。また睡眠に関係した病気についても徐々にわかってきて、「睡眠医学(sleep medicine)」という学問が形成されてきた。
しかし、睡眠の深さも睡眠の質も、いまなおその本質はわかっていない。適正な睡眠時間も、どの程度の睡眠不足があるかもはっきりとはわからない。睡眠中の現象としてはわかっていても、そのメカニズムが不明のものもある。睡眠について明らかになっていることは、まだ全体の10%にも満たないのではないかと著者が言うほどに、謎多き分野なのだ。
【必読ポイント!】 睡眠負債
眠りの借金は眠りでしか返せない
「ヒトは一定の睡眠時間を必要としており、それよりも睡眠時間が短ければ、足りない分がたまる。つまり眠りの借金が生じる」――これが睡眠負債(sleep debt)である。借金がたまると、脳や身体にさまざまな機能劣化が起こり得ると考えられている。

この続きを見るには...
残り3205/4060文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2025.03.07
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約