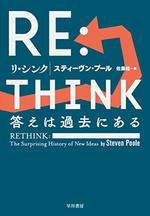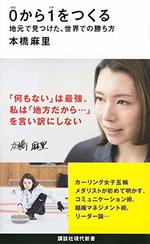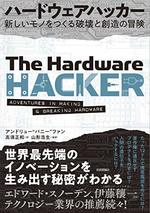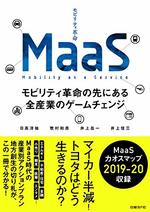ブロックチェーン・AIで先を行くエストニアで見つけた つまらなくない未来

著者
小島 健志 (こじま たけし)
1983年生まれ。東京都出身。早稲田大学商学部卒業後、毎日新聞社を経て、2009年にダイヤモンド社入社。週刊ダイヤモンド編集部で、エネルギー、IT・通信、証券といった業界担当の後、データ分析を担当。主な担当特集に「『孫家』の教え――起業家に学ぶ10年後も稼げる条件」「大学序列」「データ分析」「儲かる農業」など。また、孫泰蔵氏の連載「孫家の教え」も担当。2018年よりハーバード・ビジネス・レビュー編集部に移る。30歳を過ぎてからプログラミングや統計を学びはじめ、Oracle Certified Java Programmer Silver SE 7、統計検定2級を取得し、DataMixデータサイエンティスト育成コース第5期卒業。
1983年生まれ。東京都出身。早稲田大学商学部卒業後、毎日新聞社を経て、2009年にダイヤモンド社入社。週刊ダイヤモンド編集部で、エネルギー、IT・通信、証券といった業界担当の後、データ分析を担当。主な担当特集に「『孫家』の教え――起業家に学ぶ10年後も稼げる条件」「大学序列」「データ分析」「儲かる農業」など。また、孫泰蔵氏の連載「孫家の教え」も担当。2018年よりハーバード・ビジネス・レビュー編集部に移る。30歳を過ぎてからプログラミングや統計を学びはじめ、Oracle Certified Java Programmer Silver SE 7、統計検定2級を取得し、DataMixデータサイエンティスト育成コース第5期卒業。
本書の要点
- 要点1エストニアは電子政府の先進国である。ほとんどの行政手続きはオンラインで完結し、契約にも紙の書類は必要ない。電子署名の普及で「ハンコ」や「サイン」は過去のものとなった。
- 要点2「イーレジデンシー」はIT立国エストニアを象徴する、他に類を見ない制度だ。オンラインで申請すれば、世界の誰もがこの国の仮想住民となることができ、起業や雇用契約などを電子的に行うこともできる。
- 要点3無料オンライン通話サービス「スカイプ」は、多くのエストニア人によって開発された。この成功体験がベースとなり、現在エストニアは多くのユニコーン企業を輩出するスタートアップの聖地になりつつある。
要約
電子政府エストニアの正体
「ハンコ」も「書類」もない国で

dk_photos/gettyimages
「とてもクールなギフトよね。日本人はみんな、これを署名として利用しているのよね」
エストニアの女性がそう言いながら手に取ったのは、日本で外国人向けに売られているお土産用のハンコだ。「私たちの国には、ハンコもサインもない。行政書類にも契約書類にもコンピューターを使って電子署名をするのよ」
バルト三国のひとつであるエストニアは、人口約130万人の小国ながら電子政府を実現し、いま世界から注目を浴びている国だ。すべての国民に11桁のデジタルIDを記したカードを発行し、このカードに内蔵されている電子証明書を用いることで、納税や選挙、医療など、日常生活に必要な手続きはほとんどオンラインで完結する。
たとえば確定申告なら数分で手続きが完了し、選挙では電子投票の比率が3割を超える。医療でもメールやスカイプなどで医師から検査結果の説明を受けることができ、必要な薬は薬局でIDカードを示せば受け取れる。
電子化されていないのは「感情的に早まってはいけない」という理由から結婚・離婚の届けと、大きな金額が動く不動産売却ぐらいだ。
「何もない国」だからITに賭けた
エストニアが先進的な電子政府システムを構築した背景には、決して幸福だったとは言えない歴史がある。約100年前の1918年に建国したこの国は、長きにわたってナチス・ドイツや旧ソ連の支配下にあった。独立を果たしたのはごく最近、1991年のことだ。
行政の中心を担っていたソ連の人々が去った後、エストニアは「誰が国民か把握する」「法律をつくる」「通貨制度を整える」という、国としてきわめて基礎的なところから対応を迫られた。混乱の中で国民が流出し、GDPも3割以上少なくなるという危機的状況を乗り切れたのは、若きリーダーの決断と、この国が有していた頭脳があったからだ。
もともとエストニアは数学教育の水準が高く、旧ソ連が軍事技術の研究所やデータセンターを置いていたため、関連する技術者が数多く残っていた。そこで32才の若き首相、マルク・ラール氏を中心とした指導層は、コストを抑えながら行政サービスを提供するためITに賭け、見事成功を収めた。
「エックスロード」でITコストを削減

gorodenkoff/gettyimages
行政手続きのオンライン化をはじめとした電子政府の実現には、住民情報や企業情報、税、免許といった情報を一元化することが不可欠である。この実現には「スーパーデータベース」の構築、つまりそれぞれのデータベースにあるデータを集約するのが一般的だが、それには非常にコストがかかる。
エストニア政府はスーパーデータベースの代わりに、「エックスロード(X-Road)」というバラバラのデータベースをつなぐシステムを構築し、既存のデータベースに改修を加えることなく、低コストでのデータの集約を可能とした。
さらにエストニア政府はITコスト低減を徹底するため、行政機関が同じデータを複数のデータベースに登録することを法律で禁じた。たとえば住民の氏名や生年月日といった情報ならば住民情報データベースだけに登録し、エックスロードを通じて他のシステムに提供することで、情報管理をシンプルかつ効率的に行う仕組みを整えている。
「ブロックチェーン国家」と呼ばれる理由
どのようにプライバシーを守るのか
電子政府の利便性が上がるほど、個人に関するデータの扱い、とりわけプライバシーの問題は避けて通れない。しかしエストニアでは、「透明性」を徹底することでこれを乗り越えた。
たとえばデジタルIDでログインすると表示される個人用ページでは、自分の情報が「いつ」「誰に」利用されていたのか、逐一記録が残るようになっている。しかも不正に他人のデータを利用すれば、罰金や懲役などの重い刑事罰が課される。過去には警察官や医師といった、多くの個人データを扱う職業の者が処罰された例もある。
サイバー攻撃を機に独自ブロックチェーン技術を導入
エックスロードとともに、エストニアの電子政府を支えるのが「KSI(キーレス署名)ブロックチェーン」だ。これはリアルタイムでデータの改ざんを検知する技術で、流通するデータには1秒ごとに「指紋」がつけられ、誰がいつどのような変更を行ったのか検証できるようになっている。
エストニアがこの技術を導入したのは2007年、ロシアからと見られる大規模なサイバー攻撃を受けて政府や銀行のサーバーがダウンし、日常生活にも影響が及ぶ事態となったのがきっかけだ。このときはデータ消失や改ざんといった被害はなかったが、関係者は「もし不正にデータが書き換えられ、正しいデータがどれかわからなくなったら」という危機感を抱いた。
そこでエストニアはNATOのサイバー防衛協力センターを誘致して防御を固めると同時に、「マークルツリー」と呼ばれるブロックチェーンの要素技術のひとつを導入、膨大なデータのひとつひとつに対する変更を検証できるようにした。
仮想住民政策は、安全保障政策

KavalenkavaVolha/gettyimages
2014年末、エストニアは「イーレジデンシー」と呼ばれる制度をスタートした。これは政府が外国人を「仮想住民」として認め、仮想居住権を与えるというものである。オンラインで必要事項を入力して申請すると、エストニア大使館に呼び出される。大使館で説明を受け、指紋を登録してデジタルIDカードを受け取れば完了である。
仮想住民になる大きなメリットは、オンラインで法人設立ができるようになることだ。つまり日本にいながら、EUの5億人の市場にアクセスできる。税制面の優遇もあり、仮想住民となって法人を設立する者は増え続けている。
しかしエストニアは、ペーパーカンパニーが乱立するタックスヘイブンを目指しているわけではない。この小国をアピールするブランディング活動という面もあるが、最大の目的は安全保障だ。ウクライナ領クリミアがロシアに編入されたという出来事は、同じく旧ソ連の一部だったエストニアに大きな危機感を抱かせた。国際世論への影響力を増し、ロシアへの抑止効果をあげるには仮想住民、つまりバーチャルな国民を増やすことが最善策と考えたのである。
エストニアで見つけた未来
グローバルフリーランサーの拠点に
エストニアがイーレジデンシー政策を進めている目的は安全保障だけではない。西欧に地続きの小国であるため優秀な人材が流出しやすく、また日本と同じく少子高齢化に悩んでいるこの国が狙うのは、ITを利用した産業の育成と、「グローバルフリーランサー」を惹き付けることだ。グローバルフリーランサーとは、国境を超えて活躍する高度な職業能力を持った個人のことで、エストニアはこのような人々が集う拠点になろうとしている。
その代表的な取り組みのひとつが、世界各地の求人情報を提供している「ジョバティカル」というスタートアップで、「旅しながら働く」というグローバルフリーランサーならではの新しい働き方を提案している。またイーレジデンシー制度を利用して仮想住民になれば、ジョバティカルで見つけた仕事に就く際の雇用契約もオンラインで完結できる。
加えてエストニアは「デジタルノマドビザ」という制度も構想している。これは仮想住民に365日の居住権を与えるビザで、申請すればEU各国にも90日以内の居住が認められるというものだ。実現すれば、世界で1億人ともいわれるグローバルフリーランサーにとって魅力的な制度となることは間違いない。
スカイプを生んだ国
無料オンライン通話サービス「スカイプ」を利用している人は多いだろう。このサービスの開発には、エストニア人が深く関わっていた。2005年にスカイプが約2800億円でイーベイ社に買収されたとき、多額のストックオプションを得たエストニアの開発者は100名以上にも上る。彼らは国民に「小さい国からも世界に通用するサービスを生み出すことができる」という勇気を与え、この国がIT立国となる礎を築いた。
スカイプ出身者はその後、ユニコーン企業を次々と立ち上げ、「スカイプ・マフィア」と呼ばれるようになる。スカイプと同じくP2P(ピア・ツー・ピア)技術を用いた送金サービス「トランスファーワイズ」、タクシー配車サービスの「タクシファイ」などが代表格だ。
現在は若いスタートアップが次々と生まれ、もはやスカイプ・マフィアも時代遅れになりつつある。「エストニアン・マフィア」というのが、スカイプの次世代の起業家たちの呼び名だ。
教育をデジタル化する

gorodenkoff/gettyimages
教育水準を国際的に評価できる指標として、日本でもしばしば持ち出される学力到達度調査PISA。OECDが世界72の国・地域を対象に行っている調査であるが、2015年の結果でエストニアは教育大国フィンランドを抜いて欧州でトップを獲得し、世界から注目を集めた。特に「科学」の分野は世界第3位と、同程度の経済力を有する国と比べると突出している。
建国当時に行政の電子化と同様、教育現場でもITの徹底活用を決断したエストニア。現在はパソコンやインターネットの導入はもちろん、9割近い学校でコンピューターサイエンスの授業が行われており、一部の学校ではプログラミングやおもちゃのロボット制御なども教えられている。
ITが取り入れられているのは授業だけではない。学校と家庭との情報共有には「イースクール」というシステムが取り入れられ、児童・生徒それぞれの出欠や宿題の状況、テストの結果などがすべて記録され、教員のコメントも付く。また詳細な記録を残すため、20人ほどの児童に教員が2人つき、そのうちの1人が入力作業をすることもある。
ITバブルがはじけた不況下でも、エストニアは教育予算を増やし続けた。なぜここまで教育、特にIT分野に投資するのか。それはグローバルな社会でエストニアという小国が存在感を示すには、発想を生み出し実現するアントレプレナーシップの発揮が最も有効だと考えているからだ。

この続きを見るには...
残り0/4038文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2019.03.18
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約