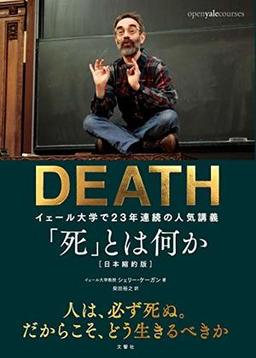死について
魂は存在しない
死について考えるときに重要なのは、「二元論」と「物理主義」の見方を区別することだ。二元論者は人間を「身体と心の組み合わせだ」と主張する。二元論者にとって心とは魂そのもの、もしくは魂に収まるものだ。一方で物理主義者は、精神的活動としての心は否定しないものの、魂なるものは存在しないと考えている。この立場からすると、心はあくまで身体の持つ能力のひとつにすぎない。
著者は後者の立場に立つ。たしかに人間は“驚くべき物体”であり、他の物体にはない機能をいくつも持っている。だが「人(魂)は自分の身体の死後も存在し続ける」という主張は論拠を欠いている。私たちが有形物であることは間違いなく、そういう意味では機械と根本的には変わらない。ゆえに身体が死ねば、その人も消滅するのは必然ということになる。
自分は「身体」に宿っている

死について考えるのが厄介なのは、逆説的に「そもそも生き続けるとはどういうことなのか」という疑問にぶち当たるためである。私たちは過去・現在・未来の自分を同一の存在と見なすが、そもそもそれはなぜか。この問題に対する立場は大きく分けて3つある。(1)「魂説」、(2)「身体説」、(3)「人格説」だ。
二元論者は大抵の場合、「魂」をその根拠に見出している。これが(1)「魂説」である。「魂説」によれば、身体と魂は別のものだから、身体がどう変わったとしても(あるいは肉体が消滅したとしても)、魂さえ変わらなければ同一の存在と見なされる。
一方で物理主義者の多くは、(2)「身体説」を採用している。身体さえ一致していれば、それは同一の存在と見なすという考えだ。なおここでの「身体」は、原子レベルですべて同じということを意味しない。身体の構成要素は定期的に入れ替わるからだ。
「身体説」にはいくつかのバージョンがあり、著者のように「脳」が同じであれば、他の身体が変わっても同一の存在だと考える人もいる。いずれにせよこの説を採用した場合、身体(脳)の死はそのまますべての終わりを意味する。
興味深いのが(3)「人格説」だ。これは二元論者にも物理主義者にも受け入れられる余地がある。この考えに従うと、同じ信念や欲望、記憶などの集合である「人格」が同じであれば、同一の存在と見なされる。なお「身体説」と同じく、少しずつ構成要素が入れ替わることは問題視しない。基本的には同じ身体(脳)を持つ=同じ人格を持つという点で「身体説」に近いが、身体と人格を分離可能なものと捉えれば、「魂説」にも接近しうる。とはいえ現時点では別の身体に自分の人格を「アップロード」する技術はないので、この説もいまのところ「死」については身体説と同じ立場をとっている。
死は不思議な現象ではない

物理主義者にとって、人間とは正常に機能している身体にすぎない。考えたり感じたりできる身体を、本書では「P機能(人格機能)を果たしている」と表現する。この考えを受け入れる場合、人間はいつ死ぬことになるのかを考えてみたい。
一見すると答えは単純に思える。