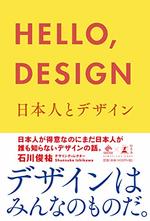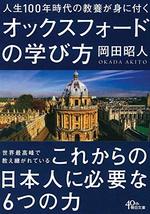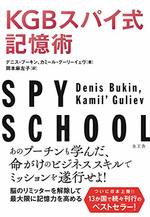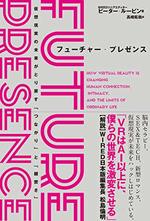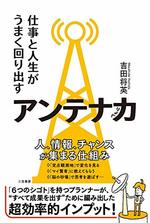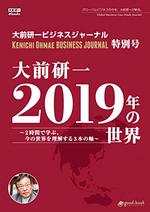THE VISION
あの企業が世界で成長を遂げる理由
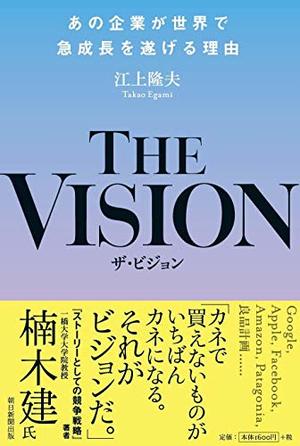
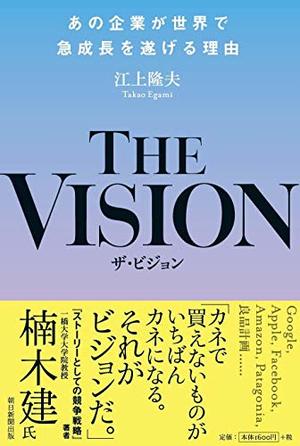
著者
江上 隆夫 (えがみ たかお)
株式会社ディープビジョン研究所 代表取締役
ブランド戦略コンサルタント
「本質からブランドを組み立てる」というアプローチで、全国の中小企業から大企業までのブランドづくりを行っている。
長崎県五島列島出身。大学卒業後いくつかの広告制作会社を経て18年近く大手広告代理店アサツーディ・ケイでコピーライター及びクリエイティブ・ディレクターとして、さまざまな業種の企業広告キャンペーンやブランド構築にかかわる。朝日広告賞、日経広告賞グランプリ、日経金融広告賞最高賞、東京コピーライターズクラブ新人賞ほか数多くの受賞で評価を高め、2005年に独立。現在は、クリエイティブを行う「ココカラ」と、ブランド・コンサルティングやセミナーなどを行う「ディープビジョン研究所」の2社を経営している。
企業全体を俯瞰的に見るデータ的・マーケティング的に捉える手法、企業カルチャーや独自性などから価値を引き出すデザイン思考的手法、ビジョンやミッション、コンセプトなどを引き出すクリエイティブ的手法の、三つの手法を組み合わせた“ESSENNTIAL BRANDING”(エッセンシャル・ブランディング)を提唱。数億から百億を超える規模のブランド運営にかかわり、数多くの企業、経営者に支持されている。
最近はブランディングやコンセプトづくりなどの企業研修、イノベーションスキルを開発する事業、個人向けにブランディングを教える塾“創風塾”を主宰するなど、活動の幅を広げている。
著書にロングセラーになっている『無印良品の「あれ」は決して安くないのになぜ飛ぶように売れるのか?』『降りてくる思考法』(いずれもSBクリエイティブ刊)。開発商品に発想支援のための「イノベーションカード」(デキル。株式会社 / イノベーションデザイン協会)などがある。
株式会社ディープビジョン研究所 代表取締役
ブランド戦略コンサルタント
「本質からブランドを組み立てる」というアプローチで、全国の中小企業から大企業までのブランドづくりを行っている。
長崎県五島列島出身。大学卒業後いくつかの広告制作会社を経て18年近く大手広告代理店アサツーディ・ケイでコピーライター及びクリエイティブ・ディレクターとして、さまざまな業種の企業広告キャンペーンやブランド構築にかかわる。朝日広告賞、日経広告賞グランプリ、日経金融広告賞最高賞、東京コピーライターズクラブ新人賞ほか数多くの受賞で評価を高め、2005年に独立。現在は、クリエイティブを行う「ココカラ」と、ブランド・コンサルティングやセミナーなどを行う「ディープビジョン研究所」の2社を経営している。
企業全体を俯瞰的に見るデータ的・マーケティング的に捉える手法、企業カルチャーや独自性などから価値を引き出すデザイン思考的手法、ビジョンやミッション、コンセプトなどを引き出すクリエイティブ的手法の、三つの手法を組み合わせた“ESSENNTIAL BRANDING”(エッセンシャル・ブランディング)を提唱。数億から百億を超える規模のブランド運営にかかわり、数多くの企業、経営者に支持されている。
最近はブランディングやコンセプトづくりなどの企業研修、イノベーションスキルを開発する事業、個人向けにブランディングを教える塾“創風塾”を主宰するなど、活動の幅を広げている。
著書にロングセラーになっている『無印良品の「あれ」は決して安くないのになぜ飛ぶように売れるのか?』『降りてくる思考法』(いずれもSBクリエイティブ刊)。開発商品に発想支援のための「イノベーションカード」(デキル。株式会社 / イノベーションデザイン協会)などがある。
本書の要点
- 要点1ビジョンとは「多くの人に共有・共感される、未来への洞察を信念にまで高めた末に生まれた、自らが心から達成したいと願う、あるべき未来像」である。
- 要点2驚異的なスピードでテクノロジーが進化する中で、ビジョンを持たないということは、こうした流れを傍観するということであり、意志の放棄に他ならない。
- 要点3日本のスタートアップからも、創業の志と明確なビジョンを持っている企業がいくつも出てきている。一方で苦境にあえいでいる大企業には、ビジョンの欠如を見ることができる。
要約
ビジョンから見た日本の現状
予測不可能な未来を生きるために

Martin Barraud/gettyimages
未来は個別の事象においては予測できない。だが大きな潮流に関しては、大体のところが予想可能である。たとえばAIや遺伝工学、量子コンピューター、拡張現実などのテクノロジーの進化は今後も続くし、地球温暖化や人口の激増、資源の枯渇が生態系に大きな影響を与えることは確実である。
日本人の多くには、主体的に世界を創造するビジョンを描き、それに向かって進んでいくという習慣がこれまでなかった。これはユーラシア大陸の東端の列島群という地理的な条件の中で、何万年も暮らしてきたことが生み出した特性である。
そんな日本もここ200年ほどを見ると、明治維新と第二次大戦後の際には大きなビジョンを持って動き、大きな変革を達成していた。ただしそれはいずれも圧倒的な「外圧」によるものだ。明治維新の時は外国からの開国圧力を、終戦の時は「敗戦」と「米軍による占領」を起点としていた。つまり外との差が圧倒的であり、「追いつかないと自分たちがダメになる」と思えないと、日本人は自分たちの力を最大限に発揮できなかったのだ。
優れたビジョンの事例
いまの日本でも、創業の志を抱いてスタートし、明確なビジョンを持っているスタートアップ企業はいくつもある。たとえばLITALICOは、「障害は人ではなく、社会の側にある」と考え、障害のある方の就労を支援するサービスや、自閉症・ダウン症などの診断を受けている子ども向けの学習教室を展開している。「障害のない社会をつくる」というビジョンを掲げ、すべての事業活動がそこに向かってフォーカスされているのだ。
別の事例として、貧困層向けマイクロファイナンスを展開する五常・アンド・カンパニーも挙げたい。同社は2018年時点でカンボジア、スリランカ、ミャンマー、インドの4カ国で事業を展開している。創業者の慎泰俊氏は在日として東京の下町で生まれ、一家6人の豊かでない暮らしと、外資系金融機関で磨いた知識をもとに、この会社を立ち上げた。彼らのビジョンは「誰もが自分の宿命を克服し、よりよい人生を達成する機会を得られる世界を創造すること」であり、民間版世界銀行として、世界中すべての人のための金融アクセスを提供している。
衰退のスイッチを押すダメなビジョン

Gearstd/gettyimages
一方で苦境にあえいでいる企業もある。東芝は代表例の1つであり、その一因としてビジョンの欠如が考えられる。
たしかに東芝のウェブサイトには、「人と、地球の、明日のために。東芝グループは、人間尊重を基本として、豊かな価値を創造し、世界の人々の生活・文化に貢献する企業集団をめざします」という経営理念などが書かれている。
だがこれは著者の考える「ビジョン」ではない。なぜなら東芝が目指す未来の姿が具体的に見えてこないからである。これらはあくまで全社員に「心がまえ」を説いているだけであり、結果として「私たちにはいま語るべき、取り組むべき未来像がない」ということ、「とりあえず、いまある技術的資産、人的資産を使って頑張るしかない」というメッセージになってしまっている。
こういうビジョンを掲げている経営者は、私たち自身が持つ知性、能力、感情のエネルギーを低く見積もっていると言わざるを得ない。
ビジョンを創る上で想定すべき未来
驚異的なテクノロジー進化のスピード
これからの100年を見据えるうえで、もっとも重要な視点は「テクノロジーと人間の調和」である。

この続きを見るには...
残り2254/3670文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2019.05.24
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権は株式会社フライヤーに帰属し、事前に株式 会社フライヤーへの書面による承諾を得ることなく本資料およびその複製物に修正・加工す ることは堅く禁じられています。また、本資料およびその複製物を送信、複製および配布・ 譲渡することは堅く禁じられています。
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権は株式会社フライヤーに帰属し、事前に株式 会社フライヤーへの書面による承諾を得ることなく本資料およびその複製物に修正・加工す ることは堅く禁じられています。また、本資料およびその複製物を送信、複製および配布・ 譲渡することは堅く禁じられています。
一緒に読まれている要約