僕は偽薬を売ることにした
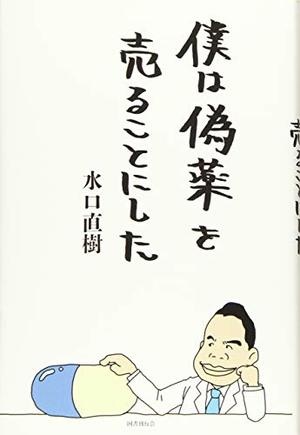
僕は偽薬を売ることにした
著者
著者
水口 直樹 (みずぐち なおき)
1986年、滋賀県生まれ。プラセボ製薬株式会社代表取締役。2010年京都大学薬学部卒業。2012年同大学院薬学研究科修了。製薬会社に研究開発職として入社。2014年に退社独立、現在に至る。
1986年、滋賀県生まれ。プラセボ製薬株式会社代表取締役。2010年京都大学薬学部卒業。2012年同大学院薬学研究科修了。製薬会社に研究開発職として入社。2014年に退社独立、現在に至る。
本書の要点
- 要点1プラセボ製薬株式会社は、「ニセモノ」につきまとうイメージを払拭させ、偽薬のプラセボ効果の有効活用を目標としている。
- 要点2プラセボ効果は、科学で説明できないことに対する「説明原理」だ。
- 要点3科学が「実数」だとしたら、プラセボ効果は「虚数」のような位置づけにあると考えられる。今後の医療を捉えるうえでは、虚数的なものも含めて考慮することが重要になってくる。
- 要点4偽薬を有効活用することで、健康という概念の見直しや、持続可能な社会保障制度の構築につながることが期待される。
要約
【必読ポイント!】 プラセボ製薬株式会社がめざす理念
プラセボ製薬株式会社
著者はプラセボ製薬株式会社の創業者だ。医薬品の製造ではなく、還元麦芽糖など各種食品成分を成形し、それを「偽薬食品」と称して販売している。「ニセモノ」につきまとうイメージを払拭し偽薬の価値を向上させること、プラセボ効果に関して独自に考察し妥当な解釈を示すこと、自然治癒力を信頼する健康観を普及させて持続可能な範囲での社会保障を充実させること――これらを理念として提示したのが本書である。
偽薬の価値

Chunumunu/gettyimages
偽薬の価値は2つある。1つは効果がないこと、もう1つは効果があることだ。
プラセボの原語はラテン語のplacebo(人を喜ばせる)であり、医療におけるプラセボは当初、偽薬のみを指していた。しかし最近では、外科的処置などの偽手術や、医師と患者のコミュニケーションなど、治療環境のすべてを含んでいると解釈されるようになり、より広い意味合いをもつ言葉となっている。
19世紀後半にアメリカ人医師がはじめて「プラセボ治療薬」を使用して以来、数々の臨床試験、実験、手術においてプラセボ効果が確認されてきた。その大半は、偽薬や偽の治療行為であることを、患者や被験者に伏せて行われた。しかしなかには、あらかじめ効果がないことを伝えたうえで、被験者に偽薬を服用させる「オープンラベル・プラセボ」の実験も行われ、症状の改善が見られたとする事例もあった。
現代のプラセボ効果に対する興味関心は、もっぱら臨床試験におけるものである。そこではプラセボ効果が「乗り越えるべき壁」と認識され、場合によっては「不快なノイズ」とさえ捉えられている。そのため医薬品や医療行為の効果を評価する臨床試験においては、プラセボ効果を差し引いて考慮する手法が用いられる。
このように医薬品開発とプラセボ効果は切っても切れない関係にあるが、医薬品の研究開発だけでなく、広い枠組みとしての医療そのものが、プラセボ効果と深い関係にあると言える。
プラセボ効果を解釈する
ヒトは進化の過程で不安や恐怖に対するストレスを感じるようになり、わからないものに対して否定的な感情を抱くようになった。わからないものがわかるようになるのは、ストレスの解消であり快感でもある。
そこでヒトは「わからないことの原因」に名前をつけた。たとえば意思のある超越的存在としての「神」という概念は、森羅万象のすべてに対応して説明できる能力をもった概念である。論理的整合性を付けて納得を得るために「わからないことの原因に名前をつけた概念」を「説明原理」と呼ぶ。
プラセボ効果もまた説明原理だ。本来薬効のない偽薬による治癒という現象は、従来の論理からすると説明不可能である。だが新たにプラセボ効果と呼ぶことで、「薬効成分を含まない偽薬の投与が、プラセボ効果により人に変化をもたらした」とする説明原理が成り立つようになるのだ。
複素効理論

amtitus/gettyimages
プラセボ効果に対する見解は大まかに言って、実在するという立場と、実在しないという立場に分けられる。本書では「プラセボ効果は実在する」ということを前提に話を進めるが、その場合でもプラセボ効果をどう解釈するのかに関しては、暗示や未解明の生理現象など、さまざまな主張に分かれる。
著者は次のような解釈を提示する。

この続きを見るには...
残り2927/4280文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2019.12.07
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約











