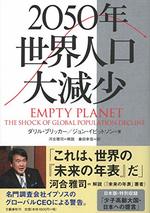72歳、今日が人生最高の日
著者
メイ・マスク(MAYE MUSK)
国際的なスーパーモデル。栄養士。『ヴァニティ・フェア』『ヴォーグ』『コスモポリタン』『マリ・クレール』といったファッション誌で活躍。長男はテスラ、スペースXのCEO、イーロン・マスク。
国際的なスーパーモデル。栄養士。『ヴァニティ・フェア』『ヴォーグ』『コスモポリタン』『マリ・クレール』といったファッション誌で活躍。長男はテスラ、スペースXのCEO、イーロン・マスク。
本書の要点
- 要点1メイ・マスクは白髪のスーパーモデルだ。モデルとしてデビューしたのは15歳のときで、当時、モデルは18歳までしか続けられない職業だとされていた。だがモデルの仕事はますます楽しくなっており、いまが最高だと断言できる。
- 要点2仕事も生活もうまくいっていたとき、息子の希望で海を越えた引っ越しをした。ときには思い切って変化することも重要だ。うまくいかなくても、やり直せばいい。
- 要点3「確実な“イエス”」は存在しないが、頼まなければ「確実に“ノー”」だ。どうしても手に入れたいものがあるなら、粘り強くアプローチしよう。
要約
生き方
人生はどんどんよくなる

Moyo Studio/gettyimages
著者は67歳のとき、ニューヨーク・コレクションに初出演し、3分の1の年齢の女性たちと一緒にランウェイを歩いた。ヴァージン・アメリカ社の広告のオーディションでは、自分よりも若い300人の女性たちの中から、見事選ばれた。タイムズスクエア、地下鉄、アメリカじゅうの空港……著者の顔を見ずに電車や飛行機から降りることはできないほど、その広告はあちこちに掲出された。白髪のスーパーモデル、それがメイ・マスクだ。
著者が初めてランウェイを歩いたのは15歳のときだ。当時、モデルは18歳までしか続けられない職業だと言われていた。著者自身、モデルをこんなに長く続けるなんて思っていなかったし、71歳で最盛期を迎えるなんて考えたこともなかった。
いま確実に言えるのは、ますます楽しくなっているということだ。日を重ねるごとにわくわく感が増し、何かおもしろいことが起きそうな予感でいっぱいだ。たとえ何も起きなくても、SNSやウェブサイトに投稿して、自ら何かを起こせばいい。
冒険
快適さは不要
著者と両親、そして兄妹たちはあるとき、カナダから南アフリカ共和国に転居した。毎年夏になると、家族でカラハリ砂漠を冒険するのがお決まりだった。父が自家用飛行機を操縦し、母が車を運転することもあれば、家族みんなで方位磁石をもってトラックに乗り、3週間かけて砂漠を横断することもあった。母は車に3週間分の食糧と水とガソリン、そして5人の子どもたちを積み込んだ。
冒険の旅を通して学んだのは、快適さは不要だということ。支出はいくらでも抑えられる。贅沢に暮らしている人を羨む必要もない。最善を尽くし、生き残るために奮闘するだけだ。
やらない理由なんてない

princigalli/gettyimages
大学で栄養学を専攻していた著者だが、3年生のときに出場した美人コンテストが、その後の人生を一変させた。同級生から、美人コンテストに推薦すると言われたのだ。著者はそもそも、そのコンテストの存在すら知らなかった。興味がないし、自分にはふさわしくない。そう断ったのに、推薦されてしまった。ほんとうに出場していいものか迷ったが、とりあえず参加してみることに決めた。やってみない理由なんてない。
コンテストの会場に到着して初めて、いかにほかの出場者たちが本気で参加しているかを知った。彼女らは髪をきちんと整え、メイクはプロの手を借りている。一方、著者は、水着は自分で用意したし、ヘアセットもメイクも自分の手によるものだった。
そんなふうに参加したコンテストだったのに、なんと優勝してしまった。ヨハネスブルクのモデル学校に通い、モデルとしての技術とプロ意識を身につけることになった。
著者は、何かを依頼されたら、それほど考えずに「イエス」と答えるようにしている。いくら自分が「やらない理由なんてない」と考えても、やらない理由を見つけてくる人もいるだろう。それでも、どうしたら自分が幸せになれるかという観点のもと、結論を出してほしい。そして、自分のために人生の扉を開くのだ。試してみないかぎり、何もわからないのだから。
結婚
著者が通っていたのは、南アフリカ共和国にある、地元の大学だ。著者が学びたかった食事療法の学位はアフリカーンス語(南アフリカ共和国の公用語のひとつ)で授業が行われる大学でしか取得できなかった。カナダで育った著者にとって、アフリカーンス語の習得はきわめて難しいものだった。ストレスを発散するために食べすぎてしまい、大学を卒業するときには体重が大きく増えていた。
そんな著者には、10代の頃から別れてはまたよりを戻す恋人がいた。

この続きを見るには...
残り2277/3754文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2020.07.31
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約