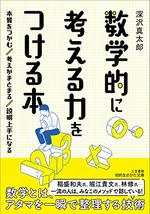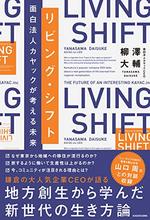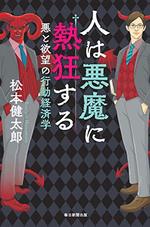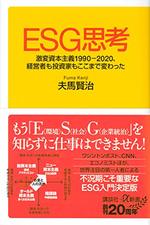ネットビジネス進化論
何が「成功」をもたらすのか
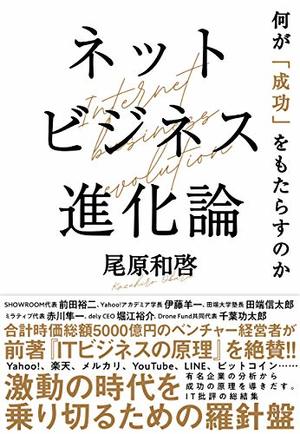
著者
尾原和啓(おばら かずひろ)
IT批評家。1970年生まれ。京都大学大学院工学研究科応用人工知能論講座修了。マッキンゼー・アンド・カンパニーにてキャリアをスタートし、NTTドコモのiモード事業立ち上げ支援、リクルート、ケイ・ラボラトリー(現:KLab、取締役)、コーポレートディレクション、サイバード、電子金券開発、リクルート(2回目)、オプト、グーグル、楽天(執行役員)の事業企画、投資、新規事業に従事。経済産業省対外通商政策委員、産業総合研究所人工知能センターアドバイザーなどを歴任。
著書に、『ITビジネスの原理』『ザ・プラットフォーム』(共にNHK出版)、『モチベーション革命』(幻冬舎)、『どこでも誰とでも働ける』(ダイヤモンド社)、『アルゴリズム フェアネス』(KADOKAWA)、共著に『アフターデジタル』『ディープテック』(共に日経BP)などがある。
IT批評家。1970年生まれ。京都大学大学院工学研究科応用人工知能論講座修了。マッキンゼー・アンド・カンパニーにてキャリアをスタートし、NTTドコモのiモード事業立ち上げ支援、リクルート、ケイ・ラボラトリー(現:KLab、取締役)、コーポレートディレクション、サイバード、電子金券開発、リクルート(2回目)、オプト、グーグル、楽天(執行役員)の事業企画、投資、新規事業に従事。経済産業省対外通商政策委員、産業総合研究所人工知能センターアドバイザーなどを歴任。
著書に、『ITビジネスの原理』『ザ・プラットフォーム』(共にNHK出版)、『モチベーション革命』(幻冬舎)、『どこでも誰とでも働ける』(ダイヤモンド社)、『アルゴリズム フェアネス』(KADOKAWA)、共著に『アフターデジタル』『ディープテック』(共に日経BP)などがある。
本書の要点
- 要点1インターネットの本質は、情報や物を小分けにして、離れていたものをつなげることにある。それにより、これまでなかった情報の流れ、物の流れが起こり、そこに新たなビジネスが生まれる。
- 要点2本書では、ネットビジネスがどういう原理で成り立っているかを理解するために、「ネットビジネスの進化の系統樹」という形で、それらを14のパターンに分類し、解説している。
- 要点3ネット勝者になるために重要なのは、どこが「儲けの一等地」として花開く場所かを知ることである。
要約
【必読ポイント!】 権力:つながりの場所を押さえる
小分けにしたものを遠くにつなげる
インターネットの本質は、情報や物を小分けにして、離れていたものをつなげることにある。それにより、これまでなかった情報の流れ、物の流れが起こり、そこに新たなビジネスが生まれる。
たとえば、これまでなら口紅を買えば使い切るのが普通だった。しかし今では、口をつけたところだけカッターで切り落とし、残った部分をメルカリで売ることも可能である。4000円で口紅を買った人が、自分が使った部分だけ切り落として、3500円でメルカリに出品したとする。次の人もまた使った部分だけ切り落として3200円で出品。これを繰り返せば、結果として1人が負担する料金はたった数百円となる。メルカリの実態は「シェアリングエコノミー」と変わらなくなっているのだ。
このように、情報や物を小分けにしてつなげるのがインターネットの本質といえる。では「何」を小分けにしてつなげるのか。そして「誰」と「誰」をつなげるのか。著者は、それらをネットビジネスの進化の系統樹という形で、14のパターンに分類している。ネットビジネスの原理・原則まで掘り下げれば、この先ネットビジネスがどこに向かうのか、グローバル企業がめざすものを先回りすることも不可能ではない。
本書のPart1では、ネットビジネスのどこに権力が宿るかについて解説されている。Part2以降では、どうすれば権力が独占構造をつくれるかという原理を、ネットビジネスの進化の枝分かれに沿って語っていく。本要約では、Part1~5のうち、それぞれ1つずつ「進化のパターン」をとりあげる。
検索はなぜ権力の一等地なのか?

sesame/gettyimages
ネットビジネスにおける権力の宿る場所とは何か。消費者側の一等地は「ポータル」だ。
インターネット上には大量の情報があり、ほしい情報にたどり着くための「入り口」のニーズが高まっていった。そんななか、1995年3月にはアメリカでヤフーが、1998年9月にはグーグルが生まれた。ヤフーとグーグルの間では、権力の一等地となる「検索」を巡る熾烈な争いが巻き起こることとなる。
当初ヤフーは、ユーザーの役に立つハイパーリンクを集めた「お役立ちリンク集」を作ることで、ユーザーを獲得した。ウェブサイトにはURLという「住所」があり、それをつなぐのがハイパーリンクである。クリックするとそのサイトに一瞬で飛べるのはハイパーリンクでつながっているからだ。
ユーザーにとっては、入り口は1つでよい。ヤフーというポータルサイト以外に、2番手、3番手を覚える必要はない。こうして「ポータルサイトと言えばヤフー」という純粋想起を獲得し、一気に市場を占有できたのだ。しかし落とし穴があった。ネット上の情報が爆発的に増え、人力でウェブサイトを集めていては追いつかなくなったのだ。
一方、後発のグーグルは、ネット上にあるサイトの「ページ」を巡回し収集する技術を開発した。この検索エンジンによって、ヤフーのようなサイト単位のリンクではなく各サイト内のページを検索結果に表示できるようになった。
目的のページに直接飛べる検索エンジンの便利さを知った人々は、何度もクリックしなければ目的のページに行けないヤフーには戻れなくなった。グーグル検索の精度向上に伴い、グーグルはヤフーにかわる「インターネットの入り口」になった。一方でヤフーは、いまもトップの集客力を誇るポータルサイトとして君臨し続けている。「Yahoo! ニュース」「Yahoo! 天気」などのさまざまなサービスを提供することで、ネットのポータルから、ネットとリアルのサービスのポータルとしての「スーパーアプリ」へと進化しようとしているのだ。
コマース:物や予約をつなげる
企業から人へ物をつなげる

BogdanVj/gettyimages
インターネットの最大の特徴は、網の目のように張り巡らされたハイパーリンクだ。ハイパーリンクは、情報を求める人と必要な情報をつなぎ、ネットに接続したい「人と人」「企業と企業」「企業と人」をつなぐ。物やサービスを売りたい人と買いたい人をつなぐオンラインサービス全般を、「eコマース(電子商取引)」と呼ぶ。
eコマースの分野でも、人が最初にアクセスする「入り口」になることが重要となる。そのため、「入り口」を巡る熾烈な競争が展開されてきた。
相互ネットワーク効果をしたたかに利用したアマゾン
BtoCコマースの覇者といえるアマゾンの最初の事業領域は「本」だった。本を選んだのは、ユーザーにとっての購入の判断しやすさ、在庫管理・配送のしやすさにくわえ、多品種少量生産という性質があったからだ。
現在、日本だけで毎年7万点もの書籍が出版されている。それらすべてを書店に並べるのは不可能だ。そこで、書店に置いていないニッチな本とその本がほしい人とをつなげ、物流改革により本の到着を速めた。こうしたことがアマゾンの強みとなり、その認知が広がっていった。

この続きを見るには...
残り2296/4316文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2020.08.18
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約