戦略コンサルタント 仕事の本質と全技法
「頭の知性」×「心の知性」×「プロフェッショナル・マインド」を鍛える最強のバイブル
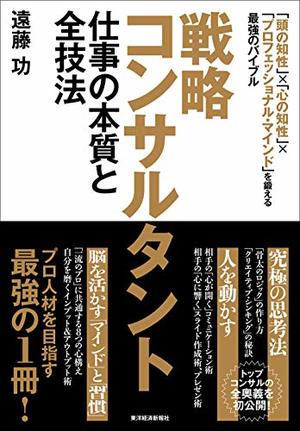
著者
遠藤功(えんどう いさお)
ローランド・ベルガー日本法人会長。早稲田大学商学部卒業。米国ボストンカレッジ経営学修士(MBA)。三菱電機株式会社、米系戦略コンサルティング会社を経て、現職。経営コンサルタントとして、戦略策定のみならず実行支援を伴った「結果の出る」コンサルティングとして高い評価を得ている。ローランド・ベルガーワールドワイドのスーパーバイザリーボード(経営監査委員会)アジア初のメンバーに選出された。株式会社良品計画社外取締役。SOMPOホールディングス株式会社社外取締役。株式会社マザーハウス社外取締役。株式会社ドリーム・アーツ社外取締役。コープさっぽろ有識者理事。株式会社NTTデータアドバイザリーボードメンバー。『現場力を鍛える』『見える化』『現場論』『生きている会社、死んでいる会社』『「ホットケーキの神さまたち」に学ぶビジネスで成功する10のヒント』(以上、東洋経済新報社)、『新幹線お掃除の天使たち』(あさ出版)など、ベストセラー著書多数。
ローランド・ベルガー日本法人会長。早稲田大学商学部卒業。米国ボストンカレッジ経営学修士(MBA)。三菱電機株式会社、米系戦略コンサルティング会社を経て、現職。経営コンサルタントとして、戦略策定のみならず実行支援を伴った「結果の出る」コンサルティングとして高い評価を得ている。ローランド・ベルガーワールドワイドのスーパーバイザリーボード(経営監査委員会)アジア初のメンバーに選出された。株式会社良品計画社外取締役。SOMPOホールディングス株式会社社外取締役。株式会社マザーハウス社外取締役。株式会社ドリーム・アーツ社外取締役。コープさっぽろ有識者理事。株式会社NTTデータアドバイザリーボードメンバー。『現場力を鍛える』『見える化』『現場論』『生きている会社、死んでいる会社』『「ホットケーキの神さまたち」に学ぶビジネスで成功する10のヒント』(以上、東洋経済新報社)、『新幹線お掃除の天使たち』(あさ出版)など、ベストセラー著書多数。
本書の要点
- 要点1戦略コンサルタントという仕事は、化学反応を引き起こす「触媒」のようなものだ。企業変革というきわめて重大な局面で、アウトサイダーという立場から進むべき方向を指し示し、変革の実現を支援する。
- 要点2一流の触媒になるためには、「頭の知性」、「心の知性」、「プロフェッショナル・マインド」の3つの資質を持ち合わせている必要がある。この3つがそろっていなければ、クライアントの意識変革を促して「その気にさせる」ことはできない。
要約
戦略コンサルタントとは
戦略コンサルティングファームの世界
世界最古のコンサルティング会社が生まれたのは、いまから130年以上前のことだ。その後、1920年代に米国で企業合併が相次ぐと、経営は複雑かつ高度化し、それにあわせて数多くの戦略コンサルティングファームが登場した。その多くに創業者の名前が冠されているのは、「プロフェッショナル」たる個人による卓越したサービスの提供がこの職業の本質であることを物語っている。
戦略コンサルタントの仕事は、「Up or Out」と称される厳しい世界だ。これは「生き残るためには、結果を出し、早く昇進するしかない。さもなくば、会社を去れ」という意味である。
「触媒」として「化学反応」を起こす

metamorworks/gettyimages
戦略コンサルタントの本質に言及する前に、コンサルタントに頼ることの是非について考えてみよう。変革の当事者はあくまでもクライアントだ。これは、戦略コンサルタントがそのプロセスに介入したとしても変わらない。
では、部外者に頼ることの必要性はどこにあるのだろうか。実際のケースを簡単に紹介しよう。
業界準大手の消費財メーカーB社は、国内市場の成長が鈍化する中、競合他社から提携話をもちかけられ、新たな経営モデルの可能性を探っていた。独自技術を有する産業用機械メーカーC社は、新興勢力が台頭する中、ハード(製品)に頼った自社の収益構造には限界があるとして、付加価値の高いサービスの提供が第一だと考えていた。エンターテインメントサービスを提供するD社は、非効率で生産性の低い現場に危機感を感じており、業務改革を検討していた。
これら3社に共通していることは、過去の延長線上にない「不連続の変革」を迫られているということだ。過去の経験にもとづいて対処できるならコンサルタントはいらない。変革が大半の企業にとっての「非日常」だからこそ、社内の常識にとらわれない「アウトサイダー」の立場で企業変革に関わることに意味がある。
戦略コンサルタントとは、いわば特定の化学反応の反応速度を速める「触媒」だ。「触媒」はひとたび変化が起きれば不要になるが、なければ「化学反応」は起きない。戦略コンサルタントの存在意義はそこにある。
戦略コンサルタントの仕事
一流の触媒であるための5つのポイント

ridvan_celik/gettyimages
戦略コンサルタントの仕事でなにより大切なのは、シンプルだが骨太の変革シナリオを描き、実現することである。データや情報の海に飲み込まれて物事の本質を見失ってはならない。世の中の潮流を読み解く「鳥の眼」にもとづく大局観と、泥臭い「虫の眼」で未来の予兆を感じ取る現場感が必要だ。
一流の触媒たるために、著者は常に5つのポイントを意識している。このうちどれか一つでも欠けてしまうと、「触媒」としての効果を発揮することは難しい。
1つ目は「適社性」。戦略には「これなら勝てる」という合理性が必要だが、それはベストプラクティスではなく、クライアントに適した「個別解」でなければならない。
2つ目は「ファクト」(事実)だ。エビデンス(証拠)なきものはロジックにあらず。常に数字で語る癖をつけ、自分の提言の正当性を証明しなければならない。
3つ目は「概念化・構造化・言語化」である。

この続きを見るには...
残り3024/4341文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2020.08.19
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約











