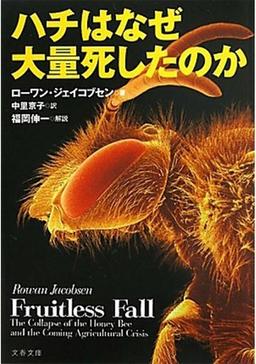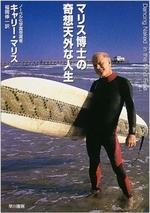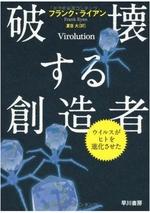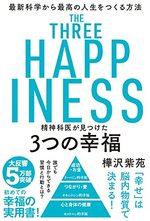植物の交配システムに組み込まれた昆虫
人と植物を結ぶミツバチの存在

植物の一生を簡単に説明すると次の通りになる。大地にまかれた種が芽を出し、芽は成長し成体となり蕾をつけ、花を咲かせる。そして種の詰まった実を作り、実が地面に落ちて、種から芽を出す。
一見するとこの過程は自己完結しているように見える。しかし、花には非常に重要な役割がある。その役割とは、同じ種の他の個体との繁殖だ。ほとんどの花にはオスの部分とメスの部分がある。細長い雄しべの先端の葯(やく)には、動物の精子にあたる花粉が付いていて、果実を育てるためには、この花粉を花の中心にある雌しべの柱頭に運ばなければならない。うまく花粉が柱頭に運ばれれば、卵子にあたる胚珠を結合し、「子房」の中で種が誕生して果実が出来上がるのである。
花の中には自分の花粉を使って自家受粉するものもあるが、これでは生殖の本来の目的である遺伝子の交配が達成されない。そのためほとんどの花では、他の個体からの花粉でなければ受粉できない仕組みになっている。ほかの個体へ花粉を届け、受粉する方法の一つは、物量に物を言わせる戦略である。つまり花粉を大量に作り風に任せて受粉を行うのだ。だがこの方法では花粉と雌しべが出会う確率が低く、効率が悪い。
そこで植物がとった戦略は昆虫という宅配便を使う方法だった。とはいっても昆虫もタダでは花粉を運んではくれない。そこで植物は花に蜜という褒美を溜め、その蜜を目当てに訪れる昆虫の体にそっと花粉をつける。昆虫がもっと花蜜を集めようと次の花に移ったとき、体についていた花粉がその花の雌しべの柱頭に触れ、受粉が行われる、という仕組みだ。
花蜜と花粉を食料としている昆虫は多くいるが、8000万年ほど前、その一群で あるハチがこれを特殊技能として発展させた。2万種も存在するハチの中でも人間がその技能を利用して文化を築くまでに至ったハチはたった1種類しかいない。学名を「アピス・メリフェラ」、種名セイヨウミツバチ。これが本書の主人公である。
受粉請負人、ミツバチ
アメリカ全土を駆け巡る派遣労働者
工業的農業が世界の食物生産を支配するようになり、他大陸からやってきた外来種の作物が栽培されるようになった現在、木箱と燻煙器を抱えた養蜂家は需要が増え、ますますあてにされるようになっている。ハイテク手段への依存を強める農業において、生物に依存した受粉に頼ることは驚くべき事実である。