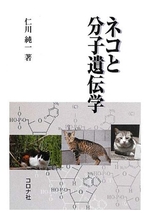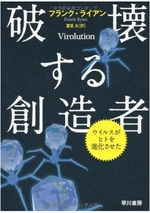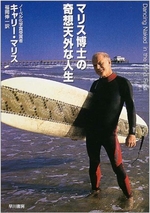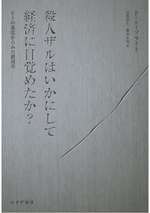分子からみた生物進化
DNAが明かす生物の歴史
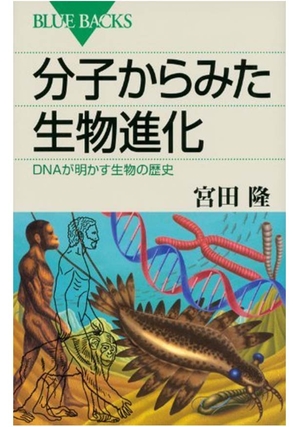
著者
宮田 隆(みやた・たかし)
1940年東京都生まれ。理学博士。分子進化学を専攻。1973年九州大学助教授に着任後、物理学から生物学に転向。京都大学教授を経て、現在同大学名誉教授。日本遺伝学会木原賞、木村資生記念学術賞を受賞。著書に、『DNAからみた生物の爆発的進化』(岩波書店)をはじめ、多数。
1940年東京都生まれ。理学博士。分子進化学を専攻。1973年九州大学助教授に着任後、物理学から生物学に転向。京都大学教授を経て、現在同大学名誉教授。日本遺伝学会木原賞、木村資生記念学術賞を受賞。著書に、『DNAからみた生物の爆発的進化』(岩波書店)をはじめ、多数。
本書の要点
- 要点1表現型レベルの進化は自然選択で説明されるが、分子レベルの進化は淘汰の有利不利ではなく中立におこり、この二つのレベルの進化をどのように統一的に理解するかは重要な問題である。
- 要点2進化速度がDNA複製エラーによる突然変異を主要因とするなら、数において圧倒的な精子を作るオスが進化を牽引するといえる。
- 要点3生物の進化は、既存の遺伝子を、あるいは何かに使っている遺伝子を、別の目的に利用するという「ソフト」な視点で理解することができ、これは表現型レベルの進化と分子レベルの進化を繋ぐ一つの考え方といえる。
要約
【必読ポイント!】ダーウィンと近代的進化論
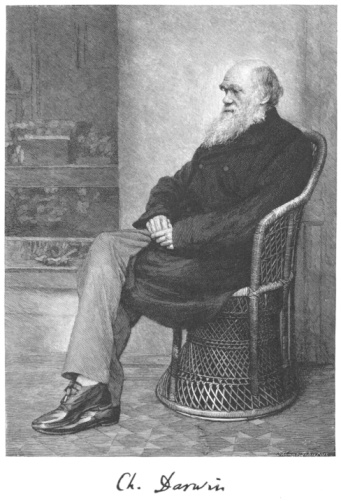
Photos.com/Thinkstock
表現型レベルの進化は自然選択で説明されるが、分子レベルの進化は淘汰の有利不利ではなく中立におこる
われわれ人間が野生の状態で見分けることができる生物種は500種類程度だが、実際に生物種の種類は驚くほど多く、ある推定によると1億種にも及ぶと著者は紹介している。これほど種の数が多いと、ルールを定めて分類することが必要になる。生物種を分類しようとする試みはギリシャ・ローマ時代にまでさかのぼるが、近代的な分類は、1735年「自然の体系」を著したカール・フォン・リンネによるものが始まりである。
これは分類の基本単位を「種」とし、それより上位の分類単位「属」の二つをラテン語を使って名付けるいわゆる二命名法であり、生物がもつ特徴的な形質の類似性に基づいている。種とは、一般には、交配によって繁殖力のある新しい個体を生みだしうる個体の集まりと定義されるが、正確な定義は現時点でもされていない。
進化とは一個体に生じた突然変異が同じ種に属する個体の集まり「集団」全体に広まることをいう。ここで著者は、産業革命が原因で比較的最近おきた進化の実例として、オオシモフリエダシャクという夜行性のガの翅の色が、淡色型から暗化型へわずか50年で変化した進化を挙げている。
ダーウィンは、種は変化し、新しい種は共通の祖先から分岐によってのみ生じる、そのメカニズムが自然選択よる進化であると説明している。しかし、同時に「種の起源」の中で、『進化は跳躍的におこるのではなく漸進的におこる』ことを主張しているが、その移行型はまれにしか見つかっていないという問題が最近まで議論されている。
一方、メンデル遺伝学の発見は、新しい種は突然変異によって一足飛びに生じるという学説を支持し、ダーウィンの考える自然選択のもとで徐々に形成されるという考えと対立した。その後、ダーウィンの進化理論とメンデル遺伝学が合体した「集団遺伝学」が誕生し、さらに古生物学を取り込み、「進化の総合説」へ発展を遂げる。
そして20世紀には、DNAの構造が明らかになり、DNAが遺伝情報の担い手であり、さらに進化の痕跡をとどめていることが明らかになった。そして、進化の化石ともいえるDNAに蓄積された情報をもとに進化を研究する「分子進化学」が誕生した。この発展は、1968年、木村資生博士が提唱した「分子進化の中立説」で大きな反響を呼んだ。
「分子でおこる進化の大部分は、有利な変異が自然選択によって広まった結果おこるのではなく、淘汰に有利でもなく、不利でもない、中立な変異が偶然に集団に広まった結果おこる」と主張する中立説は、分子レベルでおこる進化を説明する理論として定着した。それと同時に、眼でみてそれとわかる表現型レベルでおこる進化は依然ダーウィンのいう自然選択説で説明されると考えられている。マクロなレベルでおこる進化とミクロなレベルでおこる進化をいかにして統一的に理解できるのかが、今後の分子進化学に課せられた重大な課題なのである。
オス駆動進化説

Ingram Publishing/Thinkstock
オスが進化を牽引するということからすると、男性が高齢で子供を作ることにより子供へのリスクが高まることが推測される
進化に寄与する突然変異の主な要因は、生殖細胞の分裂に際しての「DNA複製エラー」である。これは生物種によって進化速度が異なることを合理的に説明しており、その進化速度は世代の長さとも関係し、一世代が長いと進化の速度は遅くなる。これは年あたりのDNA複製回数に比例して複製エラーが蓄積することで進化速度が速くなることを説明している。

この続きを見るには...
残り2936/4418文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2014.10.07
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約