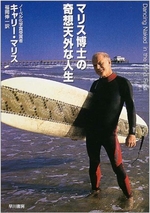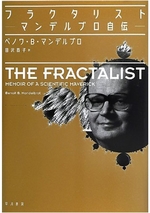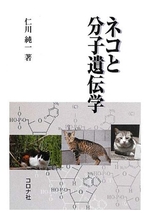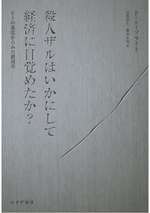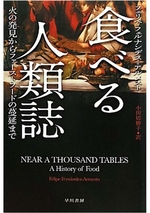現代アートビジネス

現代アートビジネス
著者
著者
小山 登美夫
1963年東京生まれ。東京藝術大学芸術学科卒業。西村画廊、白石コンテンポラリーアート勤務を経て、1996年に小山登美夫ギャラリーを開廊。奈良美智、村上隆をはじめとする同世代のアーティストの展覧会を企画・開催し、海外へも積極的に紹介。現代日本のアートシーンを牽引する中心的ギャラリストとして内外で注目を集める。日本のアートマーケットを確立することが現在の課題。明治大学国際日本学部特任准教授。
http://www.tomiokoyamagallery.com
1963年東京生まれ。東京藝術大学芸術学科卒業。西村画廊、白石コンテンポラリーアート勤務を経て、1996年に小山登美夫ギャラリーを開廊。奈良美智、村上隆をはじめとする同世代のアーティストの展覧会を企画・開催し、海外へも積極的に紹介。現代日本のアートシーンを牽引する中心的ギャラリストとして内外で注目を集める。日本のアートマーケットを確立することが現在の課題。明治大学国際日本学部特任准教授。
http://www.tomiokoyamagallery.com
本書の要点
- 要点1ギャラリストの仕事は、誰も見たことのないアート作品に価値を見出し、その価値を高めて世の中に出していくことだ。
- 要点2美術の歴史的な流れ、現代社会の動向と、現代アートの価値はつながっている。
- 要点3健全な現代アートマーケットは、作品が好きで、楽しみのために買うコレクターに支えられている。需要が増え、より公的なコレクターに買い求められるようになることで、作品価値が上がっていく。
- 要点4作品の価値と価格が上がっていくことで、アーティストも、ギャラリストも、買い手も、利益を得ることができる。
要約
誰も見たことのないものに価値を見出す
ギャラリストの仕事

moodboard/moodboard/Thinkstock
小山氏は高校生のとき、ジャスパー・ジョーンズの絵に胸を射抜かれた。わけがわからなかったからだ。現代美術を「わからない」から面白くないという人がいるが、でも「わからないから面白い」と考えることもできる。ただで作品が見られる画廊(ギャラリー)巡りをはじめた小山少年は、東京藝大卒業後、現代アートを取り扱う画廊で働くことになる。
新しいアートが世の中に受け入れられていく過程とは、今までまったく存在したことがないものに、どうやって価値を見出していくかということではないか、と小山氏は語る。
ギャラリストは、第二次世界大戦後、ニューヨークを中心とした現代アートの環境から生まれた。ギャラリーで働くギャラリストは、広義でいえば画商(アートディーラー)の一形態だが、展示空間を持ち、みずから企画展示をすることが画商と違う点だ。
また、ギャラリストは、みずから見出したアートをギャラリーで発表し、社会に価値を問い、その価値を高めていく仕掛け人ともいえる。画商がブローカーや営業マンに近く、顧客であるコレクター寄りに活動しているとすれば、ギャラリストはマネージメント業者やプロデューサーに近く、アーティスト寄りに活動しているのだ。
日米アートマーケット事情
やがて独立した小山氏は、みずからのギャラリーを開廊する。すでに出会っていた村上隆、奈良美智らのような同世代のアーティストを赤字覚悟で売り出すためだ。
しかし、若手アーティストの作品はさっぱり売れず、経営は逼迫。日本のマーケットに頭打ち感を感じ、小山氏はアメリカに活路を求めることにした。
開廊前、小山氏はアメリカのアートギャラリーを視察していた。圧倒的なギャラリーの数の多さと多様さは、それを支える顧客の層が厚いことを物語っていた。「これが売れるのか?」と疑問に思う絵も次々と売れていた。作品が「よい/悪い」「好き/嫌い」ということと、「売れる/売れない」は全く別の話で、どんな作品でも交換が成り立てばマーケットができるということを、目の当たりにしたのである。
小山氏は作品をトランクにつめ、単身アメリカに渡った。英語が話せないので日本人留学生に声をかけて通訳を頼んだ。するとそこでは思いがけないことが起こる。ほとんどの客には見慣れないはずの、奈良美智や村上隆の作品が次々と売れていったのだ。ふつうの人たちが、極東のアーティストの作品をどんどん買っていく。
その頃日本のギャラリストたちは、現代アートの本場である欧米に引け目を感じていたせいで、なかなか海外へ売り出しに行かなかったのかもしれない。だが小山氏は、「アートの世界は自由だ。日本のアートだって引けをとらない」「海外で新しいマーケットをつくっていく」という気概で挑んだ。
アーティストが仕事の要

Jupiterimages/Digital Vision/Thinkstock
ギャラリーの要となる仕事は、自分のギャラリーが取り扱うアーティストを決めることだ。自分なりの美の基準に合ったアーティストを発掘し、育てていくというタイプのギャラリストもいるが、小山氏の場合は、そのアーティストが「社会」や「時代」と真剣に切り結んでいるかどうかを基準にしている。

この続きを見るには...
残り3179/4481文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2014.08.19
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約