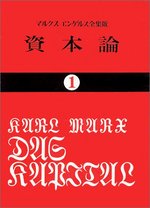乃公出でずんば
渋沢栄一伝

著者
北康利(きた やすとし)
昭和35年12月24日愛知県名古屋市生まれ。東京大学法学部卒業後、富士銀行入行。資産証券化の専門家として富士証券投資戦略部長、みずほ証券財務開発部長等を歴任。平成20年6月末でみずほ証券退職。本格的に作家活動に入る。著書に『白洲次郎 占領を背負った男』(第14回山本七平賞受賞)、『陰徳を積む 銀行王・安田善次郎伝』(新潮社)、『松下幸之助 経営の神様とよばれた男』(PHP研究所)、『胆斗の人 太田垣士郎 黒四(クロヨン)で龍になった男』(文藝春秋)、『思い邪なし 京セラ創業者 稲盛和夫』(毎日新聞出版)などがある。
昭和35年12月24日愛知県名古屋市生まれ。東京大学法学部卒業後、富士銀行入行。資産証券化の専門家として富士証券投資戦略部長、みずほ証券財務開発部長等を歴任。平成20年6月末でみずほ証券退職。本格的に作家活動に入る。著書に『白洲次郎 占領を背負った男』(第14回山本七平賞受賞)、『陰徳を積む 銀行王・安田善次郎伝』(新潮社)、『松下幸之助 経営の神様とよばれた男』(PHP研究所)、『胆斗の人 太田垣士郎 黒四(クロヨン)で龍になった男』(文藝春秋)、『思い邪なし 京セラ創業者 稲盛和夫』(毎日新聞出版)などがある。
本書の要点
- 要点1渋沢栄一は学問の師に感化され、過激な尊王攘夷思想を持っていた。しかし徳川慶喜に見いだされて幕臣となり、パリで行われた万国博覧会への視察に同行した。
- 要点2幕府崩壊後の新政府においても栄一はその手腕を振るったが、大久保利通との確執などを経て要職を辞す。その後は商人の道を選択し、数多くの会社の設立に携わっていく。
- 要点3社会福祉事業に幅広く貢献するなど多忙を極める中、後継者を孫の敬三に定める。1931年11月11日、栄一はついにその盛大な人生の幕を閉じた。
要約
頭角を現す幕末期
尊王攘夷思想に染まる青年期

traveler1116/gettyimages
渋沢栄一は、1840年2月13日(旧暦)、現在の埼玉県深谷市に父市郎右衛門(いちろうえもん)、母栄(えい)の子として生を享けた。生家は養蚕と藍玉で財を成し、名字帯刀を許された豪農であった。兄弟姉妹は10人以上いたようだが、兄たちが次々と死んでいき、男子として一人残った栄一は、跡取り息子として大切に育てられた。稲刈り後の冬の田んぼを走り回る元気な子で、容易に言うことを聞かず、お化けなどの迷信も信じず、強情な性格の持ち主だった。
市郎右衛門は質素倹約を旨としながらも、子弟の教育には気を配った。7歳になった頃には、栄一を従兄の尾高惇忠に師事させる。栄一は、中でも孔子の言語録『論語』に傾倒したという。こうして学問に励む一方で、養蚕と藍という渋沢一族に大きな財力をもたらした産業から、商売の基本も学んでいった。
ときは黒船来航で大騒ぎとなっている幕末である。学問の師である惇忠が、過激な尊王攘夷思想に染まっていくのを見て、栄一も幕府に対する不信感を募らせていった。
運命を変えた一橋家への仕官
栄一は従兄の喜作とともに剣を学ぶ過程で尊王攘夷へと傾斜していく。栄一18歳のときには、惇忠の妹で幼なじみの千代と結婚するが、尊王攘夷熱は消えなかった。桜田門外の変や生麦事件など、攘夷の動きの影響を受け、大河内松平家の居城、高崎城を乗っ取って長州藩と連携することを画策する。計画は「暴挙である」という惇忠の弟の発言で実行直前に中止となったが、「予定通り決行していたら、間違いなく同志全員が討ち死にしていたはずだ」と栄一は後に述懐している。若気の至りだった。
決起を踏みとどまった栄一と喜作が頼ったのが、江戸幕府最後の将軍、徳川慶喜が継いだ一橋家において、家老並筆頭側用人を務める平岡円四郎だった。有能な人物の発掘の過程で、喜作たちを見いだし高く評価してくれていたのだ。しかし、平岡は一橋慶喜と同じ開国論者。それでも、一緒に高崎城襲撃を画策した同志を救うことになると考え、栄一と喜作は一橋家仕官を決意。これが人生の転機になった。
交渉や情報収集を主な仕事とする奥口番を命じられた栄一は、薩摩藩の動静を探る過程で西郷隆盛にも会っている。不思議な魅力の持ち主に相対し、栄一もすぐに打ち解けた。西郷が豚鍋を振る舞った際、仏教の不殺生の教えにより肉食をためらっている栄一に対し、

この続きを見るには...
残り3775/4769文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2021.03.28
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約

約束の地 上
バラク・オバマ山田 文(訳)三宅 康雄(訳)長尾 莉紗(訳)高取 芳彦(訳)藤田 美菜子(訳)柴田 さとみ(訳)山田 美明(訳)関根 光宏(訳)芝 瑞紀(訳)島崎 由里子(訳)
/summary/2566