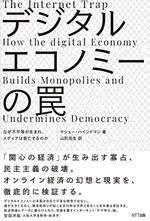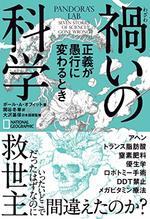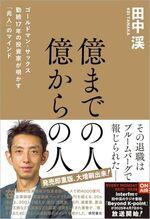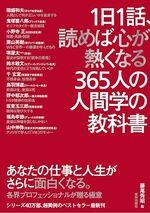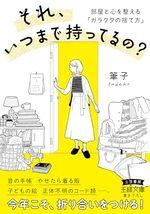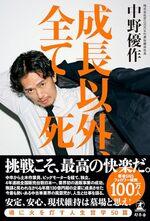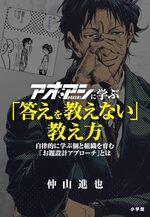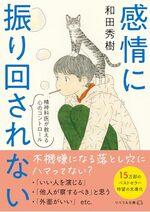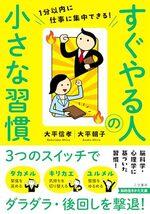【必読ポイント!】 人物を修めるための活眼・活学
心眼を開く

人間にとって目は大切なものだが、肉眼だけでは目先しか見ることができない。私たちは外と同時に内を、現在と同時に過去と未来を、そして現象の奥に本体を見なければならない。仏教では、肉眼、天眼、慧眼、法眼、仏眼が「五眼」として説かれる。ここでは、肉眼以上のものを「心眼」と呼ぼう。
私たちのエネルギーには、体格や肉づきのような顕在エネルギーだけでなく、外側には現れない潜在エネルギーがある。氷山は水面下に隠れている部分の方が大きいのと同じように、潜在エネルギーの方が遥かに強い力を持っているものだ。見てくれは堂々としている人間でも、潜在エネルギーは案外貧弱な人が少なくない。一方、見かけは弱そうでも、何かをやらせると非常に精力的で不屈不撓の人、顕在エネルギーは貧弱でも潜在エネルギーが旺盛な人もいる。忠臣蔵で有名な大石内蔵助や、『三国志』に登場する曹操のような歴史上の英雄であっても、さほど風采は上がらなかったそうだ。しかし、見る人が見ればわかる。つまり、心眼で見ればわかるのである。
この潜在エネルギーを培養するために、心眼を開き、精神の土壌や根の部分からしっかりと培養して、精神生活を豊かにしなければならない。俺は銀行人だから、銀行のことさえ考えればいい、銀行に関する知識や技術の書物に親しめばいいという考えは危険だ。仕事をしていると、思いがけない示唆やヒントによって活気を得られることがある。現実の生活に忙しくても多面的な良い付き合いを持ち、教養を高める読書をし、精神活動を豊かにすべきだ。
近代文明、物質文明が発達するほど、個人は集団生活の中に呑み込まれ、集団心理の支配を受けて個性を奪われていく傾向にある。文明が発展するほど、個人は無内容になっていくという恐ろしさがある。個人が私生活や内面的自我を喪失すれば、やがて自己のすべてを失い、肉体も人格も崩壊するだろう。文明は没落し、やがて滅びてしまうかもしれない。
現代では、世界的に目先のことに追われ、心眼が衰えてきている。文明が進歩すればするほど、私たちは心眼を開いて、内面的自我をもっと健全にしながら、本当に理性的で、道徳的、堅実な社会生活を持つようにしなければならない。
見識と胆識を身につける

知識は、それ自体では力にならない。

![[増補新版]活眼 活学の表紙](/_next/image?url=https%3A%2F%2Ffd-flier-static-prod-endpoint-b6g9b5dkedfkeqcc.a03.azurefd.net%2Fsummary%2F2598_cover_300.jpg&w=256&q=75)