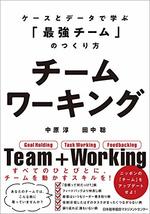ウィニングカルチャー
勝ちぐせのある人と組織のつくり方


著者
中竹竜二(なかたけ りゅうじ)
1973年福岡県生まれ。早稲田大学人間科学部に入学し、ラグビー蹴球部に所属。同部主将を務め、全国大学選手権で準優勝。卒業後、英国に留学し、レスター大学大学院社会学部修了。帰国後、株式会社三菱総合研究所入社。2006年、早稲田大学ラグビー蹴球部監督に就任。自律支援型の指導法で、2007年度から2年連続で全国大学選手権優勝。2010年、日本ラグビーフットボール協会コーチングディレクターに就任。2019年より日本ラグビーフットボール協会理事に。2014年、企業のリーダー育成トレーニングを行う株式会社チームボックスを設立。著書は『新版リーダーシップからフォロワーシップへ カリスマリーダー不要の組織づくりとは』(CCCメディアハウス)など多数。
1973年福岡県生まれ。早稲田大学人間科学部に入学し、ラグビー蹴球部に所属。同部主将を務め、全国大学選手権で準優勝。卒業後、英国に留学し、レスター大学大学院社会学部修了。帰国後、株式会社三菱総合研究所入社。2006年、早稲田大学ラグビー蹴球部監督に就任。自律支援型の指導法で、2007年度から2年連続で全国大学選手権優勝。2010年、日本ラグビーフットボール協会コーチングディレクターに就任。2019年より日本ラグビーフットボール協会理事に。2014年、企業のリーダー育成トレーニングを行う株式会社チームボックスを設立。著書は『新版リーダーシップからフォロワーシップへ カリスマリーダー不要の組織づくりとは』(CCCメディアハウス)など多数。
本書の要点
- 要点1組織文化は企業など集団内で共有される好き嫌いやこだわりといった価値観や習慣であり、一人ひとりの価値観や感情の集積である。常勝の組織文化への変革には個々人の変革が不可欠だ。
- 要点2変革は「組織文化を知る」ことが最初の一歩となる。「自分たちは何者か」を突き詰めて考え、自問し続けねばならない。
- 要点3「組織文化を変える」には能動的に変革しようとする姿勢が重要だ。さらに「組織文化を進化させる」ため、前提や常識にとらわれず「知る」、「変える」のプロセスを繰り返す根気強さが求められる。
要約
【必読ポイント!】 一人ひとりが担う組織文化
ウィニングカルチャーとは問い続けること

jacoblund/gettyimages
ラグビー日本代表は2019年にワールドカップでベスト8入りの快挙を成し遂げた。かつての歴代日本代表は、負けても照れ笑いを浮かべるような「負け犬根性」が染みついていた。しかし2012年に就任したエディ・ジョーンズ監督のもとで、意識と行動の変革に取り組み、負けたら本気で悔しがるチームへ180度転換した。一方、後任のジェイミー・ジョセフ監督は「ワンチーム」を掲げ、選手が普段から互いに感情をさらけ出し、ミスや弱さも認め合いながら、ともに成長していくチームへと変容させていった。
ラグビーに限らずどんなチームや企業も、人数や規模と関係なく、組織文化を魅力的に変革、刷新し、ウィニングカルチャーを構築することができる。
ウィニングカルチャーとは「勝ちとは何か」「どう勝つのか」と問い続けることである。一度は出た「解」をあえて疑い、過去の成果にとらわれず、謙虚に学び続け、進化、成長し続ける姿勢といえる。掲げた目標を一人ひとりが意識し、達成に向けて一丸となって動くことが大切である。
独自の「らしさ」が組織文化
組織文化は、組織に属する人々のふとした行動や言葉に表れる「問い」のことである。組織の成果や評価、未来を激変させる力を持ちながら、ぼんやりとして実態がつかみづらい。
組織文化は、集団において共有される好き嫌いやこだわりといった価値観や習慣であり、年々その意味合いを増している。例えば、その企業は何をできるのか、達成したのかといった「do」ではなく、どうあるのか、いかなる価値観で事業を行っているのかという「be」の部分が、求職者や消費者、取引先などに選ばれるうえで重視されはじめている。企業が持つ唯一無二の「らしさ」、すなわち組織文化を理解し、大切に育てていくことが重要だ。
また、企業ごとに独自の組織文化、ウィニングカルチャーが存在する。これは所属する人々のあり方や営み、言葉や行動を通じて醸成される、その組織でしか通じない文化だ。そのため、他社に模倣されることはない。
居心地の良さ、高い自由度、成長できる環境などさまざまな要素を織り交ぜた企業独自の組織文化は、「カルチャーフィット(組織文化への適合)」と言われるように、特に人材採用において重視されている。
組織文化は企業の深奥にある

imaginima/gettyimages
製品やサービスといった企業にまつわる諸要素のうち、利益や株価などの成果は最も見えやすい。反対に、最も奥深くにあって見えにくいのが組織文化である。企業の構成要素の最下層にあって普段ほとんど意識もされない。しかし組織文化は社内のルールや社員の行動や言葉、製品やサービスに至るすべてに影響を及ぼす。
組織文化は「働く人々が何となく共有している価値観や雰囲気、クセのこと」である。それは、勝敗や業績など現前の事象、事実に対し、社員らがどう反応したか、どのような感情が芽生えたかによって異なる。例えば業界最大手の企業が2位に肉薄されている場合、その状況が我慢ならないか、多少追いつかれても構わないかといったように、一つの同じ事実に対して異なる反応、見方がある。その一つひとつが組織文化を形作っていく。
著者が早稲田大学ラグビー蹴球部の主将と監督を務めていた時代にあった、「優勝しなければ負け」、「日本一以外は無意味」といった価値観も組織文化である。ただ、そこに良し悪しはない。
一人ひとりの変化が必要
事実に対する一人ひとりの感情、その集積が組織文化である。個人の感情と組織文化は相似関係にある。組織文化を変えるには、一人ひとりの反応や態度を解き明かし、言葉や行動を変える必要がある。一人ひとりの変化なしに、組織文化は変容しない。
その変化を受け入れる土壌として、個人が感情や弱みをさらけ出せる心理的安全性の高い環境が必要だ。さらけ出すことで見えてくる素の自分をオーセンティシティ(飾り気のない自分らしさ)と呼ぶ。そして組織のそれは「組織らしさ」、すなわち組織文化を意味する。組織文化は所属する一人ひとりの自分らしさの集積である。そのため組織文化を知るには、一人ひとりのオーセンティシティを知ることから始めるとよい。
組織文化の変革においては、中にいる一人ひとりが自分らしさを出し、恐れずに本音を語り合うことが最初の一歩となる。人も組織も、現在の知識や過去の成功体験を捨て、異質な、違和感のある価値観を受け入れることで成長していく。
人を知り、組織文化を「知る」
自分たちは何者かを問う
哲学者アリストテレスが「自分を知ることが、すべての知恵の始まりである」と言ったように、「自分たちは何者か」を考えることは重要である。業績不振に陥ってから自分たちは正しかったのか、変わらなくていいのかと考えるのでは遅い。平時から意識的に問い続ける姿勢が求められる。
「自分たちは何者か」「根底にある組織文化は何か」と自問することなしに強い組織を築くことはできない。また本当の意味で成長し、未来を切り拓く企業にはなれないだろう。
組織文化を的確に把握し、思い描く形に変え、進化させ続けられれば、チームや企業は一段と強くなる。その組織文化は、環境の変化や社員の入れ替わりによって揺れ動くため、常にモニタリングし、改善していく不断の努力を要する。
その組織文化は属する人たちの無意識の中にある。見えにくい組織の行動原理を顕在化させる方法は、(1)自分で知る、(2)他者に聞く、(3)他者と触れ合うという三つに大別される。
組織文化の発見

IvelinRadkov/gettyimages
まず「自分で知る」については、自分が自分を、組織内の人がその組織をどう思っているかを明らかにする「内的自己認識」というやり方がある。「組織が最重視する価値観は何か」「組織の強みは何か」「ビジョンやバリューは何か」。このように問いかけ、言葉に表すことで、組織文化の輪郭がはっきりしてくる。なぜその結果になったか、将来的にどんな結果になることが望ましいかを社員同士で話し合うプロセスが大切だ。
二つ目の「他者に聞く」は、自分が他者からどう見られているかを知る「外的自己認識」のアプローチである。まずは他者の見方の予測を立て、その予測とヒアリング結果のギャップが、組織文化の理解につながる。男女や部門を問わず幅広く意見を聞いて予測することが肝要だ。取引先や提携企業に加え、退職者や入社間もない社員の意見も貴重である。
最後に三つ目の「他者と触れ合う」については、普段接点のないような異業種との交流から得られる違和感が重要となる。その違和感や戸惑いはどこから来るのか、自問することにより組織文化に対する理解を深められる。
主体的に組織文化を「変える」
危機感から能動的に
組織文化を変える変革のタイミングは、危機に直面してからでは遅い。危機感を覚えたとき、リーダーが「おかしい」と直感したら速やかに着手すべきだ。
組織文化の変革には半年、長ければ10年超の歳月を要する。また組織文化を変えても、業績などすぐに目に見える成果が期待できるわけではない。一人ひとりの言葉や行動、価値観が変わる成長が不可欠だ。
成長には2種類、従来の枠組みにある知識や能力を伸ばす「水平的成長」、従来の枠組みの常識や前提を取り払う「垂直的成長」がある。前者を一般的な量的成長「ラーン=学び」と呼ぶのに対し、後者は学んだ知識をいったん破壊する質的成長「アンラーン=学びほぐし」と呼ぶ。ラーンもアンラーンもするタイプは、組織文化変革のお手本のような人であるが、ラーンやアンラーンに消極的な人もおり、動機付けが大切だ。
変化の速い時代、将来の予測が難しいVUCA(ブーカ、「変動性・不確実性・複雑性・曖昧性」を表す英語の頭文字)の時代にあって、受け身ではなく能動的に変革していかねばならない。
変わるためには仲間づくりから

Pict Rider/gettyimages
知り得た組織文化の強みや弱みといった特徴のうち、残すべきと変えるべきは何か。その具体的プロセスは、(1)仲間をつくる、(2)組織の理想像を決める、(3)行動基準を決める、(4)振り返りとフィードバックの4段階を経る。
最初の「仲間をつくる」の段階では、組織文化を変えたいと思い立った人が変革すると宣言する。そのうえで、有志を募ったり、変革に向けたタスクフォースを立ち上げたりして一人ひとりに変革を迫る。このタスクフォースは現場の古参から若手社員まで多様なメンバーで構成することが望ましい。
次に「組織の理想像を決める」では、「将来なりたい姿」「自分たちらしい組織像」を極力明確に言語化していく。「みんなで考える組織」とか、反対に「強いリーダーのトップダウン型」など、具体像を描いてから組織文化へ落とし込むと、進めやすい。
続いて「行動基準を決める」では理想像を具現化する。組織文化を咀嚼し、「自分たちはこれが好き」といった感覚を、具体的な行動や言葉に落とし込む。反応を見ながら違和感のある基準を外したり、必要な基準を付け足したりしていく。
最後に行う「振り返りとフィードバック」では、行動基準を実行した結果を、自分や仲間同士で振り返り共有するとともに、第三者からフィードバックを受ける。
こうした四つのステップを経ることで、理想の組織文化に向かうことができる。そこでは長期的に継続していく粘り強さが求められる。
組織文化を「進化させる」不断の努力
実るほど頭が下がる
ラグビーワールドカップで最多優勝のニュージーランド代表「オールブラックス」と、世界を代表するサッカークラブ「FCバルセロナ」。両者に共通するのは最強の名をほしいままにしながら、謙虚な姿勢で進化への歩みを止めないことである。進化し続ける姿勢は企業にも非常に重要である。過去の成功体験にとらわれず、謙虚に学び、変わり続けることにより、本当の意味で組織は強く生まれ変わる。
創業時に機能していた社是も、トップ交代や時代の流れとともに風化してしまうきらいがある。後生大事に神格化するのではなく、臨機応変に社是そのもの、あるいは社是の捉え方や言葉を見直す果断さが求められる。
組織文化を進化させるには、変革後も再び「(組織文化を)知る」「変える」のサイクルを回し続ける必要がある。理想像と現状の姿にどの程度ギャップがあるか、と問い続ける姿勢が望ましい。その際、過去の成功体験に立脚して課題解決を目指す「シングルループ」よりも、その成功や大前提さえ疑い、新たな知識と視座をもとに課題に取り組む「ダブルループ」の考え方に基づくべきである。一つ上のステージへの成長、進化には、過去にない「解」を求め、今の前提や常識にとらわれない新しい視点が必要だ。
問いの設定が肝
組織文化を進化させる肝心要は問いの立て方に尽きる。組織内の人に何を問いかけ、意思疎通を図るか。大切な3つのアプローチとして、「なぜ」「どのように」「何を」という視点が大切となる。
まず「なぜ」組織文化を進化させるのか。現状に満足している人は進化に対して疑問を抱き、拒絶の反応を示すかもしれない。そこで「世の中は変わっていく。自分たちも変わり続けなくてはならない」と、さらなる進化を奨励する必要がある。
そして「どのように」組織文化を進化させるのか。この問いには大前提を疑う、上述のダブルループの考え方が有効である。組織文化の変革に成功し、新商品がヒットした後も、自社の立ち位置や業種の定義を自問するようにしたい。
さらに、進化のために「何を」すべきか。時系列に沿って「過去に、もっとやれたことはなかったか」「現在に、何に取り組むべきか」「未来に、組織や社会はどうなっているか」と問いかけ、組織文化を常に見つめ直すとよいだろう。

この続きを見るには...
残り0/4761文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2021.05.01
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約