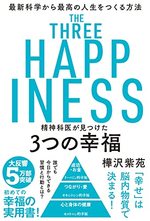無(最高の状態)

無(最高の状態)
著者
著者
鈴木祐(すずき ゆう)
サイエンスライター。1976年生まれ。慶應義塾大学SFC卒業後、出版社勤務を経て独立。10万本の科学論文の読破と600人を超える海外の学者や専門医へのインタビューを重ねながら、現在はヘルスケアや生産性向上をテーマとした書籍や雑誌の執筆を手がける。自身のブログ「パレオな男」で心理、健康、科学に関する最新の知見を紹介し続け、月間250万PVを達成。近年はヘルスケア企業などを中心に、科学的なエビデンスの見分け方などを伝える講演なども行っている。著書に『最高の体調』『科学的な適職』(クロスメディア・パブリッシング)、『不老長寿メソッド』(かんき出版)など。
サイエンスライター。1976年生まれ。慶應義塾大学SFC卒業後、出版社勤務を経て独立。10万本の科学論文の読破と600人を超える海外の学者や専門医へのインタビューを重ねながら、現在はヘルスケアや生産性向上をテーマとした書籍や雑誌の執筆を手がける。自身のブログ「パレオな男」で心理、健康、科学に関する最新の知見を紹介し続け、月間250万PVを達成。近年はヘルスケア企業などを中心に、科学的なエビデンスの見分け方などを伝える講演なども行っている。著書に『最高の体調』『科学的な適職』(クロスメディア・パブリッシング)、『不老長寿メソッド』(かんき出版)など。
本書の要点
- 要点1自己は単一の存在ではなく生存用のツールボックスである。
- 要点2脳は物語の製造機であり、人間は脳が作り出したシミュレーション世界を生きている。また、人間の脳は現実よりも「物語」を重んじるように設計されている。
- 要点3過去の体験によって生み出される物語は、ときに歪んだ悪法を生み出し、人の行動に影響を与える。
- 要点4苦しみは、「痛み×抵抗」という式で表せる。現実の痛みに対して積極的に「降伏」することで、苦しみの増大を抑制できる。
要約
【必読ポイント!】 自己
真の苦しみは「二の矢」が刺さるか否かで決まる

Benjavisa/gettyimages
「苦」の感情はあらゆる哺乳類に普遍的に備わっている。だが、ひとつだけ動物と人間には重要な違いがある。それは「哺乳類は苦しみをこじらせない」という点だ。人間なら数年は苦しみが続く悲劇が起きても、動物たちは少しの間ネガティブな感情を表出するだけで、すぐに以前の状態に戻る。では、同じ哺乳類でありながら、なぜ人間だけが「苦しみ」をこじらせるのだろうか。
恐怖・喜びといった感情は、いずれも人類の進化のプロセスで形作られたものである。人間の祖先が集団生活を始めたとき、周囲の援助を勝ち取り、裏切りの可能性を減らすため、脳内には新たな感情が宿った。それが「怒り」「不安」「恥」「嫉妬」といった新機能であり、「社会的感情」と呼ばれる。もしこれらの感情がなければ身に迫る危険を察知できず、大事なものを奪い返すこともしない。この意味でネガティブな感情は、私たちを守る生存機能であるといえる。
しかし、本来私たちを守るべく生まれた生存機能こそが、我々の苦しみをこじらせる原因、つまり「二の矢」となって突き刺さるのだ。例えば、貯金が少なくなったことに対し、「このままでは将来の生活はどうなるのか」と不安を募らせる。「貯金が少なくなったこと=一の矢」は起こってしまった事実である。だが、「将来への不安=二の矢」は新しい社会的感情が生み出したものだ。こうして最初の悩みが別の悩みを呼び込み、脳内で反復され、苦しみをこじらせている。
「自己」は生存用のツールボックスである
人間の苦悩は未来か過去に関わるものばかりだ。現在だけを生きる動物には、過去と未来を思う苦しみはない。とはいえ、来し方を悔やみ、行く先を憂いてしまうのが人間の性だろう。そこで己の中の人間、つまり「自己」が失せれば苦を受ける主体もなくなるという発想が生まれる。
「自己」はもともと集団生活を生き抜くために生まれた能力だ。食料の分配をめぐる争いの増加、資源を奪う裏切り者の出現といった社会的問題に対処するために、集団の中で自分のポジションを抽象的に考える能力を発達させてきた。これが私たちの自己の起源となる。
これまで多くの哲学者や宗教家が自己への疑問と格闘してきた。だが、認知科学や脳科学の発達により、自己についてのわかりやすい考え方が生まれてきた。それが「自己=機能の集合体」という考え方である。自己は単一の存在ではなく、様々なツールのパッケージだというのだ。
例えば、「どの仕事から手を付けるか」と考えた場合は前頭前野皮質と海馬に、「悲しくてやりきれない」と思った場合は扁桃体や視床下部に自己が発生する。それぞれの機能は脳内の異なる神経系が調整し、ほぼ独立したシステムとして動作しているのだ。つまり自己は生存用のツールボックスにすぎないのである。
虚構
自己は「物語」で構成されている

HiddenCatch/gettyimages
昔ながらの見解では、私たちは3つのステップで「世界」を体験すると考えられてきた。例えばリンゴを目にしたとしよう。その場合、映像を眼球が撮影し(ステップ1)、その画像が脳の高次機能に送られ(ステップ2)、「リンゴ」の映像として処理される(ステップ3)といった具合だ。ところが、この発想では説明できない現象は多い。

この続きを見るには...
残り3166/4513文字
4,000冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2021.08.21
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約