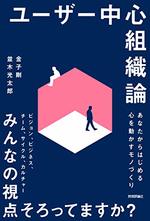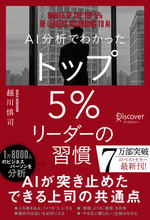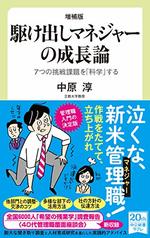職場学習論 新装版
仕事の学びを科学する
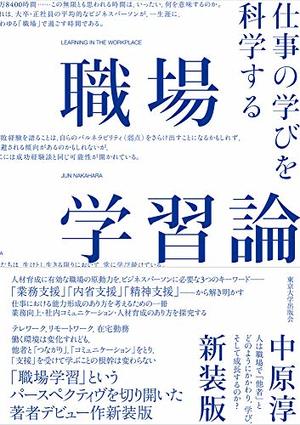
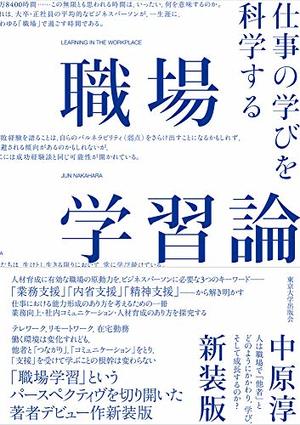
著者
中原淳(なかはら じゅん)
立教大学経営学部 教授。 大阪大学博士(人間科学)。北海道旭川市生まれ。東京大学教育学部卒業、大阪大学大学院 人間科学研究科、米国・マサチューセッツ工科大学客員研究員、東京大学講師・准教授等を経て、2017年~2019年まで立教大学経営学部ビジネスリーダーシッププログラム主査、2018年より立教大学教授。
「大人の学びを科学する」をテーマに、企業・組織における人材開発、組織開発、リーダーシップ開発を研究している。専門は経営学習論・組織行動論。立教大学大学院 経営学研究科 経営学専攻 リーダーシップ開発コース主査、リーダーシップ研究所副所長を務める。
立教大学経営学部 教授。 大阪大学博士(人間科学)。北海道旭川市生まれ。東京大学教育学部卒業、大阪大学大学院 人間科学研究科、米国・マサチューセッツ工科大学客員研究員、東京大学講師・准教授等を経て、2017年~2019年まで立教大学経営学部ビジネスリーダーシッププログラム主査、2018年より立教大学教授。
「大人の学びを科学する」をテーマに、企業・組織における人材開発、組織開発、リーダーシップ開発を研究している。専門は経営学習論・組織行動論。立教大学大学院 経営学研究科 経営学専攻 リーダーシップ開発コース主査、リーダーシップ研究所副所長を務める。
本書の要点
- 要点1職場で受けられる支援は、精神支援・業務支援・内省支援の3つに分類できる。「職場における他者とのつがなり」を回復させることで、職場のさまざまな人から支援を受け、能力を向上させられる。
- 要点2職場内の立場によって効果的な支援は異なる。職場における人材育成は、職場の人々が分散して担い、ネットワークとして取り組むほうが効果的である。
- 要点3職場における「互酬性規範」を高める試みがなされれば、「内省支援」が進む可能性がある。
要約
職場における学習の意義
「職場における学習」の背景
まずは、職場における人々の学習に関する社会的背景を概観しよう。高度経済成長期には、企業による職業訓練やOJT・人事育成施策が盛んだった。ところが、バブル崩壊後、終身雇用・右肩上がりの報酬の消失とともに、その価値は急速に低下していった。一方で、社員が高い業務能力を獲得することへの社会的ニーズは高まっている。ここに最大の矛盾と葛藤を抱える企業の実態がある。
著者は人材あるいは人材が有する知識・技術こそが、企業の持続的競争優位を生み出す源泉だと考える。そして、先の矛盾と葛藤に対する1つの答えが「職場」であるという。「職場における他者とのつがなり」を回復させることで、職場のさまざまな人から支援を受け、能力を向上させられるのだ。この職場学習の実態を明らかにするのが本書の主眼であり、そのために著者は2つの問いを立てた。
(1)人は職場で、どのような人々から、どのような支援を受けたり、どのようなコミュニケーションを営んだりしながら業務能力の向上を果たすのか。
(2)職場における人々の学習を支える他者からの支援やコミュニケーションに影響を与える、職場の組織要因とはどのようなものなのか。
これら2つの問いに答えることで、本書の目的達成を図っていく。
職場学習論の位置づけ

Blue Planet Studio/gettyimages
次に、本書のタイトルである「職場学習論」の位置づけについて説明しよう。そのためには、「組織社会化論」「経験学習論」「組織学習論」の3つの研究群について把握する必要がある。
まず、最も古くから研究されている組織社会化論とは、「個人が組織の役割を想定するのに必要な社会的知識や技術を習得し、組織の成員となっていくプロセス」を指す。具体的には、新しいメンバーが「業務に必要とされる知識・能力」を身につけ、訓練を受ける過程である。
次に経験学習論を説明する上では、米国の教育思想家ジョン・デューイの理論が欠かせない。デューイによると経験とは、「連続性の原理」と「相互作用の原理」の2つによって把握される。

この続きを見るには...
残り3832/4686文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2021.08.24
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約