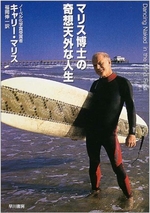異端児たちの決断
日立製作所 川村改革の2000日


著者
小板橋 太郎
日本経済新聞社 企業報道部 デスク
1991年立教大学文学部史学科卒、日本経済新聞社入社。整理部、社会部、産業部記者、日経ビジネス編集委員などを経て現在、日経新聞企業報道部デスク。
記者時代は自動車、ゲーム、エネルギー、電機、通信などの業界を担当。趣味は古地図を見ながら散歩すること。1966年生まれ。東京都出身。
日本経済新聞社 企業報道部 デスク
1991年立教大学文学部史学科卒、日本経済新聞社入社。整理部、社会部、産業部記者、日経ビジネス編集委員などを経て現在、日経新聞企業報道部デスク。
記者時代は自動車、ゲーム、エネルギー、電機、通信などの業界を担当。趣味は古地図を見ながら散歩すること。1966年生まれ。東京都出身。
本書の要点
- 要点1日立製作所は長きに渡る業績不振にあえぎ、債務超過一歩手前のところまで来ていた。立て直しに奔走したのは、社長となった69歳の川村を初め、既に本流から外れている人々だった。
- 要点2経営立て直しにはスピードが重要と考えた川村は、社長と5人の副社長の計6人のみで重要な意思決定を行っていくことにした。「六人組」は100日という短期間で何らかの結果を出すと決め、上場子会社の本体吸収を含めた事業ポートフォリオ入れ替えや、新規事業の立案に取り組んだ。
- 要点3日立を米GEや独シーメンスのようなグローバル企業と戦える集団にするべく、川村は日本の企業としては異例の数の社外取締役や外国人取締役を登用し、最先端の企業ガバナンス体制を敷いた。
要約
OBによる舵取り
日立の改革は年長者がやるしかなかった。
製造業史上最大の7873億円もの最終赤字を計上した日立の経営改革の立役者となった川村隆の社長着任はメディアから驚きの目を持って迎えられた。川村は当時69歳で、前任者である古川より7歳も年長であり、2003年4月に日立の副社長を退任した後は子会社である日立ソフトウェアエンジニアリング、日立マクセルなどの会長を歴任し、2007年には日立本体の取締役からも退いていたからである。
同じく副社長に着任した三好崇司、八丁地隆も日立本体の副社長を既に退任し子会社の社長を務めていた。「OBに経営を託す日立は、それほど人材がいないのか」とさえ揶揄されたが、川村らは意に介さず、「百日プラン」、すなわちこの体制が発足した4月1日から100日目までに何らかの結果を出すことを目標に、社長と5人の副社長の計6人を中心に改革を開始した。
経営再建へのロードマップは次の通りである。
① 出血している事業のリストラ。近づける事業と遠ざける事業の峻別(すなわちポートフォリオ入れ替え)
② 社会イノベーション事業で世界に出る成長戦略
③ 上場子会社を取り込み、社外に流出している利益を取り込む
④ 社内カンパニー制で事業部門を自立させる
日立にはOBをも含めた合意形成を重んじるあまり、必要とされる改革が未達に終わってきたという過去がある。年長者を「尊重」する日立の社風が壁となって、古川時代には実現しなかった上場子会社の本体への吸収も、年長者が舵を握った途端、解決へ向けてスムーズに動き出した。
鈍牛という汚名の返上
100日で結果を出そうと経営陣が奮闘、改革への本気度を示した。

Ivary/Thinkstock
川村の社長就任から120日後、日立は上場子会社5社(日立情報システムズ、日立ソフトウェアエンジニアリング、日立システムアンドサービス、日立プラントテクノロジー、日立マクセル)を完全子会社化すると発表した。これは鈍牛という日立のあだ名を返上するには十分なスピードの決断であった。メディアにはそれほど高く評価されず「やりやすいところから手をつけた」という見方をされがちであったが、市場関係者に日立の改革への本気度を示すものであったと言える。
次に、リストラの対となる成長戦略を示す必要があった。これが「社会イノベーション事業への集中」である。

この続きを見るには...
残り3507/4473文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2014.09.19
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約