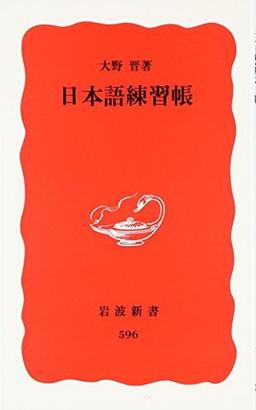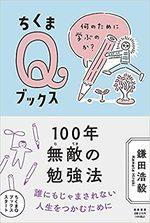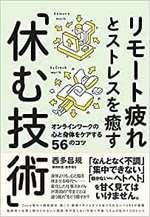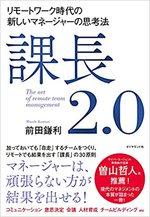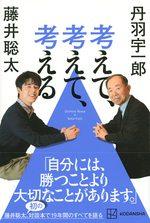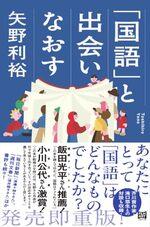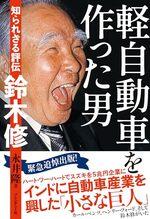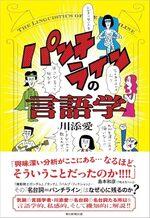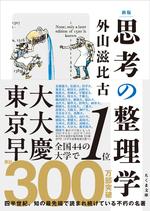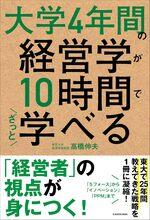「日本語」に敏感になろう
単語のニュアンスに敏感になる
文章はひとつひとつの単語で成り立っている。日本語がよく読めるように、書けるようになりたいならば、まずは単語の形と意味に敏感にならなければならない。
例えば、「思う」と「考える」はどう違うだろうか。「私はこうしようと思った」「私はこうしようと考えた」のように、どちらも使える場合と、「故郷を思う」「問題を考える」のように、いずれかしか使えない場合がある。2つの言葉には意味が重なるところと重ならないところがある。その重なりの大きさは、言葉の組み合わせによってそれぞれ異なる。意味が重なるもの同士の微妙な使い分けが、「言葉のニュアンス」だ。両者の違いを明らかに意識して使い分けられるかが、言葉の使い方の鋭敏さに関わる。
言葉の感覚を研ぎ澄ます

人間は人の書いた文章を読んで、その文脈ごと言葉を覚える。そして、それまでに出会った文例の記憶にもとづいて、言葉づかいが適切かどうかを判断する。文例の記憶が多い人は言葉づかいの判断がしやすくなる。よい言葉づかいをしたいと思う人は、よい文章を多く読んで、文脈ごと言葉を覚えるべきだ。
「新しい言葉」がつくられることもあるが、大部分は一時流行しただけですぐに消えていく。しかし、久米正雄が「微笑」でも「苦笑」でもない笑いを表現した「微苦笑」は、その存在を社会に認められ、今や和英辞典にも載っている。新しい言葉は、人間の行為や社会の状況に応じた必要性からつくられる。それがいい言葉かどうかを感じる鋭い感覚を養うには、まずは自分が区別して使える語彙を増やすことだ。語彙が少なくてはいい表現ができないからだ。