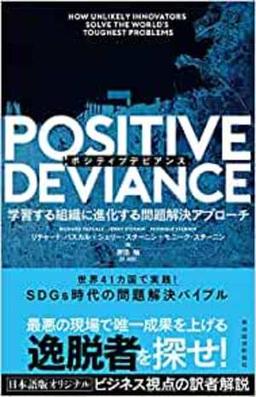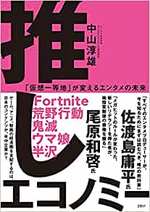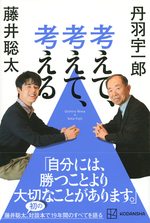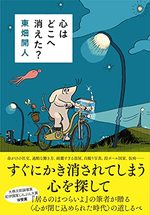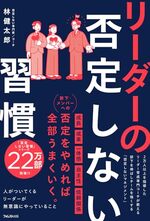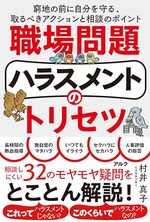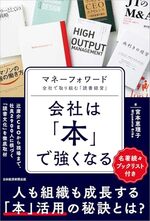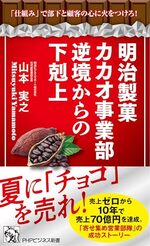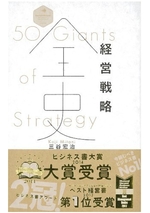ポジティブデビアンスとは何か
ポジティブデビアンスの定義
ポジティブデビアンス(以下PD)のプロセスは、失敗した規範ではなく、成功した例外すなわちポジティブな逸脱者に焦点を合わせる問題解決のアプローチである。この方法論は、コミュニティの中にほかのメンバーと同じ資源であるにもかかわらず、問題をすでに解決している人が少なくとも1人はいるという考えのもとに成り立つ。
前提となるのが次の3点だ。1つめは問題の解決策はすでに存在していること。2つめはその解決策がコミュニティ自身によって発見されること。そして3つめがこれらのイノベーターは、ほかのメンバーと同じ制約や障害に直面しているにもかかわらず成功していることである。コミュニティが自らの資源を活用し、すでに内部に存在している解決策を発見し活用すれば、目の前の問題を解決するだけでなく、将来の課題に有効に対処することができる。
WhatからHowへ

ハーバード大学のロナルド・ハイフェッツ氏は、課題を「技術的問題」と「適応課題」に分類する。技術的問題は、社会構造や文化的規範に煩わされることなく技術的に解決できる。一方、適応課題は、社会的複雑性の中に埋め込まれており、行動の変化を必要とし、意図しない結果を招くことが多い。PDプロセスは適応課題を解決するための手法であり、「何をすべきか」という技術的なWhatではなくHowを重要視する。このHowとは各コミュニティが知恵を発見し、実践していくプロセスである。WhatからHowへのリフレーミングの中で、PDを特定し、それを普及させていくという現場での自律的学習がPDプロセスの本質といえる。
スターニン夫妻が経験してきた具体的なケースを見ていこう。まずはボリビアの高原地帯で、重度の成長障害に苦しむ子どもたちの状況を改善するプロジェクトだ。事前調査では各家庭がほぼ同じものを子どもに食べさせていることがわかっていた。ところが、同様に貧しい状況でありながら正常な身長の子どもがいる家庭があるという。なぜこうした違いが生まれるのだろうか。