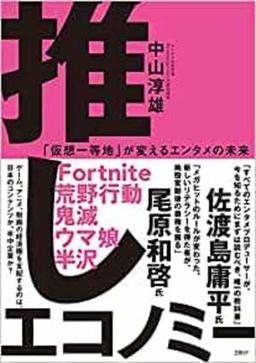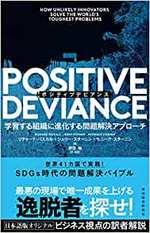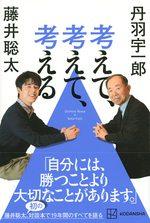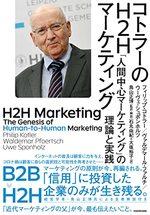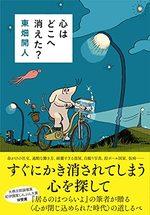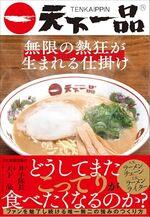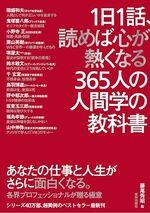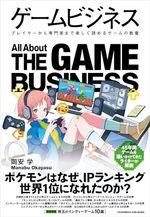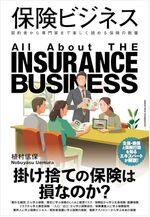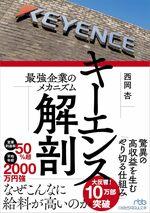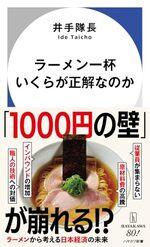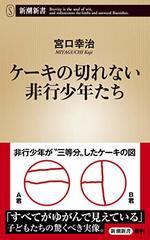メガヒットの裏側で進む地殻変動
「推しエコノミー」とは何か
占星術の領域では、2020年12月、200年ぶりの時代の節目を迎えた。これまで「土の時代」として金銭・物質・権威が重視されてきたが、これからは「風の時代」、すなわち知性・コミュニケーション・個人が重視されるようになるのだという。
スピリチュアルな話だと感じる人も多いかもしれない。著者もその一人だった。だがコロナによって働き方や生活がめまぐるしく変化したことで、著者自身も「200年前の産業革命以来の人類史の方向性が、このタイミングでシフトチェンジするのではないか」と信じるようになった。
ここから発想されたのが、人々が殺到するキャラクターやタレントを「推す」というファンの行動変容が基軸となる「推しエコノミー」である。
テレビアニメのライブ化:『鬼滅の刃』

この50年、エンタメ産業を牽引してきたのはキャラクターであり、それを生み出す源泉は「テレビアニメ」であった。そんなテレビアニメはいま、地殻変動の最中にある。2019年4~9月に放送・配信された『鬼滅の刃』がその好例である。
テレビアニメはここ20年、テレビ局の電波料やCМ枠代が膨れ上がることを嫌って、日本全国にネットワークのない「弱い」放送局であるテレビ東京やTOKYO MXで流れることが多かった。これに対して『鬼滅の刃』は、全国21チャンネルでの同時配信に踏み切っただけでなく、アベマTVやアマゾンプライムなどといった14のインターネット配信サイトでも流された。アニメプロデュースを手がけるアニプレックスは、「放送・配信はお金を稼ぐところではなく、なるべく面を広くとってユーザーに認知してもらうためのもの」と割り切ったのだ。
『鬼滅の刃』が好評を博した後、2020年10月にフジテレビが劇場版公開に合わせてテレビ放送を行った。配信サイトでいつでも見られる1年以上前のコンテンツにお金を出して「フジテレビのみで放送する権利」を獲得したのだ。
これは再放送でありながらも、同じタイミングで皆が同時に視聴できる「ライブ」としての機能を果たし、再放送第1夜の世帯視聴率は20%を超えた。これは『ゆく年くる年』とほとんど変わらない数字だ。
結果として『鬼滅の刃』コミックスの部数は、アニメ化前の2018年11月末の累計300万部から、アニメの放送・配信が終わった19年11月末には2500万部へと大きく増加した。さらにコロナ禍でブームが起き、20年11月末には1.25億部と前年のほぼ5倍になっているほか、ノベルや主題歌も成功を収めている。
『鬼滅の刃』に代表されるアニメの新しいメディア流通戦略は、「脱テレビ」である。もはや多くのテレビアニメにおいて、ストーリーを展開させたりファンを獲得したりしているのは、放送の力ではない。配信や電子書籍、アプリゲームといった他のチャネルが大きな役割を果たしている。
テレビ番組のライブ化:『半沢直樹』
テレビ番組もまた「脱テレビ」を迫られている。2020年に続編が放送された『半沢直樹』は、歌舞伎役者たちの顔芸や捨て台詞が話題となり、ネタ的な画像や台詞をユーザーが模倣したり拡散したりする「祭り」がツイッター上で拡大した。多くの回でツイート数が20万回を超えて世界トレンド1位を獲得し、最終回のツイート数は57.3万回に到達している。「この1時間の放送中に誰よりも面白いことを叫んでやりたい」「今回の顔芸に、いったいみんなどう反応したのだろう」という「劇場を見渡すような」行動が人々を駆り立てたのだろう。
『半沢直樹』ではテレビの「人々を習慣的に動員する力」という特性が如実に現れた。翌日の仕事に向けて気持ちが沈む日曜の夜はリビング着座率が高くなる。このタイミングにこの番組をネタに祭りを楽しむことが認知され、習慣化したと考えられる。
テレビの未来は、お茶の間を使ったライブコンサートだ。リビングにテレビ、その前にソファがあるという「観客席」がある空間は、テレビが持つ絶対的優位性であると言える。テレビを通じた放送・配信は、この「お茶の間劇場」をどう利用するかが試されるのである。
【必読ポイント!】 「萌え」から「推し」へ
ユーザーの価値観の変化

メディアの変化のかげには、ユーザーの変化がある。ユーザーが変わったからメディアが変わり、コンテンツが変わったのだ。ここでは、ユーザーの変化をみていく。
「推し」は、以前は主に女性に使われていた用語で、宝塚やジャニーズなど特定のタレントが、団体のなかで成長・出世していく様子をともに喜び、感動することを指していた。