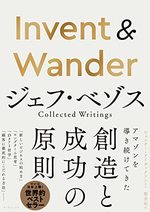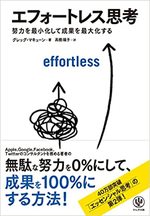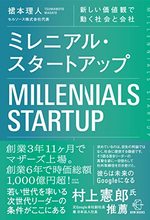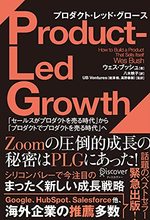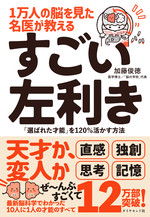Amazon Mechanism (アマゾン・メカニズム)
イノベーション量産の方程式
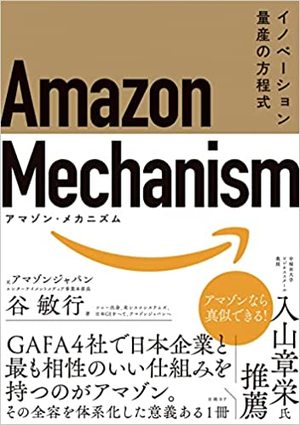
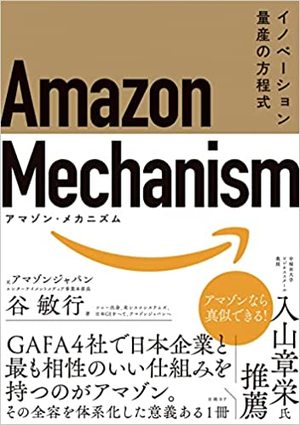
著者
谷敏行(たに としゆき)
東京工業大学工学部卒業後、エンジニアとしてソニーに入社。エレキ全盛期のソニーの「自由闊達にして愉快なる理想工場」の空気に触れながら、デジタルオーディオテープレコーダーなどの開発に携わる。米ニューヨーク大学にて経営学修士号(MBA)取得。1992年にソニー退社後、米国西海岸でIT・エレクトロニクス関連企業のコンサルティングを手掛ける(米アーサー・D・リトルに在籍)。その後、米シスコシステムズにて事業開発部長など歴任。日本GEに転じた後、執行役員、営業統括本部長 、専務執行役員、事業開発本部長など歴任。2013年、アマゾンジャパン入社。エンターテイメントメディア事業本部長、アマゾンアドバタイジング・カントリーマネージャーなど歴任し、2019年退社。現在は、TRAIL INC.でマネージングディレクターを務めるほか、Day One Innovation代表としてイノベーション創出伴走コンサルタントとしても活動。
▶https://dayoneinnovation.com/
東京工業大学工学部卒業後、エンジニアとしてソニーに入社。エレキ全盛期のソニーの「自由闊達にして愉快なる理想工場」の空気に触れながら、デジタルオーディオテープレコーダーなどの開発に携わる。米ニューヨーク大学にて経営学修士号(MBA)取得。1992年にソニー退社後、米国西海岸でIT・エレクトロニクス関連企業のコンサルティングを手掛ける(米アーサー・D・リトルに在籍)。その後、米シスコシステムズにて事業開発部長など歴任。日本GEに転じた後、執行役員、営業統括本部長 、専務執行役員、事業開発本部長など歴任。2013年、アマゾンジャパン入社。エンターテイメントメディア事業本部長、アマゾンアドバタイジング・カントリーマネージャーなど歴任し、2019年退社。現在は、TRAIL INC.でマネージングディレクターを務めるほか、Day One Innovation代表としてイノベーション創出伴走コンサルタントとしても活動。
▶https://dayoneinnovation.com/
本書の要点
- 要点1アマゾンでイノベーションが生まれる理由は、「ベンチャー起業家の環境×大企業のスケール-大企業の落とし穴=最高のイノベーション創出環境」という方程式で表現できる。
- 要点2アマゾンでは徹底的に顧客起点で考える。そのツールとして用いられるのは、「PR/FAQ」と呼ばれる企画書フォーマットだ。このフォーマットを使うことで、どんどんアイデアが出され、顧客視点で徹底的に検討される。
- 要点3アマゾンには、大企業にありがちな問題を防ぐ仕組み・プラクティスがある。社内カニバリゼーションを推奨しているのも、そのひとつである。
要約
なぜアマゾンでは、イノベーションが次々に起こるのか
アマゾンの仕組み・プラクティス
本書の著者は、アマゾンジャパンで新規事業の立ち上げに従事していた。そんな著者がアマゾンでイノベーションが生まれる理由をシンプルに表現すれば、「ベンチャー起業家の環境×大企業のスケール-大企業の落とし穴=最高のイノベーション創出環境」となる。本書では、この方程式を成立させている、アマゾンの「仕組み・プラクティス(習慣行動)」を分解して体系化することで、「アマゾン・イノベーション・メカニズム」として示している。
イノベーションを起こさせる仕組みや環境こそが、他社にないアマゾンの優位性となる「コア・コンピタンス」である――それが著者の見解だ。このアマゾン・イノベーション・メカニズムは、日本企業でも十分再現可能である。
【必読ポイント!】「普通の社員」を「起業家集団」に変える仕組み・プラクティス
「PR/FAQ」で「逆方向に思考する」

anyaberkut/gettyimages
アマゾンでは、イノベーションを創出するための思考プロセスを「ワーキング・バックワード(Working backwards)」と呼ぶ。逆方向に思考するという意味だが、つまり「顧客ニーズからスタートしてそのソリューションとなる製品・サービスを発案する」ことを指す。
その中核を担うツールが「PR/FAQ」と呼ばれる企画書だ。アマゾンで新たな製品・サービスを提案する際には、必ずこのフォーマットが用いられる。PRはプレスリリース、FAQはよくある質問や想定問答のことだ。
一般的にプレスリリースは、サービスや製品を世に送り出す前に、自社のサービスや製品を宣伝するために出される。FAQも、サービスや製品の情報がそろった後に、報道関係者や消費者から質問されそうな内容を想定して用意するものだ。一方アマゾンでは、新サービスや新製品を企画するタイミングでこれらを作っている。
アマゾンのPR/FAQには、主に3点の要素が盛り込まれる。それは「どのようなサービス・製品が市場に導入されるのか」「使用する人にとってどんな利点があるのか」「実際使ってみた人のフィードバックはどうか」だ。企画書を作るプロセスを通じて、企画立案者は顧客視点に立って企画をブラッシュアップすることができる。そして提出されたPR/FAQを検討する際、チーム全員の視点もより顧客中心のものとなっていく。
アマゾンでは、誰もがPR/FAQを作れるように工夫されている。まず、ほとんどの社員がPR/FAQを書くトレーニングを受けていること。そしてそもそも、簡単に作成できるようなフォーマットであることだ。分量としてはA4用紙で1ページほどの長さだ。数時間で書き上げることも決して難しくはない。
アマゾンは、こうして提案のコストを下げることでイノベーションを起こしやすくしている。もし提案フォーマットがもっと複雑ならば、提出される企画の数は減ってしまうだろう。
「沈黙から始まる会議」で「社内政治」を撲滅する
会議資料にも、アマゾンならではのルールがある。

この続きを見るには...
残り2238/3490文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2022.01.24
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約