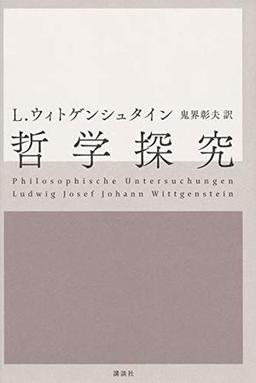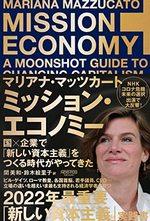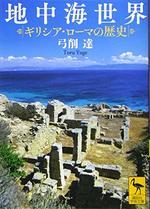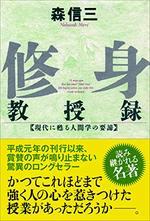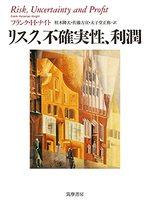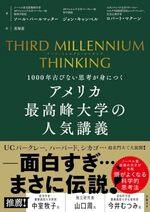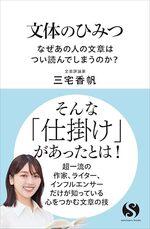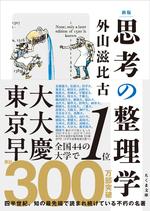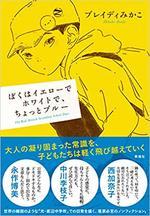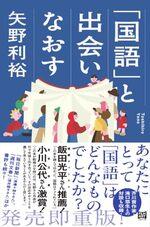【必読ポイント!】 言語ゲーム論
言語ゲームとは何か
語とはある対象の名であり、文とは語が結合したものである、ということが言語の本質とされてきた。それは、すべての語には意味があるという考えの根源である。ここでは名詞以外の品詞は二の次となっている。
しかし、次のような場面について考えてみよう。「五 赤 リンゴ」と書かれた紙切れを渡して誰かに買い物に行かせ、それを店員に見せるよう指示する。店員は「リンゴ」と書かれた引き出しを開け、「赤」の色見本を見てから、数を順に五まで数えて、色見本と同じリンゴを取り出す。
またこのような場面はどうだろうか。石材建築をしている作業者が助手に「ブロック」「板」などと言えば、助手がその言葉に適した石材を運ぶ。
言語の実践においては、一方が語を提示し、他方はそれに応じて行動するといえる。子供が母語を習得する際、教える者が物を指し示してその名前を呼ぶことで、子供の心にその物の像が浮かぶと思われるかもしれない。だが、それは決まったやり方でそう教えられた場合にのみ引き起こされるのであって、違う方法で教えられれば、同じ指し示しでもまったく別の理解をもたらすのだ。
以上のような語の使用過程全体、また言語と、織り合わされる活動の総体を、本書では「言語ゲーム」と呼ぶ。
言葉の意味は使用によって知られる
語の意味は、それだけで何かを表すものとしてではなく、実際の使用において知られる。
先ほどの石材建築現場において、「板」といった言葉のほかに、数を表わす一連のアルファベットと「これ」などの言葉、何かを指差す手の動きを組み合わせて用いるとする。作業者がある場所を指しながら「d-板-そこへ」という命令を発すると、助手は該当するd枚の石材を指定された場所へ運ぶ。
作業者が助手に「板!」と叫べば、それは「私に板を持ってきてくれ!」という文と同じ意味に理解されるだろう。このように、一語のものと、いくつかの語が組み合わさった文が同じ意味を持つのは、それらが同じように使用されるからである。
文には数限りなく多様な種類の使用の仕方が存在し、新しい型(言語ゲーム)が生まれては別の型が忘れられていく。命令する、対象を記述する、報告する、仮説を立てて検証する、物語を創作して朗読する、冗談を言う、ある言語を別の言語に翻訳する……。言語ゲームとはかように多様であり、それがわかっていれば「問いとは何か」という問いを発する必要もない。
家族的類似性
言語ゲーム、つまり言語の本質とは何か。言語は、共通の一般形式があるから成立するのではない。相互に、様々に異なった仕方で類似しているものを、我々は「言語」と呼んでいるのだ。
たとえば、「ゲーム」と呼ばれる事象には盤上のゲーム、カードゲーム、ボールを使うゲーム、格闘的なゲームなどがあるが、これらに共通するものがあるかどうかをただ眺めてみよう。そこに見られるのは、すべてに共通するような何かではなく、いくつもの種類の類似性だ。
このように、互いに重なり、交差している様々な類似性を「家族的類似性」と表現できる。ある家族には体格、目の色、性格といった様々な交差した類似性があるように、様々な「ゲーム」も一つの家族を形成していると言える。
ゲームという概念には、明確な定義や境界が存在するわけではない。たしかに、どこまでがゲームでどこからがゲームではないのか、特定の目的のために境界線を引くことはできる。しかし、「一歩=75㎝」と定義した人が初めて「一歩」という尺度を使えるようになったわけではないのと同じように、ゲームという概念の境界を厳密に定めなければその意味がわからないというわけではない。
ある人に特定の地点を指差し、「大体この辺に立ってくれ!」と指示できる。それと同じように、ゲームという輪郭のぼんやりとした概念を理解させるためには、様々な例を挙げ、それを指定のやり方で利用してほしいと説明すればよい。ゲームはまさにそのように行われているのだから。