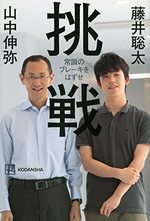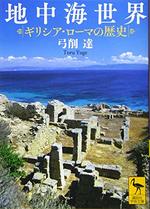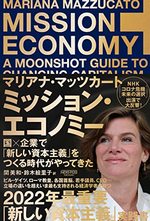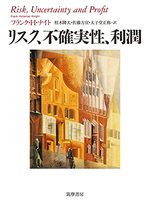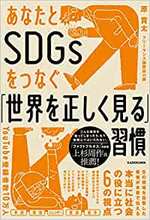デカルト入門
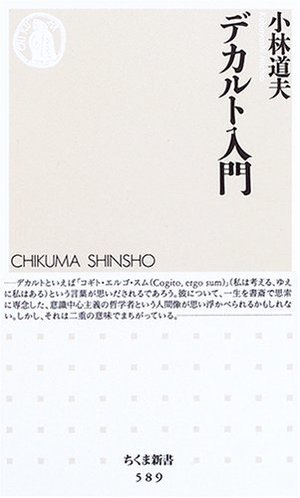
デカルト入門
著者
著者
小林道夫(こばやし みちお)
1945年生まれ。京都大学文学部哲学科卒業。Docteur de 3e cycle(パリ・ソルボンヌ大学)。西洋近代哲学・科学哲学専攻。京都大学名誉教授。デカルトを中心とする近世ヨーロッパ哲学および科学哲学研究の第一線で活躍。著書に『デカルト哲学の体系―自然学・形而上学・道徳論』(勁草書房)、『科学哲学』(産業図書)、『デカルトの自然哲学』(岩波書店)、『デカルト哲学とその射程』(弘文堂)、『自然観の展開と形而上学』(共編集、紀伊國屋書店)、訳書にデカルト『哲学の原理』(共編訳、朝日出版社)、ピエール・デュエム『物理理論の目的と構造』(共訳、勁草書房)などがある。2015年逝去。
1945年生まれ。京都大学文学部哲学科卒業。Docteur de 3e cycle(パリ・ソルボンヌ大学)。西洋近代哲学・科学哲学専攻。京都大学名誉教授。デカルトを中心とする近世ヨーロッパ哲学および科学哲学研究の第一線で活躍。著書に『デカルト哲学の体系―自然学・形而上学・道徳論』(勁草書房)、『科学哲学』(産業図書)、『デカルトの自然哲学』(岩波書店)、『デカルト哲学とその射程』(弘文堂)、『自然観の展開と形而上学』(共編集、紀伊國屋書店)、訳書にデカルト『哲学の原理』(共編訳、朝日出版社)、ピエール・デュエム『物理理論の目的と構造』(共訳、勁草書房)などがある。2015年逝去。
本書の要点
- 要点1行動の人であるデカルトは、すべてのものを疑おうと決意する一方で、そのように疑う自分という存在は疑うことはできないと考えた。
- 要点2自己意識から出発して哲学によって論じられる神の存在証明を行った。
- 要点3宇宙全体を等質なものとする近代の自然観につながるものを打ち立てた。
- 要点4身体を動かすという行為のあり方そのものは、科学的に理解できるものではない。体得するしかない。
- 要点5人はただ一人では生存できない。ゆえに、自分よりもみずからが属する全体の利害を優先しなければならない。
要約
デカルトの生涯と思想
病弱だった青年時代
デカルトはどういう人物で、どのような思想を展開した人だろうか。「コギト・エルゴ・スム(Cogito, ergo sum)」(私は考える、ゆえに私はある)という言葉に代表されるように、デカルトはこのラテン語のコギト(自己意識)を哲学の第一原理にすえ、近代哲学の基礎を築いたと言われている。その彼は実際には、一生を書斎で過ごした意識中心主義の哲学者というより、行動半径の広い劇的な生涯を送り、数学や生理学など諸科学にわたる新たな理論体系を構築した人間であった。
1596年フランス、医師の家系に生まれた。病弱で、若くして死ぬと医師に言われ続けた青年時代、ヨーロッパ中世のスコラ哲学をその教育体制の中心としつつ、リベラルな面も備えた寄宿学校で過ごした。体の弱かったデカルトはその教育に対して、「自分に有用なこと」を熱心に求めようとしていた。
行動人デカルトがみた夢
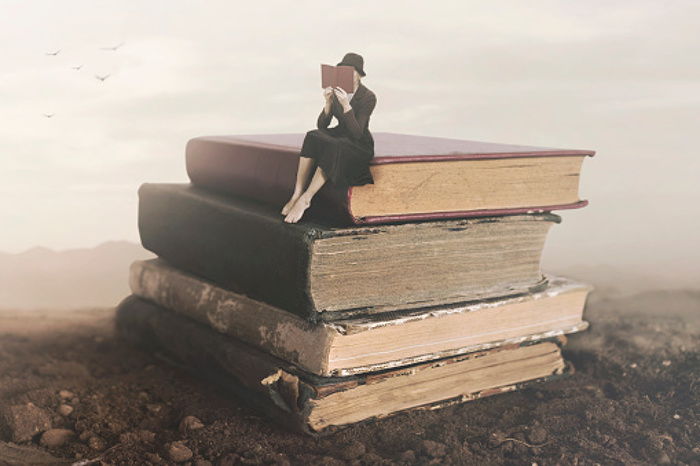
fcscafeine/gettyimages
大学を卒業したデカルトは個人的な決断で軍隊という現実の世界に身を投じる。「書物の学問」を放棄し、「世界という大きな書物」のなかで生を歩みたいと考えたのだ。
数年間、デカルトはさまざまな体験をし、多くの人々の行動を観察したが、そこにあったのは哲学におけるのと変わらない文化の多様性だけだった。
だから彼は「自分自身をも研究しよう」と考えるに至り、ドナウ河畔のとある村にとどまって思索に耽ることになる。そうして終日炉部屋にただひとりとじこもり、「デカルトの夢」を見た。それは具体的には、諸学問の新たな統一的構築を求める構想であり、思想史上の革命をもたらすものであった。
4つの規則と3つの指針
そしてデカルトは、「自分の精神が受け入れうるあらゆることがらの認識に達するための真の方法」として、4つの規則を掲げることにした。
第一は「明証」の規則であり、「明晰判明なもののみを真とすべし」という規範を示し、疑いが少しでもあるものは判断に用いないとする。第二は「分析」で、困難は容易に扱える小部分に必要なだけ分割せよと指示する。第三の「総合」は、分割したものを簡単なものから順番に複合していくことを指す。第四の「枚挙」は、そうして総合された知識の全体を見落とさずに把握することを示す。
またデカルトは、十分に成熟した年齢に達し、堅固な哲学を築き上げるまでの善い生き方の指針として、3つの「仮の道徳」を定めた。まず、自らの精神の自由を守るため、「最も分別のある人々」が受け入れている考え方や「最も穏健な意見」にしたがうという保守主義。次に、最も蓋然的な選択肢を選ばざるを得ないとしても、その決断自体は「確実な真理」であるということ。そして、「必然」である運命や世界の秩序ではなく、自己の欲望を変え、それに打ち勝つことを格率とした。
近代思想の幕開けとデカルトの死
デカルトはこのような「自己の思想あるいは理性の開発こそが最善の途である」と決意しながら、1620年からの9年間、世界をめぐり歩いた。その旅のなかで特筆すべきは、彼がある女性をめぐって決闘をしたり、彼自身の経験をもとに『剣術』という論考を書いたりしていることだ。まさに行動人デカルトの武断ぶりが如実に示されているといえよう。
ブルターニュでこれまでに積み上げた方法論的考察を『精神指導の規則』(生前未公刊)にまとめた後、オランダに隠棲して形而上学に没頭し、1637年に『方法序説』を出版した。この本は、人間精神の生まれつきの「平等」と自分に与えられた理性を開発する「責任」という、緊張関係にある近代社会の概念を同時に示すものであった。
さらには自身の形而上学を発展させた主著である『省察』(1641年)、そして『哲学の原理』(1644年)を出版した。『哲学の原理』では、全宇宙を力学的に解明することに力を注いだ。
後半生では、エリザベト王女との文通によって「心身問題」が提起され、『情念論』(1649年)で道徳論を完成させた。その後スウェーデンへ移住し、1650年の2月に肺炎で亡くなっている。
【必読ポイント!】 デカルトの認識論と形而上学
「私」の存在・「私」の本質

metamorworks/gettyimages
近世哲学の原点ともされる「私はある」の哲学の第一命題は、どのようにして生まれたのだろうか。

この続きを見るには...
残り1947/3687文字
4,000冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2022.02.16
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約