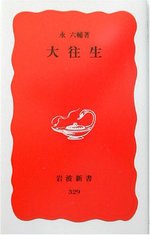自省録
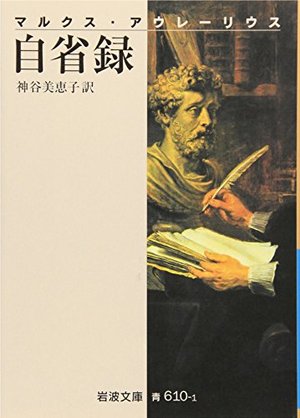
自省録
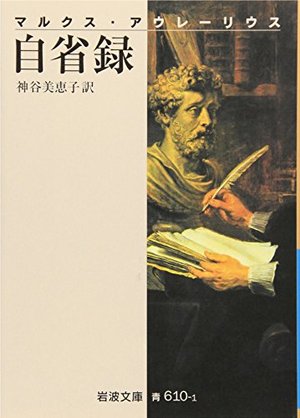
著者
マルクス・アウレーリウス(Marcus Aurelius)
本書の要点
- 要点1宇宙全体からすれば人生は一瞬であり、死後の名声もすぐに忘却され、全ての物事はやがて消え去る。名誉や快楽、富も善ではない。快楽や苦痛を統御し、揺るぎなく自己を全うするよう導くのは哲学のみである。
- 要点2他人が自分に対して過ちを犯したとき、その人が自分と同じような善悪の観念を持っていることに気づけば、その人を憐れみこそすれ、怒ることはなくなるだろう。
- 要点3すべての悩みの種となる主観を捨てれば、波の立たない水面のような静かな心に至ることができる。善い人間とは何かを論じる以前に、善い人間にならなければならない。
要約
何事も恐れず、揺るがない生き方
養父から学んだこと
本書は、マルクス・アウレーリウスがさまざまな人物、事柄から得たものへの感謝から始まる。たとえば、養父アントーニウス・ピウス帝の振る舞いから学んだのは次のようなことである。
温和でありながらも、いったん決断したことは守り通す。虚しい虚栄心をいだかず、公共的精神がなんたるかを知り、ものを徹底的に検討する態度をもつ。
あるいは、自らに対する喝采や追従をとどめ、帝国の要務について日夜心を砕き、そこで生じる非難を甘受する。大衆に媚びて人気を集めようとはせず、きまじめで着実に、卑俗に陥ることもない。
真の哲学者たちを尊敬する一方で、その他の人々に批評がましく接することもなく、かといってかれらにたやすく惑わされもしない。人づきあいのよさと気難しいところのない慇懃さを持ち合わせ、医者や薬を必要としないほど、自分の肉体に対しても節度ある配慮をする。
雄弁や法律などの知識で卓越した才能を持つ人に対しては、妬まずに譲るどころか、熱心に援助もする。政治に関するもの以外の秘密をほとんど持つこともなかった。
粗暴でも厚顔でも激しい性格でもなく、「汗みどろ」になるようなところもなかった。静かに、秩序正しく、終始一貫して思慮深く行動した。マルクス・アウレーリウスの養父は、強く忍耐深く節制を守るという、完全で不屈の魂を持った人間の最たる例である。
自らを導くのは哲学だけ

Crisfotolux/gettyimages
続く第2巻では、次のようなことが展開されている。
口うるさい者、横柄な者、やきもち屋といった人たちの欠点は、善と悪が何であるのかを知らないことに由来する。善の本性は美しく、悪は醜いこと、そして悪を為す者も自分と同じ叡智を共有していることを悟っていれば、誰も自身を良からぬことに巻き込むことはできない。だからこそ、そういった同胞に対して怒りや憎しみを抱くことはない。両足や両手、両目、上下の歯列のように、私たちは協力し合うために生まれたのであり、互いに腹を立て、毛嫌いし合うようなことは自然に反するのだ。
平穏で敬虔な生涯を過ごすために、あらゆる行動を一生で一度きりのもののように行おう。人生は短く、ほとんど終わりに近づいているなら一層、自分を大事にする時間などもうない。今すぐにでも人生を去ることのできる者のように行動し、話し、考えよう。
死と生、名誉と不名誉、苦痛と快楽、富と貧しさは善人にも悪人にも平等に起こるのだから、それ自体は善でも悪でもない。
体は宇宙の中に、記憶は永遠の中に、すべてのものはすみやかに消え去っていく。死とは自然のなすこと以外の何ものでもなく、自然にとって有益でさえあるのだから、恐れる必要はまったくない。
たとえ三万年生きるとしても、今生きている生涯以外の何ものも失うことはなく、他の生涯を生きることもない。人が失うもの、持っているものは現在だけであり、現在は万人にとって同じものだ。長命であろうと短命であろうと、失えるものは現在だけである。
肉体は腐敗しやすく、魂のもつ運命は不確実で夢のようなものだ。人生は戦いであり、死後の名声は忘却にすぎない。私たちを導くことができるのはただ一つ、哲学だけである。内なる魂を守り、快楽と苦痛を統御し、他人が何をしようと気にせずに自己の本分を全うし、安らかな心で死を待てるように示すことである。
自制心が人間を自由にする

wataru aoki/gettyimages
第4巻の終わりから第6巻にかけては以下のようなことが記されている。
多くの人間を殺し、不死身であるかのように傲慢に権力をふるった多くの暴君であっても、結局死を迎えた。都市も、私たちが知る人たちも、次々と死んでしまう。しかもこれらは束の間の出来事だ。人間に関する事柄は全て取るに足らないものだと認識すべきである。昨日は少しばかりの粘液だったものが、明日にはミイラか灰になる。このほんのわずかな時間を自然に従って歩み、安らかに旅路を終えよう。
なぜ、あることを不運と感じ、このことは幸運と感じるのか。人は、人間の本性の失敗でないことまで人間の不幸だと思ってしまう。悲しみに囚われそうなときには、つぎの信条を思い出そう。「これは不運ではない。しかしこれを気高く耐え忍ぶことは幸運である。」
朝、目覚めるのが億劫なときには、こう自分に言い聞かせよう。

この続きを見るには...
残り2431/4180文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2022.05.05
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約