存在と無
現象学的存在論の試み Ⅰ
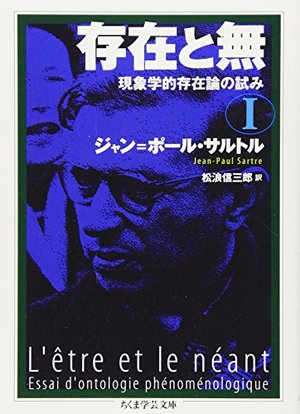
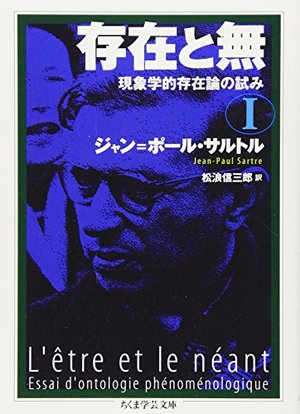
著者
ジャン=ポール・サルトル(Jean-Paul Sartre)
1905-80年。パリに生まれ、高等師範学校に学び、哲学の教授資格を取得。1930年代から独自に現象学を研究し、『自我の超越性』『想像力』『情動論粗描』などを発表。その現象学的総決算が、本書『存在と無』(1943年刊)である。戦後教壇を去り、「実存主義はヒューマニズムか」と題する講演で一躍マスコミの脚光を浴び、実存主義ブームを巻き起こす。在野の知識人として、小説、文学評論、政治論文と幅広い執筆活動を行う。1964年にはノーベル文学賞を辞退。彼の葬儀には何万人という市民が参集した。著書に『嘔吐』『自由への道』『聖ジュネ』『弁証法的理性批判』など多数。
1905-80年。パリに生まれ、高等師範学校に学び、哲学の教授資格を取得。1930年代から独自に現象学を研究し、『自我の超越性』『想像力』『情動論粗描』などを発表。その現象学的総決算が、本書『存在と無』(1943年刊)である。戦後教壇を去り、「実存主義はヒューマニズムか」と題する講演で一躍マスコミの脚光を浴び、実存主義ブームを巻き起こす。在野の知識人として、小説、文学評論、政治論文と幅広い執筆活動を行う。1964年にはノーベル文学賞を辞退。彼の葬儀には何万人という市民が参集した。著書に『嘔吐』『自由への道』『聖ジュネ』『弁証法的理性批判』など多数。
本書の要点
- 要点1現象学の哲学は意識の現れに着目したが、意識は存在のあらわれであり、存在は存在しないということも同時に意味するため、存在と無を研究しなければならない。
- 要点2存在それ自体は、他の何かによってもたらされるのではなく、それ自体によって「それがあるところのものとしてある」という形で即自的に存在する。
- 要点3存在は、それが「あらぬ」ものとしての否定、無によって際立たせられる。無はあらかじめあるのではなく、存在の否定として、人間によって世界にもたらされる。
要約
存在とは何か
存在を語るべきとき

francescoch/gettyimages
現代思想は、〈存在〉とその〈現われ〉という二元論の難問を、〈現象〉という一元論によって克服しようとしてきたが、はたしてそれは成功しただろうか。
たしかに現象学によって、内面と外面とを対立させ、現われの背後に存在や本質を信じる二元論は哲学において市民権を失った。現象は、自分自身の本質とともに現実存在をあらわすからだ。
それでもあらゆる二元論が克服されたわけではなく、有限なものと無限なものという、新たな二元論へと転じたようである。現われは、たえず変化する無限に多様な主観と関係しているためだ。
茶碗の実在性は、それがまさに“そこにあり”、私では“あらぬ”ということを指す。有限である現われは、無限な現われの連鎖、あらゆる可能な観点の無限性においてとらえられなくてはならない、ということだ。〈あらわれること〉が現われの本質であり、「あらわれない存在」はそれに対立する。これにまつわる問題が、存在と無に関する研究の出発点となる。
現われは、他のどのような存在者に支えられているわけではなく、それ自身の存在をもっている。私たちは存在について語り、一種の了解を抱いている。そのため、あるものとして記述できる一つの存在現象、存在の現われというべきものがあるはずだ。
存在は、倦怠や吐き気といった直接的な接近の形で私たちの前にあらわれるだろう。しかし、私にとってあらわれる存在(存在現象)は、あらわれる諸々の存在者(個別の対象)の存在と同じ性質のものなのだろうか。
私たちは、対象の色や香りといった性質を区別できるし、そこに含まれる本質をとらえることができる。ただし、存在とは対象のこうした性質の一つではない。たとえば、不在もまたそこに存在しないということで存在を意味する以上、存在は現在だけを意味するのではないからである。対象が存在を所有するのではなく、「それは存在する」という仕方のみによって、その存在が規定される。
存在者(対象)は現象であり、自身を諸性質の組織的総体として〈それ自体〉を示す。こうした現象の存在は、私たちの認識の根拠をなすものである。
即自という存在者
現象論者たちが対象をその現われのまとまりに還元したのは正当だった。しかし、それはすでに存在している諸存在の間の関係を示すものでしかなく、したがって、存在のしかた(知覚されるものという相対性および受動性)だけにしか適用されえない諸概念によって存在を説明するという誤りにつながった。
あらゆる意識は何ものかについての意識である。意識は、その意識とは異なる一つの存在に向けられるがために生まれるのであり、それは純然たる主観性が先にあるという考えを否定する。したがって意識とは、意識ではない存在を巻き添えにしながら、意識自体の存在を問題とするような一つの存在であると定式化できる。意識が巻き添えとするのは、そこにあるテーブルやシガレット・ケース、すなわち世界の存在である。この「意識にとって」存在するものは、すでに「即自的に(それ自体において)」存在している。
存在は神の創造によって与えられたとは考えられない。存在が神の主観性の中にあるとすると、客観性の表象や創造は不可能になってしまうからだ。かといって、存在は自己自身を創造するわけではない。自分を創造する存在が先に存在することになるからだ。
存在は、それ自体においてある。これは、「存在はそれがあるところのものである」ということを意味し、すなわち即自存在の領域を示す。同時に、自分以外の別のものとして自己をとらえることもできない。存在はいかなる否定も持たず、全くの肯定性だけを備えるのだ。存在が崩壊するときにも、もはやその存在はあらぬと言うこともできない。時間的にそうとらえられるのは意識だけだ。
存在はある、存在はそれ自体においてある、存在はそれがあるところのものであるという3つが、存在現象の検討によって導かれた即自存在の特徴である。
【必読ポイント!】 無と自由、不安、人間存在
無はどこから来るのか

allanswart/gettyimages
人は探究において、問うことによって「それはこれこれであって、それ以外の何ものでもない」とする客観的な答えを期待する。存在に関する問いは、非存在、それがそれで「あらぬ」ところのものに条件づけられているのだ。かくして私たちは、人間的存在と即自存在との関係だけでなく、存在と非存在との関係をもとりあつかわなければならない。
財布のなかにあるお金が思ったより少なかった場合、それ「しか」お金を見いだせないのは、これだけあると思った金額が実際にはないという非存在が人間の期待の内にあらわれているからである。

この続きを見るには...
残り1865/3773文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2022.08.06
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約




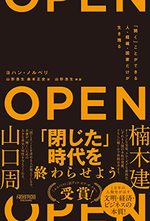
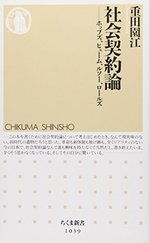
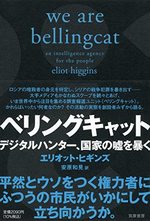



![自己信頼[新訳]](https://fd-flier-static-prod-endpoint-b6g9b5dkedfkeqcc.a03.azurefd.net/summary/3082_cover_150.jpg)
![ニコマコス倫理学(上)[全2冊]](https://fd-flier-static-prod-endpoint-b6g9b5dkedfkeqcc.a03.azurefd.net/summary/3038_cover_150.jpg)
