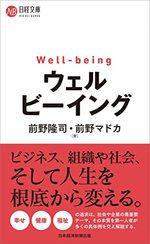「ピアニスト反田恭平」の誕生
1枚のチラシが運んだピアノとの出会い

著者がピアノに出会ったのは3歳のときだった。転勤族として名古屋で暮らしていたとき、社宅に1枚のチラシが投げ込まれた。ヤマハ音楽教室のチラシであった。
それから半年ほどして東京への転勤が決まったとき、音楽教室の先生は母にこう言った。「この子はとんでもなく耳が良すぎます。東京に行ってからも、必ず何か音楽を続けてくださいね」。このときは音あてクイズでちょっとしたズルをしていただけのつもりだった。しかし、東京で通い始めた、子どもに絶対音感を教える「一音会ミュージックスクール」で、耳に入ってきた音をそのまま再現できる能力が特殊なものであることに気づいた。
一音会では、スパルタではなく「音を楽しむ」ことを教えてくれる先生から、ピアノのレッスンを受け始めた。
反田ファミリーは音楽とは無縁の一家であった。家系にピアニストやプロの音楽家は一人もおらず、特に父親は音楽にまったく関心がなかった。著者当人も「本業はサッカー」というほどのサッカー少年で、ピアノはあくまで「趣味」であり、音楽の基礎をまったくわかっていないほどだった。
しかし、11歳のときにサッカーで右手首を骨折したことをきっかけに、サッカー選手になる夢を断念する。そして「近所にあるから」というだけの理由で、桐朋学園大学音楽学部附属「子供のための音楽教室」に入学した。その当時の著者は教室の底辺層であった。しかも、2021年のショパン国際ピアノコンクールで4位に輝いた小林愛実さんも通っていた。小林さんはその当時すでに「天才少女」と全国で有名な存在だった。著者とは家族ぐるみの付き合いをしていた仲の良い幼なじみであり、ともに切磋琢磨をしていったライバルでもあった。
「音楽の世界で生きていく」と決める
音楽にシフトチェンジした理由には、オーケストラの指揮者へのあこがれもあった。音楽教室が主催した「子どものための指揮者のワークショップ」で、プロのフルオーケストラの前で指揮棒を振る機会を得たのだ。
著者はこのときの衝撃を今も忘れられないという。指揮台に立ったときの重圧と張り詰めた緊張感、そして指揮棒で合図をした瞬間に全身にぶつかってくる金管楽器のものすごい音圧。きらびやかで豊穣な音楽の世界がそこにあった。12歳の夏、「自分はこの世界で生きていこう」と肚を決めた。
ワークショップの後、指導をしてくれた指揮者の曽我大介先生に「どうしたら先生のような指揮者になれますか?」と質問をした。すると先生は、まずピアノを極めることを勧めたのだった。
ショパン国際ピアノコンクール
著者がショパンコンクールを強く意識したのは12歳のときだ。NHKのドキュメンタリー番組を観て、「ピアニストの世界にも、ワールドカップのようなすごい大会があるのか」と興味を持った。
それから10年後の2015年、小林愛実さんがショパンコンクールに出場してファイナル(最終審査)まで勝ち進んだ。当時、留学先の国立モスクワ音楽院でくすぶっていた著者は「うらやましい、自分も出たい」と本気で思った。
しかし、そこには葛藤もあった。