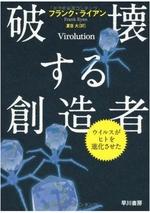第一次大戦をめぐって何が問題になってきたか
戦争責任論から大戦全体史に迫る国際共同研究へ
第一次大戦開戦直後から、各国は自国の参戦を正当化するための外交資料を公表していた。これらの比較をもとに戦後すぐに、大戦原因や開戦責任を解明しようとする動きが出てきた。大戦が「ドイツとその同盟国の攻撃によって」引き起こされたとし、これを賠償請求の根拠にするヴェルサイユ講和条約が締結されると、この解釈を不当とするドイツと戦勝国との間で論争がさらに激化した。
大戦研究は長い時期を視野に収めた大戦起源論に重心を移していき、1930年代後半にはドイツ単独責任論の見直しも進み、特定国の責任を問えないという合意に至った。
その後第一次大戦史への関心は長らく下火であったが、1950年代末にドイツが開戦に積極的役割を果たしたとするドイツ歴史家フィッシャーの説が現れると、国内外で再び激しい論争となった。この説は1960年代後半には大筋で認められ、その後も修正は加えられてはいるが、現在まで有力な説となっている。
冷戦終結後の1990年代以降、第一次大戦の歴史的位置づけについて新たな見直しが始まった。国際的プロジェクトなどを通して大戦の全体像、全体史に迫ろうとするなど、現代で第一次大戦研究が再び高まりをみせている。
1914年 大戦の始まり
参戦へと駆り立てる列強の論理
1914年6月オーストリア帝国皇位継承者が暗殺されたサライェヴォ事件は、当時の列強の帝国主義的進出や、バルカン地域の国民国家確立を目指すナショナリズムが競合する文脈で見る必要がある。
1890年代後半からのドイツの世界政策の路線変更を受けて、20世紀に入ると次第に列強体制は、独・墺・伊の三国同盟と、英・仏・露の三国協商の二極化、対立化が進む。19世紀以降独立を目指してオスマン帝国と対立を繰り返し「ヨーロッパの火薬庫」と評されたバルカン半島は、1908年以降からオスマン帝国の弱体化や諸国の自立の動きが顕著になると、列強の介入が強まり、一触即発の「ヨーロッパの導火線」と化した。
サライェヴォ事件後の7月、オーストリアはセルビアとの二国間戦争に踏み切る。これに対しスラヴ系諸民族の盟主を自認するロシアが総動員例を発令し、ドイツも8月1日そのロシアに宣戦し、それぞれの同盟国を巻き込んで列強の大戦が始まった。
参戦動機は各列強により異なる。多民族帝国ロシアとオーストリアは、とりわけ自国内の分裂危機とバルカン地域などでの国際的な地位の低下を恐れて参戦したが、ドイツはヨーロッパのヘゲモニー(覇権)の掌握 、英・仏はそれを阻止し、既得権を守るために参戦した。一方、戦争の傍観は列強としての地位を弱めるとする伝統的列強の論理や、生存競争に勝ち残る国を正当と認め、そのための戦争を政治手段と認める社会ダーウィン主義的価値観、また一握りの政府・軍首脳が参戦の決断を下したことは、どの列強にも共通していた。
物量戦がもたらした国内体制の変革と戦況
戦況の膠着
1915年から16年の間は両陣営とも新たな同盟国を獲得し、航空機や毒ガスなどの新兵器を投入し、激しい攻防を繰り返すが、戦況は膠着状態が続いた。1916年にドイツは狭い戦線での兵力集中攻撃(ヴェルダン戦)、広い前線での攻撃(ソンム戦)、広域の多戦線での同時攻撃(ブルシーロフ)という多数の大砲を投入した三つの陣地戦打開の方法を試みたが、ブルシーロフ攻勢を除けば戦線突破は失敗し、プルシーロフも予備兵力不足で途中で挫折した。
開戦後イギリスは海軍増強で制海権を強固にし、遠海封鎖でドイツの通商路を遮断した。これに対抗しドイツは潜水艦による商船攻撃を始めるが、