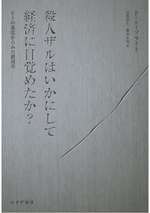歴史として戦後をどうみるか
歴史をするのか、歴史を書くのか、歴史を考えるのか
渡邊昭夫は、 Doing history? というテーマで、ナジタ・テツオ、キャロル・グラック、升味準之輔の著書を手掛かりに、近代化という大きな枠組みの中で日本の戦後とは何か、またそれを考える作業である歴史研究について論じた。
日本の戦後史については、進歩的知識人による批判的な見方と、肯定的な見方があるが、60年安保騒動は分水嶺で、その後民衆のエネルギーからの知的なインパクトとして色川大吉に代表される民衆史が生まれた。70年代以降は、「近代のプロジェクト」の議論を経て、「近代後」という不安、問題意識を、先進資本主義国が共通に抱える時代に入ったとする。ナジタは、歴史を「する」とは、「過去のテクストを訳し、ある言葉を別の言葉に置き換える」、グラックは、「過去を使って未来のために考える」とし、両者とも歴史を材料に自己の考え方を展開させていく。升味は、「歴史を書く以外に歴史を考える方法があるのか」と問題提起する。
戦後体制下の政治と政党
行政学から戦後政治学へのアプローチ
村松岐夫は、研究をはじめた頃からの関心領域や思索経緯をたどりながら、これまでの実証主義的研究成果やそこから出た主張をまとめた。
政策アクター調査(官僚調査)を10年ごとに3回行い、政官関係をみていったことで、これまでの官中心のパラダイムと異なる国会・政治中心のパラダイム、政党優位論を主張するに至った。これは同時に、戦前と戦後は断絶しており、地方自治論においても従来の中央・地方の垂直的行政統制モデルとは異なるモデルの必要性を意味する。政官の協力的関係がなくなり、政党優位が露骨に現れる98年ごろ、政官スクラムは崩壊していったと考える。
戦後日本のシステムを多元主義、新自由主義、ポピュリズムの観点から読み解く

大嶽秀夫は、日本政治と他国の政治を比較するため、日本政治分析に多元主義の視点を導入した。多元主義とは、政策決定者の多元性を示し、流動的な政治体制の中で利害がぶつかり合い政策形成されるという意味、それぞれの分野の政策決定の場(アリーナ)が相互に独立して存在し、それぞれのアリーナの中にもイニシアチブをとるグループが存在するという意味、あるいは政治、経済、社会分野で、相対独立したエリートがいるというエリートの多元性という意味で理解される。しかし、実際のケーススタディでは、多元主義の理論化は、政策決定もモデル自体も流動性が高いため難しく、単なる叙述に陥る危険がある。
一方自身の実証研究から、政治主導で経済成長を計る立場と、経済の自立性を尊ぶ自由主義の立場が、縦断的に日本に根強く存在することを示し、自由主義と社会民主主義の対立やポピュリズムの問題も指摘する。
自民党政権に連れ添われた日本の戦後
牧原出は、戦後、自民党政治は可変的な一方、占領下の時代、経済成長時代、停滞とデフレの時期に重要な質的変容があり、これらは戦後の理解に非常に重要だとする。同時に、戦後像自体も時代と共に変化してきているのではと指摘する。