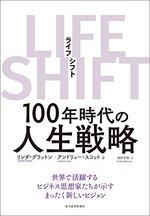【必読ポイント!】 文化人類学とは何か
「あたりまえ」を見つめ直す
文化人類学とは、「(異)文化や人類のことを扱う学問」を指す。そこに生きている人たちのことをただ書き留めて考察するだけでなく、相手側の視点から私たちの世界を見つめ返すことで、既成のやり方や考えを疑ってみる姿勢を持つ。それは、「これからの時代を生き抜く」ことができるという思い込みを問い直すことにもつながる。
20世紀の偉大な人類学者クロード・レヴィ=ストロースは『悲しき熱帯』の中で、「世界は人間なしに始まったし、人間なしに終わるだろう」と述べている。文化人類学では、地球規模の時間軸、人間の存在しない世界をも念頭に置きつつ、多種多様な文化を持つ人間の姿かたちを記録し、考えるのだ。
未知の土地に出向き、そこで展開されているなじみの薄いやり方や考え方を自ら体験することで、「あたりまえ」を見つめ直す。それは、「自分や人間、文化、世界を考えるための拠りどころ」になる。
異文化に参加し、考えること

異文化を研究対象とする調査方法は徐々に整備され、画期的な発見につながっていった。
未知の世界に出ていく「フィールドワーク」の確立には、ブラニスラウ・マリノフスキが決定的な役割を果たしている。オーストラリアでの調査中に第一次世界大戦が勃発して長期滞在することになったことを契機として、現地の言葉を覚えながらその生活に浸ることで、その社会の全貌を「内側」から解明しようとしたのだ。この調査経験は、ある文化・社会の全体像がわかるように体系的に記述された「民族誌(エスノグラフィー)」として発表された。
このように、「調査者が現地の人びとの日常の出来事に参加しつつ、他方でその観察データを記録するというかたち」を「参与観察」と呼ぶ。
文化人類学は、19世紀には植民地主義と深く結びつき、西洋が最も進歩した文明と捉えていた「文化進化論」に基づいていた。マリノフスキ以降のフィールドワークと民族誌という手法は、異文化を同じ地平に置き、その内部へ分け入っていくような視点を与えた。「いずれの文化もそれぞれ固有の価値を有している」ことを認める「文化相対主義」に移行したのである。
性とは何か
生物繁栄のかたちの多様性
人類学は、生物としてのヒト、文化的な存在としての人間の両者をカバーして、「人間というものを全体的に考える学問」として始まっている。性とは、まさにそうしたテーマの問題である。
生物の性は多様だ。たとえばヒドラは、池が干上がるなど環境が悪くなると、種として生き延びる確率を高めるために無性生殖を有性生殖に切り替える。カタツムリやフジツボは雌雄同体の性を持つ。
配偶者の獲得をめぐる同性同士の競争も様々だ。ゾウアザラシやアカシカのように体格と体力で優れるものが勝つ「正直な闘争」もあれば、繁殖行動が始まる前にカップルの後ろから自分の精子を撒き散らして受精させるイモリの仲間のような「スニーカー戦略」もある。
文化的な性の多様性

人間は、生物進化的な側面から大きく逸脱して、多様な性の文化を開花させてきたと言えそうだ。
たとえばベネズエラのバリ社会では、父親、父性は「分割」されるものとされる。ある父親は自分の子どもだけでなく他の子どもに対しても父として振る舞い、子どもには複数の父親がいることになる。