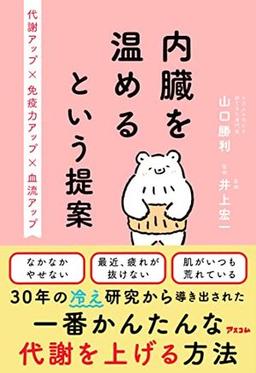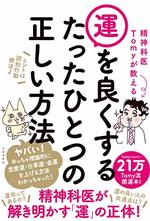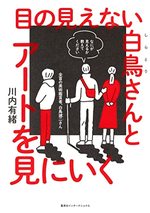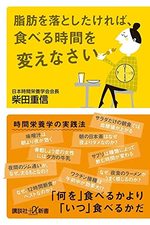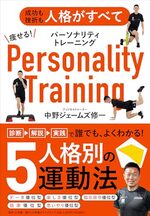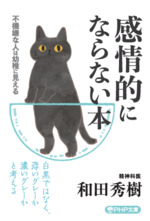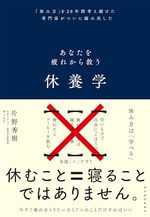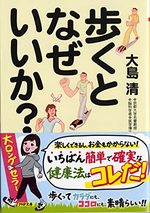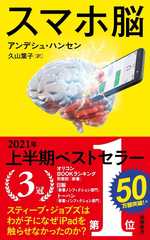私たちの臓器は冷え切っている
ポストコロナの「内臓の氷河期」
2020年初頭から猛威を振るった新型コロナウイルス。外出自粛、長時間のマスク着用、リモートワークなど、私たちは新たな生活スタイルを強いられた。この期間、著者・山口氏のクリニックには冷え性をはじめ、原因不明の頭痛、肩こり、肌荒れなど、さまざまな不調を訴える人が以前よりも多く来院するようになった。新型コロナウイルスは「コロナ負債」ともいえる大きなダメージを、私たちの体に残したようだ。
このダメージとは、主に次の3つである。
まず、運動不足による筋力の量と質の低下だ。血液を全身に運ぶ役目をする筋肉が減ると、血流が悪くなり内臓は冷えやすくなる。
次に、生活環境の変化からくる自律神経の乱れだ。血流をコントロールしている自律神経が乱れると、内臓に適切な熱が運ばれなくなって内臓が冷えてしまう。
そして最後は、体型の変化である。コロナ禍の運動不足やストレスに伴う肥満化。人間は1キロ体重が増えると、毛細血管が1500メートル長くなるという。つまり、毛細血管が長くなった分、全体的な血流は悪くなり内臓の冷えにつながり得る。
さらに、慣れない環境での長時間のリモートワークで、骨格が歪んでしまった人も多い。骨格が歪んで血管が圧迫され、血流の悪さや自律神経が乱れにつながることもある。
冷え性の2つのタイプ

冷え性というと、「手足が冷たいこと」と思う人は多いだろう。しかし、冷え性には2つのタイプがある。血管が広がるタイプと縮まるタイプが混在しているのだ。
冷え性の7割は、手足が冷たい「血管収縮型冷え性」である。このタイプは、室内にいても手足や足先が冷える、寒い時期に症状が出る、主に下半身が冷える、手足がむくむ、肩こり・腰痛・便秘・生理痛が気になるといった特徴がある。
この冷え性の原因は、基礎代謝の低下や自律神経の乱れによって、血液が手足の末端まで届かないことにある。手足の温度が低い人は内臓温度も低い。健康な人の理想的な内臓温度は、体表面温度よりも1〜2℃高い37.2~38℃くらいだとされる。