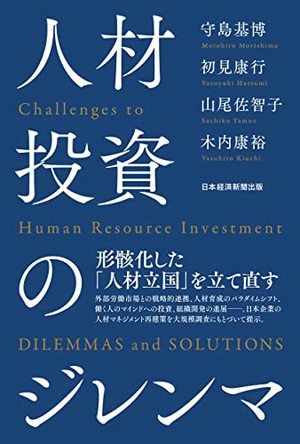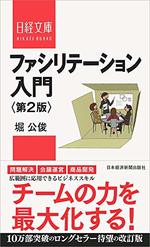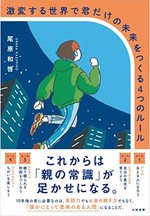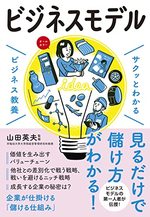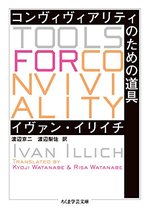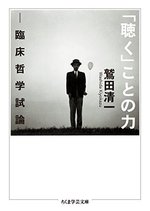人材投資のジレンマ
著者
守島基博(もりしま もとひろ)
学習院大学経済学部経営学科教授、一橋大学名誉教授
1986年米国イリノイ大学産業労使関係研究所 博士課程修了。人的資源管理論でPh.D.を取得後、カナダ国サイモン・フレーザー大学経営学部Assistant Professor。慶應大学総合政策学部助教授、同大大学院経営管理研究科助教授・教授、一橋大学大学院商学研究科教授を経て、2017年より現職。厚生労働省労働政策審議会委員、中央労働委員会公益委員などを兼任。2020年より一橋大学名誉教授。主な著書に『人材マネジメント入門』『人材の複雑方程式』『全員戦力化 戦略人材不足と組織力開発』(以上、日本経済新聞出版)、『人事と法の対話』(共著、有斐閣)などがある。
初見康行(はつみ やすゆき)
多摩大学経営情報学部准教授
同志社大学文学部卒業。株式会社リクルートHRマーケティングにて法人営業、人事業務に従事。一橋大学大学院商学研究科博士後期課程単位取得退学。2017年一橋大学博士(商学)。いわき明星大学(現:医療創生大学)准教授を経て、18年より現職。専門は人的資源管理。主な著書に『若年者の早期離職』(中央経済社)などがある。
山尾佐智子(やまお さちこ)
慶應義塾大学大学院経営管理研究科准教授
津田塾大学国際関係学科卒。神戸大学大学院国際協力研究科(経済学)、英国マンチェスター大学ビジネススクール(国際経営論)の修士課程を経て、豪州モナッシュ大学にて経営学Ph.D.を取得。2009年豪州メルボルン大学レクチャラー、16年同大学シニアレクチャラー。17年より現職。専門は国際人的資源管理論。主な論文に「グローバル人材とそのマネジメント――国際人的資源管理研究から得られる知見」『一橋ビジネスレビュー』2021年夏号(東洋経済新報社)などがある。
木内康裕(きうち やすひろ)
公益財団法人日本生産性本部 生産性総合研究センター上席研究員
立教大学大学院経済学研究科修了。政府系金融機関勤務を経て、日本生産性本部入職。生産性に関する統計作成・経済分析が専門。労働生産性の国際比較分析などのほか、アジア・アフリカ諸国の政府機関などに対する技術支援も行っている。
主な著書に『新時代の高生産性経営』(分担執筆、清文社)、『PX:Productivity Transformation[生産性トランスフォーメーション]』(分担執筆、生産性出版)などがある。
学習院大学経済学部経営学科教授、一橋大学名誉教授
1986年米国イリノイ大学産業労使関係研究所 博士課程修了。人的資源管理論でPh.D.を取得後、カナダ国サイモン・フレーザー大学経営学部Assistant Professor。慶應大学総合政策学部助教授、同大大学院経営管理研究科助教授・教授、一橋大学大学院商学研究科教授を経て、2017年より現職。厚生労働省労働政策審議会委員、中央労働委員会公益委員などを兼任。2020年より一橋大学名誉教授。主な著書に『人材マネジメント入門』『人材の複雑方程式』『全員戦力化 戦略人材不足と組織力開発』(以上、日本経済新聞出版)、『人事と法の対話』(共著、有斐閣)などがある。
初見康行(はつみ やすゆき)
多摩大学経営情報学部准教授
同志社大学文学部卒業。株式会社リクルートHRマーケティングにて法人営業、人事業務に従事。一橋大学大学院商学研究科博士後期課程単位取得退学。2017年一橋大学博士(商学)。いわき明星大学(現:医療創生大学)准教授を経て、18年より現職。専門は人的資源管理。主な著書に『若年者の早期離職』(中央経済社)などがある。
山尾佐智子(やまお さちこ)
慶應義塾大学大学院経営管理研究科准教授
津田塾大学国際関係学科卒。神戸大学大学院国際協力研究科(経済学)、英国マンチェスター大学ビジネススクール(国際経営論)の修士課程を経て、豪州モナッシュ大学にて経営学Ph.D.を取得。2009年豪州メルボルン大学レクチャラー、16年同大学シニアレクチャラー。17年より現職。専門は国際人的資源管理論。主な論文に「グローバル人材とそのマネジメント――国際人的資源管理研究から得られる知見」『一橋ビジネスレビュー』2021年夏号(東洋経済新報社)などがある。
木内康裕(きうち やすひろ)
公益財団法人日本生産性本部 生産性総合研究センター上席研究員
立教大学大学院経済学研究科修了。政府系金融機関勤務を経て、日本生産性本部入職。生産性に関する統計作成・経済分析が専門。労働生産性の国際比較分析などのほか、アジア・アフリカ諸国の政府機関などに対する技術支援も行っている。
主な著書に『新時代の高生産性経営』(分担執筆、清文社)、『PX:Productivity Transformation[生産性トランスフォーメーション]』(分担執筆、生産性出版)などがある。
本書の要点
- 要点1従業員の「マインド面」の状態が、自身の主体的な行動や思考を喚起し、そうした行動や思考によって仕事の生産性が向上する。マインド面の向上には、教育訓練、自己啓発支援、組織開発への投資が有効である。
- 要点2著者たちは、(1)外部労働市場との戦略的連携、(2)人材育成のパラダイムシフト、(3)働く人のマインド面への投資、(4)組織開発の進展、という4つの提言をしている。
要約
今、私たちは人材投資の転換点にいる
外部調達と内部育成のジレンマ
労働人口の減少、経営戦略の変化、人々の価値観の変化。現在は、経営を取り巻く環境が大きく変化しており、企業は人材マネジメントを再考するよう迫られている。それにより、いくつかの変化とジレンマが起こりつつある。
1つめの変化は、外部労働市場に開かれた人材マネジメントの積極的活用だ。近年、人材獲得の方法として、外部労働市場からの採用が重視されるようになってきた。外部からある程度育成された人材を確保した方が、時間的に大きな節約となる。一方で、それはリスクも伴う。採用した人材が期待通りのパフォーマンスを出してくれるか、長期的にその企業に残ってくれるかといったことだ。今後は、人事部門が外部と内部の効果的なポートフォリオを組む必要がある。
また、日本企業は、賃金や処遇の内部公平性と外部公平性の問題にも直面している。内部公平性とは、賃金などが企業内部の他の従業員と比較して公平なものになっているかの判断である。これに対し、外部公平性とは、外部企業の同様の従業員と比較しての公平性を意味する。労働市場における相場との比較といってもよい。
これまで日本の人事では、内部公平性を保つことで、従業員の納得性とエンゲージメントを保ってきた。だが、他社の賃金や待遇などの情報は、ネットなどを通じて容易に手に入るようになっている。そこで、外部労働市場の相場と比べて公平感を持てるような賃金設定が、人材のリテンションにおいて重要となっているのだ。
企業内での人材多様性の増加

Ada daSilva/gettyimages
2つ目の変化は、企業内での人材多様性の増加である。外部労働市場からの採用が増えると、能力や知識、経験値などの多様性、つまりタスク型の人材多様性が増していく。結果的に、そうした人材の能力開発ニーズに応じて、人材育成はより多様化、個別化していくだろう。

この続きを見るには...
残り3431/4207文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2023.06.10
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約