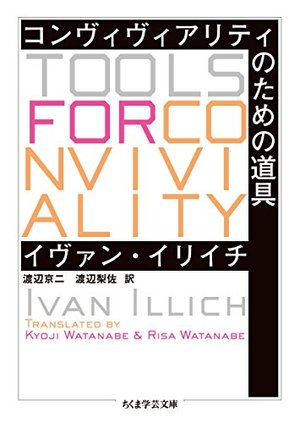コンヴィヴィアリティのための道具
著者
イヴァン・イリイチ(Ivan Illich)
1926‐2002年。ウィーン生まれの思想家。ヴァチカン・グレゴリオ大学で神学と哲学を学び、カトリック司祭として活動。1969年、ローマ・カトリック教会との軋轢により還俗し、以後、学校・病院制度に代表される産業社会への批判を展開。その議論は、教育、医療、エコロジー運動、コンピュータ技術など、多分野に影響を与えた。著書に『脱学校の社会』『シャドウ・ワーク』『生きる希望』などがある。
1926‐2002年。ウィーン生まれの思想家。ヴァチカン・グレゴリオ大学で神学と哲学を学び、カトリック司祭として活動。1969年、ローマ・カトリック教会との軋轢により還俗し、以後、学校・病院制度に代表される産業社会への批判を展開。その議論は、教育、医療、エコロジー運動、コンピュータ技術など、多分野に影響を与えた。著書に『脱学校の社会』『シャドウ・ワーク』『生きる希望』などがある。
本書の要点
- 要点1産業主義が単に商品だけではなく、産業主義的な様式で「サービス」を生産するようになると、均衡が失われ、産業に支配された社会に近づく。
- 要点2産業主義的な進化の過程には「二つの分水嶺」が存在している。第二の分水嶺を超える頃には技術的進化の限界効用が低下し、限界非効用が大多数の人々の苦痛の指標となってしまう。
- 要点3自立共生的な道具とは、「それを用いる各人に、おのれの想像力の結果として環境をゆたかなものにする最大の機会を与える道具」のことである。
要約
コンヴィヴィアリティとは何か
道具に隷属する人間

PeopleImages/gettyimages
著者は、1970年頃から数年にわたって「産業主義時代の終焉」というテーマに取り組んでいた。
産業主義的な生産様式を批判し、その替わりとなる生産様式を規定するにあたり、まず教育制度に着目した。大衆教育の生産と市場商品化による強制的な「学校化」を分析した結果、教育の大量生産は、サービス商品、公益事業などほかの産業に属する企業のあり方にも影響を及ぼしていることがわかった。就業者と消費者を潜在的に条件づけし、社会を管理しやすいものにして、基本的な諸価値を破壊してしまう。
わかりやすい事例は、専門家が管理したものに限って強制加入させられる健康保険制度や、交通がある一定速度に強制的に制限される公共輸送システムである。人工的製品と同様に、サービス部門にも生産の限界値が避けがたく存在するということであり、それは産業主義的成長にも限界を設定するのだ。まずは、そのうまい限界値を見極めることが必要である。
そこで、人間と(産業主義の結果もたらされた)道具との関係を評価するために、「人間生活の多元的均衡」という概念を著者は提唱する。自然な成長規模を確定するためだ。
大量生産による限度なき成長は、機能の専門化・価値の制度化・権力の集中をもたらし、人間を官僚制や機械(道具)に隷属させてしまう。一方で「人間生活の多元的均衡」が守られた、産業に支配されていない社会では、人間の「能力と管理と自発性」が発揮しやすい社会となる。
道具が責任を持って限界づけられ、政治的に相互に結びついた個人とともに新しい共同性の中にある現代社会を、著者は「自立共生的(コンヴィヴィアル)」と呼んでいる。ここには、現代スペイン語の「節制ある楽しみ(エウトラペリア)」という意味合いが意図されている。この「節制(節度)」とは、トマス・アクィナスが述べるように、「人格的な結びつきから気をそらせたり、それに対して破壊的であったりする楽しみだけを排除するような徳性」を指す。
二つの分水嶺
産業主義が社会に及ぼす影響
産業主義的な進化の過程には「二つの分水嶺」が存在している。最初の分水嶺では科学的根拠に基づいて新しい知識が特定の問題を解決する。第二の分水嶺を超えると、進歩それ自体が、限られた専門職エリートによって定義される価値のサービスという形をとって、社会を搾取する理論的根拠になる。
たとえば、医学の進歩は、以前は「天罰」と思われていたようなことの原因の見直しから行われた。水の浄化は幼児死亡率を低下させ、ねずみの駆除はペストを無力化した。これらは公衆衛生、農業、商品販売、生活態度の変化のおかげであり、医者の介入によるものはごくまれであった。
西欧化に伴い、医師という専門職による「定義された効果的な治療」への要求は強まっていく。1913年あたりから患者は、専門の資格を持った医師から専門的治療をうける機会が50パーセントを超えるようになった。これが、第一の分水嶺である。それ以降医師は治療手段の適用を独占し、あらゆる人がますます医師に依存していく。

この続きを見るには...
残り3340/4614文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2023.06.15
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約