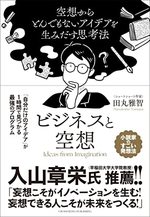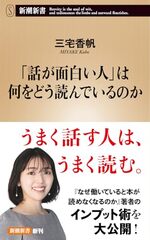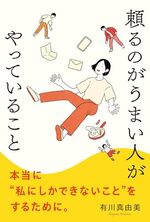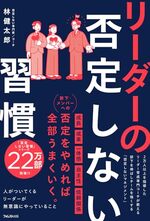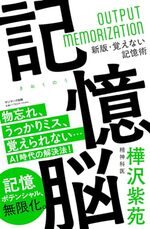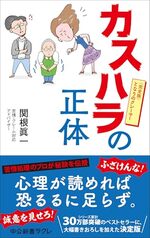自己肯定感
非認知能力とは
本書は、私たちの思考のくせに気づき、機能する思考と行動の新習慣に書き換えることを目指す。
これからの時代に必要なのは、自己肯定感、自分軸、成功体質、主体性、オープンマインド、共感力などを総称した「非認知能力」である。非認知能力は、従来のテストの点数などの目に見える能力とは異なる「目に見えない能力」であり、「生きる力」である。
非認知能力を身につけることは、自分という存在を無条件に認め、感情をコントロールし、多様なバックグラウンドを持つ人たちと良好な関係を築く術を学ぶことにつながる。本書の各章は、コーチングの4ステップ、すなわち「気づき→肯定→決断→行動」のステップに沿って書かれている。
気づきは自分のキャリア構築を妨げる思考のくせに気づくことを促す。次に、機能していない思考のくせがある自分を否定せず、「そういう自分も自分」と肯定する。続いて求める結果を決め、最後にその決断を可能にする行動を選択し、思考と習慣を書き換えていく。
本書での行動は、「視点を変える」ことと「視点を増やす」ことが基本となる。これまでどおりにやっていて結果が出ない場合は、物事を別の視点から見る「リフレーミング」と、見方を多様化することが求められる。
非認知能力の要・自己肯定感
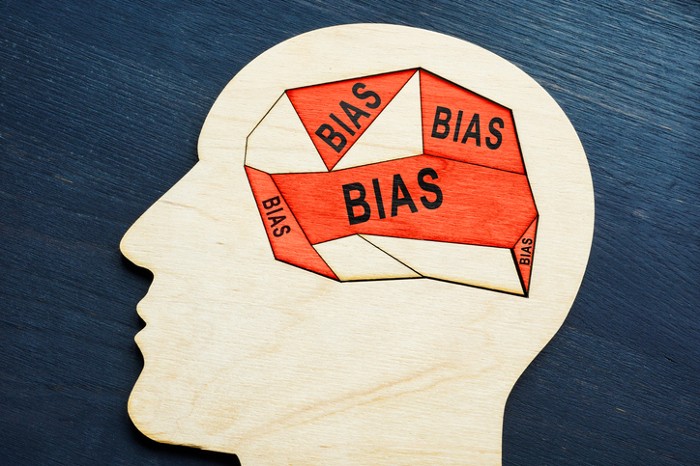
自分はダメだ、どうせ無理と言った言葉がつい出てきてしまう人は「自己肯定感」を身につけることが必要だ。
著者は、自己肯定感を非認知能力の要だとしている。全ては自分を大切にして、あるがままの自分に価値を認めることから始まる。
日本は、2014年に内閣府が実施した7カ国を対象とした調査で、「自分に誇りを持っているか」「自分に長所はあるか」など全ての質問の回答で、平均を下回った。
また、自己肯定感は年齢を重ねるごとに低まるそうだ。人間は、1日に6万もの思考をする中で、8割がネガティブなものとされる。これを「ネガティブ・バイアス」という。私たちが成長するにつれて経験した失敗や失望は、ネガティブ・バイアスによって強く記憶に残る。こうすると、成功した経験は忘れたり見逃したりするため、「ダメな自分」が出来上がってしまう。
自己肯定感を下げるもう一つの要因に、比較がある。比較もまた、本能的に行ってしまうものである。
思考のくせを書き換える
ネガティブ・バイアスのせいでダメなところに目が行きがちになるが、あえてポジティブなところに目を向けるよう心がけたい。「足りない、まだダメだ」という意識から、「満ちているところもある」と思考するよう習慣化するのである。
ポジティブ探しには、「誰かに感謝された」「素敵な本を見つけた」といったどんな小さなことでも見逃さないのがコツである。こうしたことを見つけていくと、自分の思考は自然とポジティブに向かうようになる。
私たちは、良い子でないと価値がないわけではない。今ここに生きて存在していることにこそ価値があるのだ。誰かに褒められた時に自己肯定感が上がるのは、自己肯定感のコントロールを他者に委ねている状態である。
それをやめ、自分の存在価値を自分のコントロール下におく。このために有効なスキルが「セルフ・コンパッション」である。具体的には、寝る前に今日の自分にいたわりや感謝の言葉をかけるだけである。この習慣は、自分を慈しむことが、自分を前に進める大きな原動力となる。
そして比較してしまう自分に対して、自分の弱みと相手の強みを比較するのではなく、自分の成長のために比較することが有効だ。

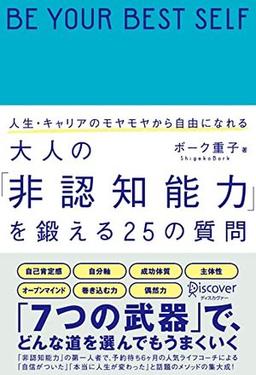

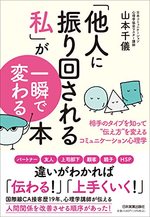

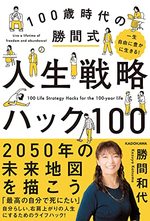
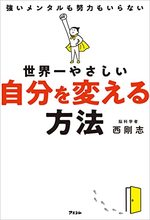

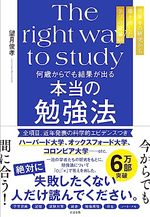
![[新装版]成功への情熱](https://fd-flier-static-prod-endpoint-b6g9b5dkedfkeqcc.a03.azurefd.net/summary/3459_cover_150.jpg)