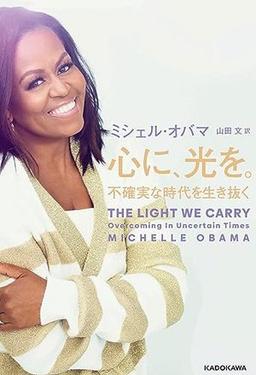大きなもののための、小さなこと
8年の重圧
アメリカ合衆国の「ファーストレディ」としての8年間は慎重に過ごす期間だった。歴史上、「白人の家(ホワイトハウス)」だった場所にはじめて入る黒人として、失敗は許されないし、何か意義のある変化を起こさなければならなかった。二人の娘たちを守り、世界規模の重責を背負うバラクを支える必要もある。良くも悪くも「アメリカの象徴」になることは避けなければならない。一つ一つの決断に、並々ならぬ熟慮を要した。その旅のすべてを吐き出したのが前著『マイ・ストーリー』だった。
その後のさまざまな混乱や不確かな状況、不公平さの体験も含めて、著者が不安に苛まれながらも前に進み続けられているのはなぜか。その光を見つけ出そうというのが本書である。
忙しいという鎧

数々の責任に包まれたホワイトハウスでの8年は、忙しさの利点に気づかせてくれた。能率化された組織は遅れを許さず、否定的なことを考える暇を与えない。忙しさという「道具」は視野を広くさせ、鎧となって思考を楽観的に保ってくれた。他人からの矢を意識する時間もないのだから。
パンデミックは最初の数カ月でそうした状況も変えてしまった。未来は不透明になり、まるで嵐の中にいるように、方向感覚と、鎧の一部を失った。不安と孤立に苛まれ、胸にしまいこんでいたさまざまな葛藤が鎌首をもたげた。ついには、ドナルド・トランプを大統領に選んだことからアメリカ国民は何を得ようとしたのか、という疑念へと立ち戻った。
バラクと著者は、「いつでも希望と努力を原則として動こうとしていた」。ほとんどの人が共通の目的を分かちあい、物事は少しずつ進歩できると信じていた。ホワイトハウスにたどり着くまでの道のりで、同じ志を抱いているであろう何百万人ものアメリカ人に出会った。黒人である著者たちがホワイトハウスにいるという現実を胸に、よりいっそうの希望を持ち、努力し、可能性のなかに身を置こうとした。
だから、2016年のアメリカ大統領選挙の結果は、いまだにつらい。トランプはあからさまに人種差別的な中傷発言を繰り返し、わがままと憎悪を蔓延らせた。他者とのちがいを脅威であるかのように語る言説は衝撃的だった。それは「単なる政治的な敗北」にとどまらない。パンデミックに至ってその挫折を振り返っても、何の理屈も描けなかった。希望はぼんやりと遠ざかり、途方もない無力感に呑み込まれそうになっていた。
大きな問題と小さな編み物
こうした時、手に取ったのが編み針だった。YouTubeで見つけた解説動画を真似してみる。そうして集中していると、心がほんの少し楽になった。これまでは頭が手も含めた体のすべてを管理していると思い込んでいた。編み物はそれを逆転させて、手の動きが安心感を与えてくれる。小さく正確な動き、規則的な針のリズムが、頭を新しい方向へと動かしていく。
ブラック・ライヴズ・マターの活動に携わる人やエッセンシャルワーカーのように、より良き未来を手繰り寄せようとする人々の姿を思い、そうした人たちの投票によって新しいリーダーを生み出せる希望も視界に戻ってきた。そして、悲しみと挫折の果てに、「適応し、変化を起こして、乗り越える力がわたしたちにはあるという信念」を探り当てることができた。
編み物は、差別にも、ウィルスにも、うつ病にも、気候変動にも勝てないだろう。破壊された社会、自然の大きさに対して編み物はあまりにも小さすぎる。けれども、途方もなく大きな壁を感じたとき、それへの恐怖で頭がいっぱいになって立ち往生したとき、「小さなものを目指せばいい」と学んだ。
手におえない状況に立ちすくんだ時は、あえて小さなものへと進んでみる。受け身ではなく能動的に、頭と体を使う何かを見つける。そうして大きな壁から一時的に逃げる自分を、許してあげてほしい。
ちがうことへの不安
不安に対処するということ

著者はアメリカで暮らす黒人、家父長制の世界に生きる女性である。公人として批判や評価にさらされるし、憎悪の標的となることもある。新しい何かにチャレンジするとき、人前で意見を述べるときには勇気を出さなくてはならない。誰もがそうした抽象的な不安と向き合っている。