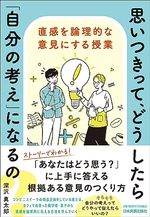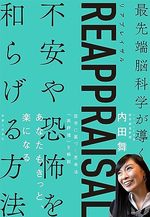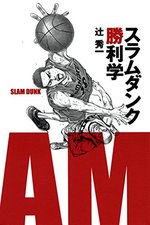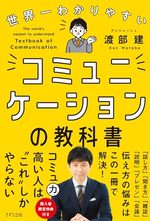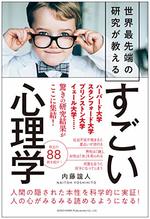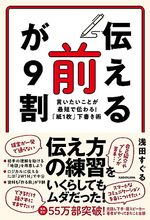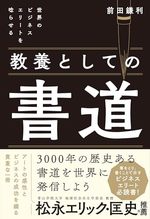訂正する力
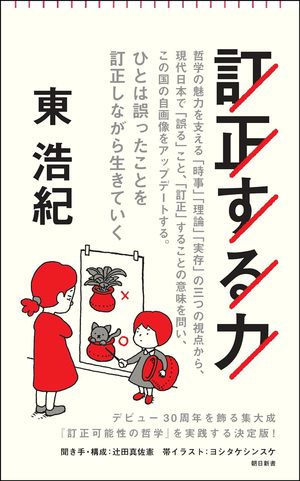
訂正する力
著者
著者
東浩紀(あずま ひろき)
1971年生まれ。批評家。東京大学大学院博士課程修了。株式会社ゲンロン創業者。『存在論的、郵便的』(98年)でサントリー学芸賞、『クォンタム・ファミリーズ』(2009年)で三島由紀夫賞、『弱いつながり』(14年)で紀伊國屋じんぶん大賞、『観光客の哲学』(17年)で毎日出版文化賞を受賞。ほか主な著書に『動物化するポストモダン』『一般意志2.0』『ゆるく考える』『ゲンロン戦記』『訂正可能性の哲学』などがある。
1971年生まれ。批評家。東京大学大学院博士課程修了。株式会社ゲンロン創業者。『存在論的、郵便的』(98年)でサントリー学芸賞、『クォンタム・ファミリーズ』(2009年)で三島由紀夫賞、『弱いつながり』(14年)で紀伊國屋じんぶん大賞、『観光客の哲学』(17年)で毎日出版文化賞を受賞。ほか主な著書に『動物化するポストモダン』『一般意志2.0』『ゆるく考える』『ゲンロン戦記』『訂正可能性の哲学』などがある。
本書の要点
- 要点1「訂正する力」とは、単に誤りを認めて正すのではなく、一貫性を持ちながらも変化していく力のことである。
- 要点2現代日本では空気の力が強い。単なる批判は、批判という空気をつくるに留まってしまう。必要なのは「これこそが本当のルールだったのだ」と主張しながら一貫性を守り、少しずつルールを変えていくことで気がつけば変化が起きている、といった「訂正」の営みである。
- 要点3「訂正の力」の核心は「じつは……だった」という発見の感覚にある。これはAIにも代替できない、人間らしい感覚だ。
要約
なぜ訂正する力は必要か
壊れた「議論」をつなぎ直す
日本にいま必要なのは「訂正する力」である。
日本は、政治が変わらず経済も沈んだままで、行き詰まっている。「大胆な改革が必要だ」とメディアは叫ぶが、何も進展してはいない。
もし日本が変わるとしたら、そこで必要なのは「トップダウンによる派手な改革ではなく、ひとりひとりがそれぞれの現場で現状を少しずつ変えていくような地道な努力」だろう。そういった小さな変革を後押しするためには、蓄積されてきた過去を「再解釈」し、現在に蘇らせるための哲学が必要だ。本書が言う「訂正する力」とは、そうして「現在と過去をつなぎなおす力」のことだ。
日本には「変化=訂正を嫌う文化」がある。政治家は謝らず、官僚はまちがいを認めない。決定された計画を変更しようとしない。ネットでは過去の発言と矛盾すると炎上する。異なる立場の人たちが対話によって少しずつ意見を変えていくこともできず、政治的な議論が成立しなくなっている。だからこそ、「まちがいを認めて改めるという『訂正する力』」が必要なのだ。
「空気」は訂正できるか

gremlin/gettyimages
訂正するとは、「一貫性を持ちながら変わっていくこと」だ。これは決して難しいことではなく、我々が日常的に行っていることである。
ヨーロッパの人々は、訂正がうまい。新型コロナウイルスの感染拡大で、イギリスは大規模なロックダウンをしたが、事態が収まってくると、最初から大したことがないと気づいていた、と言わんばかりにマスクを外していった。ヨーロッパの国々は、ルールを容赦なく変えて自分たちに有利な状況をつくり出しながらも、一方で行動や指針が一貫して見えるように一定の理屈を立ててもいる。そういった「ごまかしをすることで持続しつつ訂正していく」のが、「ヨーロッパ的な知性のあり方」なのだ。本来は日本もこうしたしたたかさを持っていたはずだが、それが失われてしまっている現状がある。
では、「どうすれば訂正する力を取り戻すことができる」のだろうか。現代日本では、社会の無意識的なルール、すなわち「空気」がつねに障害となっている。個人が他人を気にするだけでなく、その他人自身もまた他の人の目を気にするという厄介な入れ子構造をもつ。そうして相互に監視するなかで、「だれもが社会の無意識なルールにしたがってしまう」。空気の変化の切れ目はだれにもわからないし、コントロールもできない。空気を批判しようとしても、その批判そのものが空気になり、しまいにはそうした「新たな問題提起に考えなしに追随するひとが現れてしまう」。極めて厄介な構造である。
脱構築しか有効ではない
こうした空気は、「変えましょう」といってもそれが新たな空気になるだけだ。だから、その空気のなかにいながらにして、「いつのまにか変わる」ように仕向けるしかない。そうしたアクロバティックなことを成し遂げるための道具が「訂正する力」なのだ。
これは、フランスの哲学者、ジャック・デリダが唱えた「脱構築」に似ている。表面上は伝統的なルールに従っているように見せながら、そのルールを突き詰めて考えることで、西洋的な哲学の型を根本的に変えてしまう。そうした脱構築的な手法しか、日本に対して有効な手立てはないかもしれない。
水面下でルールを訂正しながら、「いや、むしろこっちこそ本当のルールだったんですよ」と主張する。そうして、「現在の状況に対応しながら過去との一貫性も守る」という「両面戦略が不可欠」なのだ。
【必読ポイント!】 「じつは……だった」のダイナミズム
訂正は日常的にやっている
そもそも訂正とはなんだろうか。「訂正の本質はある種の『メタ意識』にある」。無意識的な自分の行いに対して、違和感を覚えたりするときに「訂正の契機」は生まれる。

この続きを見るには...
残り2874/4419文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2024.03.02
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.Copyright © 2024 東浩紀 All Rights Reserved. 本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権は東浩紀、株式会社フライヤーに帰属し、事前に東浩紀、株式会社フライヤーへの書面による承諾を得ることなく本資料の活用、およびその複製物に修正・加工することは堅く禁じられています。また、本資料およびその複製物を送信、複製および配布・譲渡することは堅く禁じられています。
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.Copyright © 2024 東浩紀 All Rights Reserved. 本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権は東浩紀、株式会社フライヤーに帰属し、事前に東浩紀、株式会社フライヤーへの書面による承諾を得ることなく本資料の活用、およびその複製物に修正・加工することは堅く禁じられています。また、本資料およびその複製物を送信、複製および配布・譲渡することは堅く禁じられています。
一緒に読まれている要約