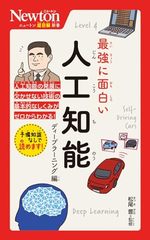人を導く最強の教え『易経』
「人生の問題」が解決する64の法則

著者
小椋浩一(おぐら こういち)
1965年名古屋生まれ。易経研究家。某電機メーカー経営企画部プロジェクト・マネジャー。名古屋大学大学院経営学博士課程前期修了。People Trees合同会社パートナー、NPO日本ファシリテーション協会会員などの副業も通じ、広く人材開発に取り組む。早稲田大学商学部卒業後、上記電機メーカーに入社。経営企画、人事を経てマレーシア工場財務部長に。新会社や工場の設立を進め、生産規模を大きく拡大。帰国後は事業部の「従業員満足度」を連続向上させ、会社を「働きがいのある会社ベスト20」に導く。しかしキャリアの絶頂期に新規事業で大損失を出し、居場所を失う。絶望のなか、『易経』研究家の竹村亞希子氏と出会い、人生観が180度変わる。現在、本業では全社横串の次世代リーダー育成を任され、自主参加勉強会は年間1000人規模を超え、社外からも講演・セミナー依頼が急増中。なかでも高校生向け「社会人とは/高校生の今やるべきこととは」出前講演には教師の参加も増え、2023年には1000人、15年間通算では6000人を超え、1年先まで予約が入っている。
1965年名古屋生まれ。易経研究家。某電機メーカー経営企画部プロジェクト・マネジャー。名古屋大学大学院経営学博士課程前期修了。People Trees合同会社パートナー、NPO日本ファシリテーション協会会員などの副業も通じ、広く人材開発に取り組む。早稲田大学商学部卒業後、上記電機メーカーに入社。経営企画、人事を経てマレーシア工場財務部長に。新会社や工場の設立を進め、生産規模を大きく拡大。帰国後は事業部の「従業員満足度」を連続向上させ、会社を「働きがいのある会社ベスト20」に導く。しかしキャリアの絶頂期に新規事業で大損失を出し、居場所を失う。絶望のなか、『易経』研究家の竹村亞希子氏と出会い、人生観が180度変わる。現在、本業では全社横串の次世代リーダー育成を任され、自主参加勉強会は年間1000人規模を超え、社外からも講演・セミナー依頼が急増中。なかでも高校生向け「社会人とは/高校生の今やるべきこととは」出前講演には教師の参加も増え、2023年には1000人、15年間通算では6000人を超え、1年先まで予約が入っている。
本書の要点
- 要点1『易経』とは世界を二進法によって分類・整理しようとした試みであり、長らく偉人や経営者に親しまれてきた。
- 要点2『易経』は「自分の未熟さを知ること」「あえて進まずに待つこと」「覚悟を持って決断すること」などの大切さを教えてくれる。
要約
多くの偉人たちが学んだ理由
経営者や偉人を虜にした『易経』
『易経』を理解することで、「運などに左右されない、『ブレない判断軸』を持つこと」ができるという。つらい時期でも上機嫌でいられるし、部下や後輩などまわりの人から頼られる存在にもなれる。
実際、多くの経営者の本棚には『易経』が置いてある。組織のトップには、人事や事業買収など誰にも相談できない案件もあり、『易経』を決断の軸にしているのかもしれない。
現代のリーダーだけでなく歴史上の偉人たちも『易経』に学びを求めてきた。室町時代初期に創設された足利学校では、当時の知識人の多くが学んでいる。そうした人たちが、戦国時代の「軍師」として活躍した。
特徴は二進法にあり

aluxum/gettyimages
『易経』は、「いかに生きるか。われわれの生きるこの世界はどのようなものなのか」という難問に挑んでいる。安易な気持ちでは踏破し得ない、まるで巨山のようなものだ。
孔子などによる解説も含めて漢字の多義性がそのまま残されており、そもそも解読が難しい。「この世界のすべてから学べ。とくに目前の自然から学べ」という教えがあまりに深い、「東洋最古の書」ともされる。
今で言う百科事典のような性格を持ち、「陽」と「陰」の二進法ですべてを分類しようとしたその体系には、物理学者も魅了されるそうだ。時間、季節や暦、方角など、多くのものを細かく二進法で整理している。
その二進法には、哲学的なアプローチもある。物事の根本を「太極」とし、「陽と陰」の二種類の局面によって、内面の好不調や外部環境の幸運・不運など、人生のあらゆるものを説明できるようにしてきた。これがいわゆる「六四卦」である。ただ、同じ話がまったく異なる文脈で使われるなど、合理的な体系として捉えにくい形式になっているため、その理解は容易なことではない。
このような特徴は、「図形の全体をいくつかの部分に分解していった時に、全体と同じかたちが再現されていく構造」を指す「フラクタル」になぞらえられている。つまり「個が全体と同じ」かつ「全体が個と同じ」なのだ。したがって、部分的にわからないところがあれば、あえて全体を見渡してみると理解が進むだろう。そうしてフラクタルの「基本形」を押さえることができれば、「いかに生きるか」という自分の軸も見えてくるに違いない。
『易経』でもっと成長する
水火既済(すいかきせい)――過剰適合のリスク
『易経』では、この世の終わりが想定されていない。世界が常に変化する「循環論」に立脚している。だから、ある環境では最適なものであっても、環境の変化によってズレていく。これは、ビジネスにおける「過剰適合」のリスクだ。たとえば、レコードがCDに置き換わったとき、いかに優れたものであっても、レコード針は売れなくなった。変化に対応できる人間は成長できると『易経』は説く。
つまり、「終わり良ければすべて良し」ではないということだ。仕事をやり遂げた達成感は、すぐに欲へと変貌する。「もっと良い仕事があるのではないか」「もっと待遇の良い会社があるのではないか」という考えは戒められる。完成はすでに過去のものであり、「心は常に未完成でいる」ことの大事さを説いているのだ。
風天小畜(ふうてんしょうちく)――苦境こそ忍耐強くあるべき
「蜜雲雨降らず」というたとえ話がある。農家が待望する雨を降らせるはずの厚い雲があるのに、雨が降らない状態を指す。このような停滞したときにこそ、思わぬ本音が出る。

この続きを見るには...
残り2515/3937文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2024.02.23
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約