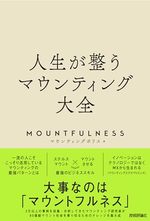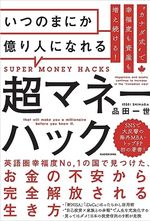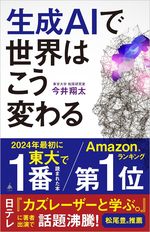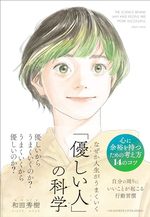科学的根拠に基づく最高の勉強法

科学的根拠に基づく最高の勉強法
著者

著者
安川康介(やすかわ こうすけ)
2007年慶應義塾大学医学部卒。
日本赤十字社医療センターにて初期研修後、渡米。米国ミネソタ大学医学部内科研修、テキサス州ベイラー医科大学感染症研修修了。米国内科専門医・米国感染症専門医。南フロリダ大学医学部助教。
2007年慶應義塾大学医学部卒。
日本赤十字社医療センターにて初期研修後、渡米。米国ミネソタ大学医学部内科研修、テキサス州ベイラー医科大学感染症研修修了。米国内科専門医・米国感染症専門医。南フロリダ大学医学部助教。
本書の要点
- 要点1ただ繰り返し読む、書き写す・まとめる、ハイライトするといった従来の勉強法は比較的効果が低い。
- 要点2アクティブリコールと分散学習を組み合わせた学習法が、現代の学習の科学的根拠に基づく、誰でも実践可能で効果の高い方法だ。
- 要点3似ているけれども異なった複数のスキルや勉強のトピックを交互に学習する「インターリービング」や「なぜ?」と問いかける精緻的質問などは科学的に効果が高い勉強法だ。
要約
科学的に効果が高くない勉強法
繰り返し読む(再読)
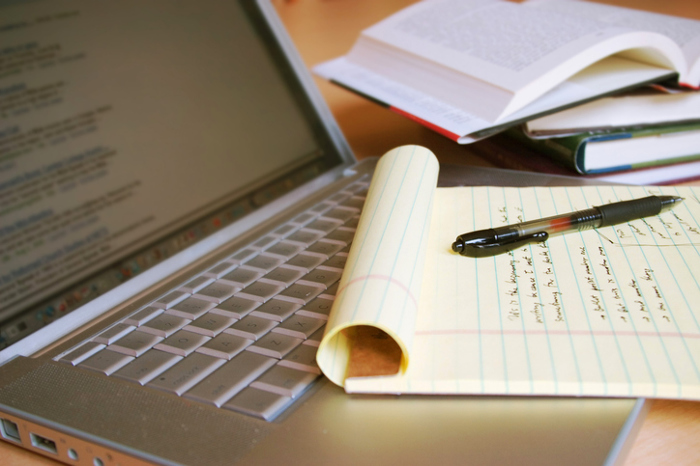
pablohart/gettyimages
本書ではまず「科学的に効果が高くない勉強法」が4つ紹介される。
1つ目は「ただ繰り返し読む(再読)」だ。
今まで行われた再読に関する複数の研究において、再読した学生と1回だけ読んだ学生の成績を比較したところ、再読に大きな学習効果はないことを裏付ける結果がある。なお、「繰り返し読む」の学習効果は、どれくらいの間隔をあけて読むかによって変わる。同じ日に繰り返し読むより、間隔をあけて読むほうが記憶に定着しやすいことがわかっている。
「ただ繰り返し読むこと」に、学習効果があまりないと考えられる一つの理由として、同じ文章を2回目に読む時のほうが、文章に慣れてすらすら読めて「分かった気になってしまう」ので、さらに理解を深めたり覚えたりするといった深い情報処理が新たに行われにくくなることが考えられる。
こうして表面的に情報が処理しやすくなったことで、実際には内容を記憶し深く理解していないのに覚えた気になってしまう、理解した気になってしまう心理的な現象は、「流暢性の錯覚(幻想)」(the Fluency Illusion)と呼ばれている。私たちの脳は、実際にはしっかり記憶したり深く理解したりしていないのに、自分の知識や習熟度を過大評価してしまうことがあるため、気をつけなければならない。
過去の学習に関する膨大な研究をまとめたダンロスキー教授らの報告書でも、「今ある科学的根拠に基づき、再読の有用性は低いと評価する」とまとめられている。
ノートに書き写す・まとめる
2つ目は「ノートに書き写す・まとめる」だ。
教科書や参考書の内容を、綺麗な字でノートに書き写したりまとめたりしているのに、あまり内容を覚えていない、理解していないという人は意外と多いかもしれない。参考書のポイントだと思う箇所や英単語帳から英単語をノートに丁寧に書き写したりまとめたりすることは、それだけで達成感があり、「勉強した気」になってしまう行為だ。
アメリカの高校生180人を対象に、ノー トの取り方についての学習効果を調べたある研究では、文章をそのまま書き写したグループの生徒の成績は、ただ文章を読んだグループの学生の成績と変わらなかった。
内容をノートにまとめることは、そのまま書き写すよりも効果が期待できるものの、要約するのがうまい人とそうでない人では効果が違うことがわかっている。どれくらいの基礎知識があり、どこの部分を重要と判断し、どれくらいの量の情報をどれくらいの文章にまとめるのかなど、要約する能力と要約した情報の質にはかなり個人差があるためだ。学習に関するダンロスキーらによる報告書でも、「今ある科学的根拠に基づき、要約の有用性は低いと評価する」とされている。

この続きを見るには...
残り3247/4405文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2024.05.14
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約