選ばれたものにだけ許される殺人
下見
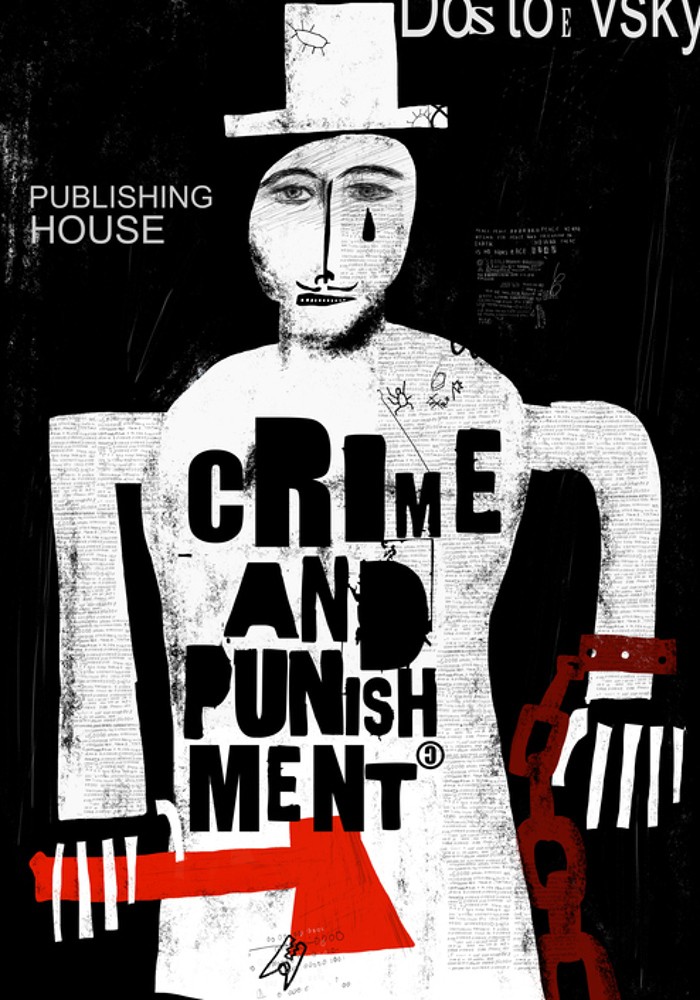
7月の初め、ロジオン・ロマーヌィチ・ラスコーリニコフは下宿を出て、高利貸しの老婆アリョーナ・イワーノヴナのもとを訪れた。一月前に質に入れた指輪の期限はもう過ぎていたが、今度は銀時計をかたに借金をしようとしていた。提示された金額は少なく、利子も天引きされてしまったが、ラスコーリニコフは争わずに金を受け取った。そしてできるだけざっくばらんに「妹さんは留守ですか?」と尋ねた。いぶかしがるアリョーナにまごつきながら、ラスコーリニコフはそこを後にした。
手紙
翌日、ラスコーリニコフは母親からの2ヶ月ぶりの手紙を受け取った。「なつかしいわたしのロージャ(ロジオンの愛称)」から始まる長い手紙は、これまで手紙を書けなかった理由や、その間に起こったことを詳細に伝えていたが、要するにたった一人の妹ドゥーニャが愛のない結婚をすることを決めたという知らせであった。兄である自分には相談もなしに、である。
手紙の内容に息がつまりそうになった彼は、帽子をつかんで外に出た。母からの報告は、息子のために娘を犠牲にするという告白にほかならなかった。ドゥーニャの婚約者であるピョートル・ペトローヴィチ・ルージンは実務家で、善良な人「らしい」。きっと彼がラスコーリニコフの学費を助けてくれるだろうと母娘は期待していた。ラスコーリニコフは学費を滞納して大学を除籍になり、家賃の借金もかさんでいたうえ、勤めにも出ていなかったのである。ルージン氏がこのペテルブルグを訪れる機会に、母娘もラスコーリニコフを訪ねて来る予定だという。だが、ルージン氏は自分の花嫁に駅までの馬車を出してやるつもりも、汽車代を出してやるつもりもないらしい。年金暮らしの母親は娘夫婦とは別居するつもりでいるというが、何を頼りに暮らすつもりなのか。娘婿が自分から支援を申し出てくれるだろうと本気で信じているのだろうか。なぜこの程度のことがわからないのか。
啓示

そうして考えているうちに、ラスコーリニコフの頭にある想念がよぎった。彼はこの想念がひらめくことを予感していた。ただし、これまでと違って、はっきりとした形をもっていたのである。
ある店の前を通りかかったとき、アリョーナと二人暮らしをしている妹リザヴェータを見かけた。リザヴェータは翌日の7時に待ち合わせの約束をしているところだった。つまり、明日の晩7時に、老婆は家に一人きりである。
アリョーナ婆さんのことを教えてくれたのは友人の大学生ポコリョフだった。ついこの冬のこと、ポコリョフがハリコフへ立つ前に、万一質を置くようなことがあったらと住所をくれたのだ。それからしばらく、ラスコーリニコフは何とか暮らしていたが、一月半ばかり前にその住所を思い出した。手元にあった質草になりそうな品は、亡き父から譲られた古い銀時計、妹から別れの記念として贈られた金指輪の2つ。彼は指輪を持って老婆のもとを訪れ、ひと目見たときから抑えきれない嫌悪を感じた。2枚のお札を手にした帰り道、安料理屋で腰をおろすと、すっかり考え込んでしまった。と、奇怪な想念が湧き上がり、彼はたちまちそのとりこになった。
奇妙な偶然であるが、彼の隣りのテーブルでは、見知らぬ大学生が若い将校にアリョーナの話をしていた。大変な金持ちだが、安値しかつかない質草でもいやとは言わない。だから、アリョーナのところに行けばいつでも金が工面できる、と。大学生は、彼女がどんな意地悪で我儘かも語り、話はリザヴェータにもおよんだ。リザヴェータは老婆の腹違いの妹で、年は35。姉のために昼夜なく働き、家事もこなしているようだった。
大学生は熱くなって言い足した。「僕はあのいまいましい婆あを殺して、有金すっかりふんだくっても、誓って良心に恥ずるところはないね」。
ラスコーリニコフはぎくっとした。からからと笑う将校に向かって大学生は続ける。無知で無価値な、意地悪で病身な婆あの命と、社会一般の利益のどちらに意味があるだろうか。あの婆あの金さえあれば、たくさんの事業を成し、多くの人の生活を正しい道に向けられるかもしれない。やつを殺して、やつの金を奪い、その金を使って全人類への奉仕に身をささげる。一個のささいな犯罪は、数千の善事で償えないものか?
もちろん大学生には本当にその計画を実行するつもりはない。これはきわめてありふれた、青年者流の議論である。けれどラスコーリニコフ自身の頭にも、正に同じような思想が生まれたばかりのこの時、こんな意見を聞くことになったのは、一種の宿命、啓示のようであった。




















