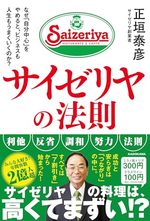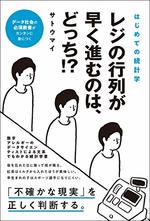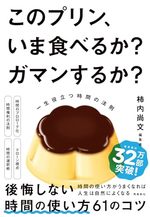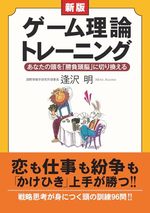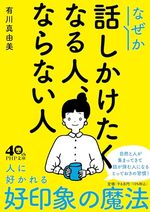タピオカ屋はどこへいったのか?
商売の始め方と儲け方がわかるビジネスのカラクリ
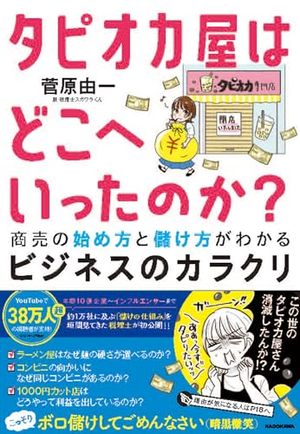
著者
菅原由一(すがわら ゆういち)
1975年三重県生まれ。SMG税理士事務所・代表税理士。高校生の頃はクラスで成績最下位、かろうじて入学した専門学校をドロップアウトするなど、落ちこぼれの青春時代を過ごす。そのあと、記帳や申告業務を淡々とこなす従来の税理士像を覆し、「真の意味で中小企業の経営をサポートする税理士になる」と、決意を新たにする。人よりも3倍の勉強量で税理士試験に打ち込み、20代で税理士資格を取得。現在は、東京・名古屋・大阪・三重に拠点を置き、中小企業の財務コンサルタントとして活躍。銀行が絶賛する独自資料の作成で赤字会社も含め融資実行率は95%以上。顧問先の黒字企業割合は 85%を実現し、全国平均30%を圧倒的に凌ぐ。これまでに全国各地で1000本以上の講演やセミナー講師を務め、1万名超の経営者が受講し、大手企業からの講演依頼が絶えない。YouTubeチャンネル『脱・税理士スガワラくん』は開設わずか1年で登録者数38万人を突破し、TV、専門誌、新聞、各メディアで取り上げられ注目を集めている。「努力と結果は比例する!」を座右の銘として、YouTube、ブログ、SNSで経営のノウハウを毎日配信している。好きな食べものは天津飯。
1975年三重県生まれ。SMG税理士事務所・代表税理士。高校生の頃はクラスで成績最下位、かろうじて入学した専門学校をドロップアウトするなど、落ちこぼれの青春時代を過ごす。そのあと、記帳や申告業務を淡々とこなす従来の税理士像を覆し、「真の意味で中小企業の経営をサポートする税理士になる」と、決意を新たにする。人よりも3倍の勉強量で税理士試験に打ち込み、20代で税理士資格を取得。現在は、東京・名古屋・大阪・三重に拠点を置き、中小企業の財務コンサルタントとして活躍。銀行が絶賛する独自資料の作成で赤字会社も含め融資実行率は95%以上。顧問先の黒字企業割合は 85%を実現し、全国平均30%を圧倒的に凌ぐ。これまでに全国各地で1000本以上の講演やセミナー講師を務め、1万名超の経営者が受講し、大手企業からの講演依頼が絶えない。YouTubeチャンネル『脱・税理士スガワラくん』は開設わずか1年で登録者数38万人を突破し、TV、専門誌、新聞、各メディアで取り上げられ注目を集めている。「努力と結果は比例する!」を座右の銘として、YouTube、ブログ、SNSで経営のノウハウを毎日配信している。好きな食べものは天津飯。
本書の要点
- 要点1消えたタピオカ屋は、次のブームに乗り換え、唐揚げやマリトッツォ、焼き芋の店になった。イニシャルコストを徹底的に抑えて短期で利益を回収し、ブームが去ったらすぐに見切りを付けて撤退するビジネスモデルなのだ。
- 要点2ラーメン屋が油の量や麺の硬さを選ばせるのは、利用者の満足度が高まり、リピートしたい気持ちにつながるためだ。
- 要点3住宅街で1個80円のコロッケを売っている精肉店は、小売とは別の収入源を持っているため、単価が低くても生き残れる。
要約
【必読ポイント!】 タピオカ屋はなぜ流行ったのか?
モノ消費からコト消費へ
社会の変化を捉え、ブームに飛び乗ることは、商売のセオリーだ。2018年ごろのタピオカ屋の急増と成功はその典型といえるだろう。
じつは、タピオカのブームがやってくるのは3回目となる。1回目は1992年、2回目は2008年、そして3回目が2018年だ。3回目のブームは、LCC(格安航空会社)の就航により、台湾旅行の人気に火がついたことで巻き起こった。
3回目のブームでは、インスタグラムが重要なキーワードとなった。新語・流行語大賞で「タピる」がランクインした前々年の2017年には「インスタ映え」が年間大賞に選ばれ、若いSNSユーザーたちはインスタ映えするネタを探していた。タピオカミルクティは、飲料としてというより、インスタ映えするアイテムとして買われていたのだ。
この現象は「コト消費」の表れといえる。コト消費とは、体験の価値を重視して商品を購入する消費行動のことだ。従来の消費はモノの機能を重視していたが、多機能で高機能なモノが世の中に行き渡った結果、モノを通じた形ある価値よりも、モノを持ったり使ったりすることを通じた形のない価値(コト)が重視されるようになった。これは事業を考えるうえで押さえておきたい社会変化の1つだ。
タピオカ屋の「ブームに乗る」ビジネスモデル

show999/gettyimages
何がブームになるかは分からないし、ブームがどれくらい続くかも分からない。だからこそ事業開発においては、どんな商品にも寿命(プロダクトライフサイクル)があることを踏まえ、いつでも撤退できるようにしておかなければならない。そのためには、少資金、省スペースで開店(開業)するなど、開業にかかるコスト(イニシャルコスト)を安く抑えることがポイントだ。ブームが長続きするようなら追加投資をし、冷めつつあると感じたら次の事業機会を探すといった柔軟性と俊敏性を持っておくことで、時代の変化に乗ることができるのだ。
さて、一時期は街中に溢れていたタピオカ屋だが、今も残っているのは一部のチェーンだけだ。消えたタピオカ屋がどこへいったかというと、ある店は唐揚げ屋に、ある店はマリトッツォの店に、またある店は焼き芋の店になった。
イニシャルコストを徹底的に抑えて短期で利益を回収し、ブームが去ったらすぐに見切りを付けて撤退する――。このようにして、消えたタピオカ屋は次のブームに乗り換え、新たな収益を生み出しているのだ。
立ち飲み屋はなぜ若い女性客が多いのか?
「帰りたくない人」の居場所
立ち飲み屋はなぜ繁盛しているのか。

この続きを見るには...
残り2371/3437文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2024.06.13
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約