デジタル・デモクラシー
ビッグ・テックを包囲するグローバル市民社会

著者
内田聖子(うちだ しょうこ)
NPO法人アジア太平洋資料センター(PARC)共同代表。自由貿易協定やデジタル制作のウォッチ、政府や国際機関への提言活動などを行なう。共著に『コロナ危機と未来の選択――パンデミック・格差・気候危機への市民社会の提言』(コモンズ、2021年)、編著に『日本の水道をどうする!?――民営化か公共の再生か』(同、2019年)。
NPO法人アジア太平洋資料センター(PARC)共同代表。自由貿易協定やデジタル制作のウォッチ、政府や国際機関への提言活動などを行なう。共著に『コロナ危機と未来の選択――パンデミック・格差・気候危機への市民社会の提言』(コモンズ、2021年)、編著に『日本の水道をどうする!?――民営化か公共の再生か』(同、2019年)。
本書の要点
- 要点1「デジタル・デモクラシー」とは、「力を持つビッグ・テックと彼らが構築した搾取的で不公正な経済モデルに対し、人々があらゆる手法やアイデア、運動を通じて抵抗し、民主的で倫理的な対案を生み出そうとしている、まさにそのプロセス」を意味している。
- 要点2自動化は、細切れで低賃金のゴースト・ワークを世界中に生んでいる。
- 要点3ビッグ・テックがこれほどの強大な力を20年で手に入れた背景には、ロビー活動をとおした政治と政策への強い影響力の行使がある。
要約
デジタル・デモクラシーとは何か
民主主義を深めるデジタル化
ビッグテックのもたらすテクノロジーは便利さと快適さをもたらし、社会にとってのインフラとなっている一方で、国家権力による監視・管理、人権侵害、フェイクニュースの蔓延、差別や貧困の再生産などにつながってもいる。
「デジタル化の究極の目的は、民主主義の深化にこそあるべき」だ。どれだけ利便性や効率性が高くても、それが誰かの不利益になるのであれば、批判や拒絶をしなくてはならない。本書の目的は、民主主義を通じて企業や市場を適正化し、公正で倫理的な技術を模索していく方法を、私たち自身で構想していく道すじをつけることである。
それゆえここで語られる「デジタル・デモクラシー」とは、「力を持つビッグ・テックと彼らが構築した搾取的で不公正な経済モデルに対し、人々があらゆる手法やアイデア、運動を通じて抵抗し、民主的で倫理的な対案を生み出そうとしている、まさにそのプロセス」を意味しているのだ。
監視広告を駆逐せよ
ビッグ・テックが握る広告

Sergey Shulgin/gettyimages
検索エンジンやソーシャルメディアを運営する企業の収入源は広告だ。総収入に占める広告収入の割合は、グーグルで83%、フェイスブックでは99%にものぼる。このモデルを根本的に変えていかなくてはならない。
一人ひとりにカスタマイズされた「ターゲティング広告」の仕組みは、とりわけビッグ・テックが仕掛けるものだと、中小企業の経営者にとってブラックボックスである。偽情報を減らすためなどの理由で突然、広告に関するアルゴリズムやルールが変更されることはよくある。そのせいで、「先住民の権利」「女性」「環境」といった言葉を使用しただけで中小企業の広告がブロックの対象となってしまい、泣き寝入りを余儀なくされているという。
インターネット広告業界は、ビッグ・テックによる垂直統合と寡占化が進む。グーグルは、広告の入り口から出稿先まですべて掌握している。YouTubeなどのメディアを所有し、「広告配信(アドネットワークやアドエクスチェンジ)」の機能をも備えているし、Chromeというブラウザも押さえており、検索機能を利用するユーザーの閲覧履歴なども活用できる。これにより、広告代理店や仲介業者まで、競合するほかのデジタル・プラットフォーム事業者との取引を禁じられたり、費用が不透明なままにされたりなど、従属的で不平等な関係のもとに置かれているのだ。
割に合わない広告
こうした広告システムにおける支配を突き崩すために、まずヒントとなるのがターゲティング広告の規制である。欧州では、2018年5月に施行された「一般データ保護規則(GDPR)」で、クッキーなどの「オンライン識別子」も個人データとして定義された。より包括的なものとして2024年2月に施行された「デジタル・サービス法」では、プラットフォーム企業による個人情報のターゲティング広告への利用を規制し、未成年者のデータ収集、ダークパターンなども禁止している。
一方日本ではこうした監視広告への包括的な規制がないだけでなく、市民運動や議論も十分にはなされていない。2022年6月に施行された改正電気通信事業法では、ユーザーの端末に保存された情報を第三者に送信する場合、ユーザーに対して通知または公表することが求められている。しかし、これは利用者の同意を必要とするものではないため、サイトの見つけにくい場所に書くだけでもよくなってしまう。
ミネソタ大学のマロッタ教授らが2019年に発表した調査では、「ターゲティング広告はコンテキスト広告に比べ、4%しか効果が上がらない」ことが示された。広告としての効果も薄く、ビッグ・テックへの従属を強いられ、ユーザーからも反発されるこのビジネスモデルは、社会的責任の面でも、利益追求の論理においても「割に合わない」のだ。
暗躍するデータブローカー
データブローカーとは何か
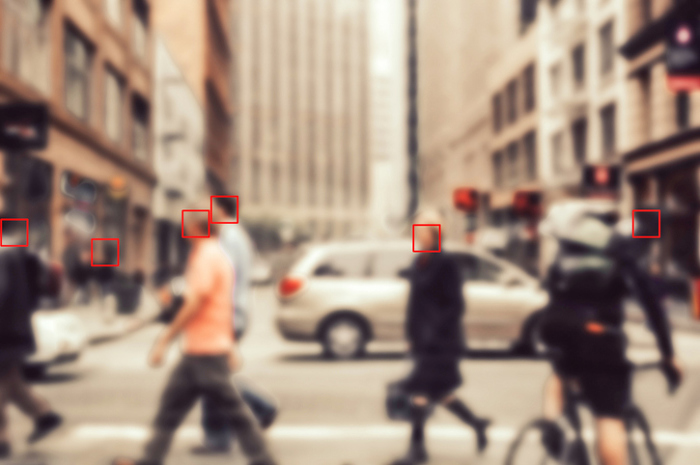
vasare/gettyimages
データブローカーは、「人々の情報(生データ)を収集・購入し、それを他の企業や組織など第三者に販売することで利益を得る企業」のことで、日本の「名簿屋」に相当する。そうした企業のほとんどは、クレジットカード会社などから購入したり、公表されたものを収集したりして合法的にデータを取得、販売している。たとえば選挙人名簿、車両登録、不動産登記簿といった個人が特定できるデータだ。サイトで「第三者とデータを共有しない」という項目にチェックをつけなかった場合、クッキーを含む閲覧履歴はデータブローカーに販売されているかもしれない。フェイスブックなどで個人が公開している情報ももちろん集められている。

この続きを見るには...
残り2845/4741文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2024.07.15
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約











