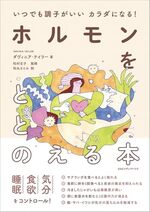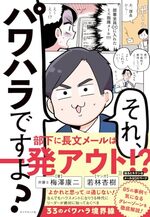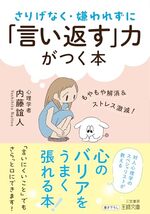静かな退職という働き方
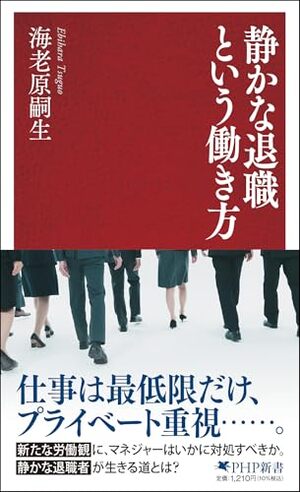
静かな退職という働き方
著者
著者
海老原嗣生(えびはら つぐお)
サッチモ代表社員。大正大学表現学部客員教授。1964年東京生まれ。 大手メーカーを経て、リクルートエイブリック(現リクルートエージェント)入社。新規事業の企画・推進、 人事制度設計などに携わる。その後、リクルートワークス研究所にて雑誌「Works」編集長を務め、2008年にHRコンサルティング会社ニッチモを立ち上げる。 『エンゼルバンク――ドラゴン桜外伝』(「モーニング」連載、テレビ朝日系でドラマ化)の主人公、海老沢康生のモデルでもある。人材・経営誌「HRmics」編集長、リクルートキャリアェロー(特別研究員)。
サッチモ代表社員。大正大学表現学部客員教授。1964年東京生まれ。 大手メーカーを経て、リクルートエイブリック(現リクルートエージェント)入社。新規事業の企画・推進、 人事制度設計などに携わる。その後、リクルートワークス研究所にて雑誌「Works」編集長を務め、2008年にHRコンサルティング会社ニッチモを立ち上げる。 『エンゼルバンク――ドラゴン桜外伝』(「モーニング」連載、テレビ朝日系でドラマ化)の主人公、海老沢康生のモデルでもある。人材・経営誌「HRmics」編集長、リクルートキャリアェロー(特別研究員)。
本書の要点
- 要点1「静かな退職」とは、最低限の業務をこなしつつ、過度な奉仕を避ける働き方である。日本における静かな退職の広がりには、女性の社会進出や柔軟な働き方の普及が影響している。
- 要点2静かな退職を成功させるためには、職場での良好な印象を保ちつつ、副業の基盤を築くことが重要となる。
- 要点3静かな退職者は、企業の経営環境を改善し、人材管理を進化させる存在である。
要約
日本にはなぜ「忙しい毎日」が蔓延るのか
日本で増えつつある「静かな退職」
出世を目指して意欲的に働くことはなく、最低限やるべき業務をやるだけの状態を、「静かな退職」と呼ぶ。これはアメリカのキャリアコーチが発信した「Quiet Quitting」の和訳である。会社をやめる気はないが仕事の意義を見出していないので、「退職」とほぼ同義だという。
かつて「エコノミックアニマル」と揶揄された日本のビジネス界にも、この新たな労働観が浸透しつつある。Job総研による2023年の調査では、全体の72.2%が「仕事よりもプライベートを重視する」という結果が出た。
言われた仕事はやるが、会社に過剰な奉仕はしない。不合理な要望は受け入れず残業は最小限にとどめる――。そんな社員に対し、旧来の働き方に慣れたミドル層は不満を抱いている。
本書はこうした軋轢を解消するための、「静かな退職の取り扱いガイドブック」だ。静かな退職を望む個人と、その周囲の上司や企業双方に、静かな退職をソフトランディングさせる方法を解説する。
手を抜けば抜くほど「労働生産性」は上がる

Milos-Muller/gettyimages
まずは欧州の働き方に目を向ける。欧州の標準労働は、日本ならクビになるレベルといえる。たとえば、スペインからアンドラ公国(フランスとスペインの国境にある)に行くバスの運転手が定時になると乗客を降ろした事例がある。日本のドライバーなら目的地まで行くだろう。
欧州では定時退社を優先するため、労働生産性が高くなる。さらに、乗客たちがタクシーなどを利用するため、新たな消費=生産が生まれ、経済活動の活性化にもつながる。このように、手を抜けば抜くほど「労働生産性」は上がるのだ。
日本では「忙しい毎日」を送る人が多く、業績に直接関係のない業務に時間を割いている。

この続きを見るには...
残り2989/3728文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2025.03.26
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約