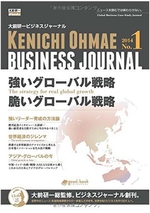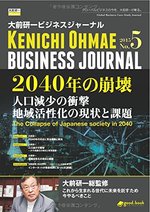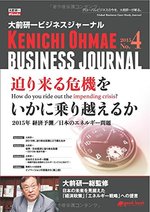大前研一ビジネスジャーナル No.2
ユーザーは何を求めるか
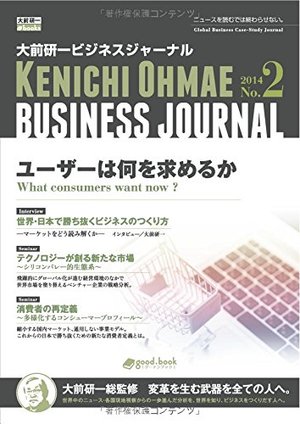
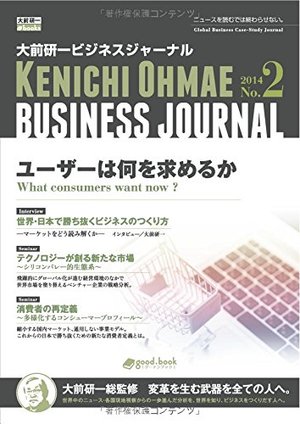
出版社
masterpeace
出版日
2014年11月28日
評点
総合
4.0
明瞭性
4.5
革新性
4.0
応用性
3.5
著者
大前 研一(おおまえ・けんいち)
1943年、福岡県若松市(現北九州市若松区)生まれ。早稲田大学理工学部卒業。東京工業大学大学院原子核工学科で修士号、 マサチューセッツ工科大学大学院原子力工学科で博士号を取得。経営コンサルティング会社マッキンゼー&カンパニー日本社長、本社ディレクター、アジア太平洋地区会長等を歴任。94年退社。96~97年スタンフォード大学客員教授。 97年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)大学院公共政策学部教授に就任。 現在、株式会社ビジネス・ブレークスルー代表取締役社長。オーストラリアのボンド大学の評議員(Trustee)兼教授。 また、起業家育成の第一人者として、05年4月にビジネス・ブレークスルー大学大学院を設立、学長に就任。2010年4月にはビジネス・ブレークスルー大学が開学、学長に就任。02年9月に中国遼寧省および天津市の経済顧問に、また10年には重慶の経済顧問に就任。04年3月、韓国・梨花大学国際大学院名誉教授に就任。「新・国富論」、「新・大前研一レポート」等の著作で一貫して日本の改革を訴え続ける。『原発再稼働「最後の条件」』(小学館)、「洞察力の原点」(日経BP社)、「日本復興計画」(文藝春秋)、「一生食べていける力」がつく大前家の子育て(PHP研究所)、「稼ぐ力」(小学館)、「日本の論点」(プレジデント社)など著書多数。
1943年、福岡県若松市(現北九州市若松区)生まれ。早稲田大学理工学部卒業。東京工業大学大学院原子核工学科で修士号、 マサチューセッツ工科大学大学院原子力工学科で博士号を取得。経営コンサルティング会社マッキンゼー&カンパニー日本社長、本社ディレクター、アジア太平洋地区会長等を歴任。94年退社。96~97年スタンフォード大学客員教授。 97年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)大学院公共政策学部教授に就任。 現在、株式会社ビジネス・ブレークスルー代表取締役社長。オーストラリアのボンド大学の評議員(Trustee)兼教授。 また、起業家育成の第一人者として、05年4月にビジネス・ブレークスルー大学大学院を設立、学長に就任。2010年4月にはビジネス・ブレークスルー大学が開学、学長に就任。02年9月に中国遼寧省および天津市の経済顧問に、また10年には重慶の経済顧問に就任。04年3月、韓国・梨花大学国際大学院名誉教授に就任。「新・国富論」、「新・大前研一レポート」等の著作で一貫して日本の改革を訴え続ける。『原発再稼働「最後の条件」』(小学館)、「洞察力の原点」(日経BP社)、「日本復興計画」(文藝春秋)、「一生食べていける力」がつく大前家の子育て(PHP研究所)、「稼ぐ力」(小学館)、「日本の論点」(プレジデント社)など著書多数。
本書の要点
- 要点1時代はスマホからウェアラブルの方向へ向かい、コンピューターのインターフェースも、今までのGUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)から、音声やジェスチャーなどで操作するNUI(ナチュラル・ユーザー・インターフェース)に向かっている。
- 要点2過去はLower-middle Classからキャリアをスタートして、Upper-Middle Classで終わるというのが、目指すキャリアだったが、今は年齢による給料の上昇幅は小さくなってきている。
- 要点3多様化した消費者に対して、消費者の動きを見極め、深層心理をつかみ、共感を得られる方策を考え実行していくことが、消費者の新潮流を的確につかむことにつながる。
要約
インタビュー
変化するマーケットをいかに捉えるか

Jose Antonio SA!nchez Reyes/iStock/Thinkstock
シリコンバレーのシーンは光のスピードで変化している。1年に1回程度の頻度で行かなければ、新しいシリコンバレーの勢力図は分からない。米国のパンドラメディア(各ユーザーの行動から好みの曲をレコメンドする、ストリーミング型インターネットラジオを提供している)を過去に見に行った際は、課金方法をどうするのかなどを不思議に感じていたものだ。しかし回線状況が良くなった今では、サービスは劇的に広まった。一曲一曲ダウンロードするのではなく、月額9ドル99セントで好きな曲を10万曲聴くことがスムーズにできるようになった。
ネットフリックスにより映画もストリーミングで観られるようになった。料金は音楽と同様に、月額9ドル99セントだ。ネットフリックスは、過去観た映画をもとにして、質の高いレコメンデーション機能を提供している。レコメンデーション機能はサービスにはまる人を増やす工夫として大切なものだ。
音楽、映画の次は本である。アマゾンは、本を好きなだけ読んで月額9ドル99セントというサービスを始めた。このサービスは出版社から抗議を受けたが、アマゾンは抗議した会社を買収して、本の在庫も全部買うという手段も駆使してしまう。
シリコンバレーは非常に滑りやすいスケート場のようである。そこでワルツを踊り、世界が向かう方向を見ていなければ、旧世代の爬虫類のように時代に取り残されることになる。
日本国内のマーケットに目を転じると、今、60歳以上の人の消費が46パーセントになっている。このような人たちは、片道1時間半以上かけて通勤するような、モーレツ社員で頑張りくたびれた後に引退しているので、時間を持て余している。日本人は年金の3割を貯金に回す、世界でも例のない国民だ。死ぬ瞬間が一番貯金がたまっていたりする。この世代が買い物に行くと、買いたいものがなくても、なぜかいいものを買う。富が集まっているこの60歳以上のセグメントを、もっと研究する会社があっても良いのではないだろうか。
テクノロジーが創る新たな市場
シリコンバレーの生態系とは

zimmytws/iStock/Thinkstock
シリコンバレーは米国の中でも特殊な場所だ。よく日本人は日本企業と米国企業に大きな差がついてしまったと言うが、米国東海岸の人も同じように、シリコンバレーと東海岸の差を嘆いている。東海岸や他の地域に住んでいる起業に意欲のある人は、シリコンバレーに吸い寄せられていく。中南米・インド・旧ソ連圏・台湾・イスラエルなどからも、人が大量に流れ込む。母国にいたのでは限界があるので、これらの国・地域の起業家が実力試しに来ているのだ。
第2次世界大戦時に、日本が戦艦や戦闘機などのハードウェアの性能に注力したように、日本の会社は今でも優れたハードウェアを提供することが得意である。しかし、欧米が戦争の勝ち方をシステムとして研究し、日本が敗戦したことと同様に、日本はシリコンバレーが形成するビジネスのシステム、生態系にやられてしまっているのだ。日本だけでなく、欧州、中国、韓国も同様の状況にある。
かつてのアメリカンドリームは起業後にIPOを実現することだったが、最近はほとんどM&Aにより会社を売却する道を選ぶ。その後、創業者はその企業に残ることもあるが、もう一度起業する人も多い。その後、彼らはエンジェルとして投資家になっていく。1000億円くらいの資産を持っていることも多く、30億円くらいポンと投資するのである。

この続きを見るには...
残り2576/4003文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2015.04.28
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約