「無知」の技法 Not Knowing
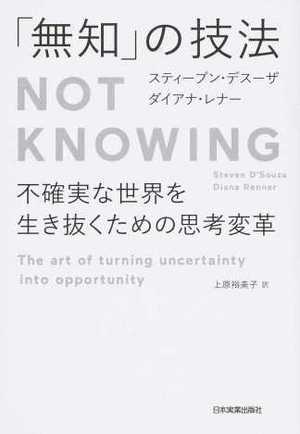
「無知」の技法 Not Knowing
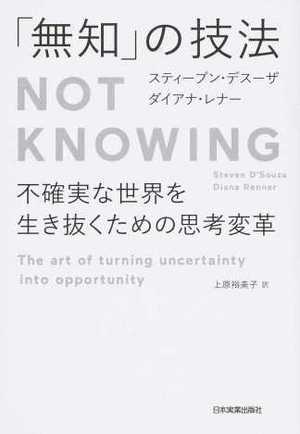
著者
スティーブン・デスーザ
企業コンサルタント、ディーパーラーニング社取締役。エグゼクティブ研修を専門とし、リーダーシップ、組織開発、ダイバーシティーなどをテーマに研修・講演などを行なう。アクセンチュア、バンクオブアメリカ、クレディスイス、ゴールドマンサックスなどが主なクライアント。IEビジネススクール(ヨーロッパNo.1ビジネススクール)准教授。
ダイアナ・レナー
企業コンサルタント、Not Knowingラボ所長。組織戦略、アダプティブ・リーダーシップ、組織の複雑性理論などが専門。ハーバード大学ケネディスクール、アデレード大学、テキサス大学などでリーダーシップ・プログラムを教える。
企業コンサルタント、ディーパーラーニング社取締役。エグゼクティブ研修を専門とし、リーダーシップ、組織開発、ダイバーシティーなどをテーマに研修・講演などを行なう。アクセンチュア、バンクオブアメリカ、クレディスイス、ゴールドマンサックスなどが主なクライアント。IEビジネススクール(ヨーロッパNo.1ビジネススクール)准教授。
ダイアナ・レナー
企業コンサルタント、Not Knowingラボ所長。組織戦略、アダプティブ・リーダーシップ、組織の複雑性理論などが専門。ハーバード大学ケネディスクール、アデレード大学、テキサス大学などでリーダーシップ・プログラムを教える。
本書の要点
- 要点1人は未知との境界線に立たされたとき、自分の弱さや不完全さをつきつけられ、有能という印象を維持したい欲求に駆られる。また、知らないという不安から逃れるために、専門家やリーダーに判断を委ねようとしがちだ。しかし、既知と未知の境界線を踏み越えるとき、模索するプロセス自体を楽しもうとすることで、新しい可能性を見つけることができる。「知らない」ことを受け入れることが成功のカギとなる。
- 要点2新しい思考が根づくための精神の余白をつくる能力を「『ない』を受容する力」(ネガティブ・ケイパビリティ)と呼ぶ。
要約
「知識」の危険性
知っていることの罠
人間は「知っている」ことに焦点を置くあまり、知識を疑ったり、知らないと認めたりすることができなくなる傾向にある。人間の脳は常に「確かな答え」を求めている。そのせいで、知識が足かせになりかねない場面でも知識にしがみつき、新たな学びや成長を阻害されるという、知のパラドックスに陥ってしまう。
もちろん、深い知識と専門的研究の注力があるからこそ専門家になれる。しかし、それがかえって視野を狭くする場合もあるのだ。特定のテーマに詳しくなればなるほど、既成概念に縛られ、問題の本質が見えなくなる「アンカリング・バイアス」を引き起こしてしまう。例えば、HIVの新たな解決策を探すために設立された国際エイズワクチン推進構想という機関は、芳しい成果を出せずにいた。専門家たちが「HIVの解決策はワクチンのはず」という偏見にとらわれてしまっていたからだ。しかし、あるイノベーション・コンサルタントが「タンパク質の安定化」に目を向けるよう促したことで、新しい角度から問題を切り取ることができ、革新的な提案書が数多く寄せられるようになったという。
リーマンショックの発端も、少数の専門家に対する過信だった。金融市場と国際経済の不均衡について、度重なる警告がなされていたにもかかわらず、優秀なリスクマネージャーが合理的に判断してくれるはずだという思い込みが蔓延していたのだ。
専門家とリーダーへの依存

m-imagephotography/iStock/Thinkstock
リーダーは過大な期待や要求を背負わされることが多く、知識を求められるうちに、「答えを知っていなければならない」という幻想に陥る。責任者に全知全能たることを望む期待感は、幼少期の体験によって形成される。親に頼り切りとなる幼少期を通じて、「偉い人」を求める習慣がしみついているのだ。大人になってからも、権威に対する盲目的な服従という形でその習慣は残っている。権威に服従すれば、知らないという不安を感じなくて済むかわりに、正しい判断力や本来の自分を発揮する力も奪われてしまう。
複雑化・曖昧化する世界
世界は変動的で不確実であり、複雑で曖昧になる一方だ。唯一確かなのは、「世界はほぼ常に理解不可能なもの」ということである。科学的管理法の父、テイラーが示唆した20世紀の指揮統制型リーダーシップ論は、効率、論理、迅速な意思決定を重視していたが、予測不可能な「未知の未知」の領域においては、まったく無力である。
にもかかわらず、人間は「その場しのぎの解決策」を求めてしまう。典型例は、不祥事が起きた組織での拙速なCEOやリーダーの交代である。

この続きを見るには...
残り3174/4239文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2016.03.04
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約











