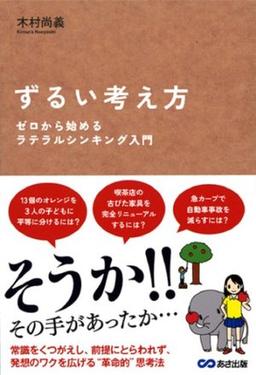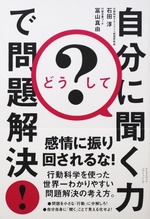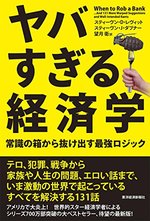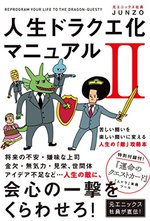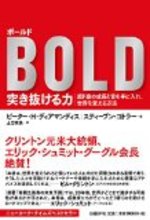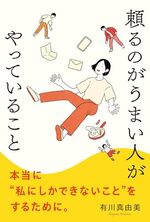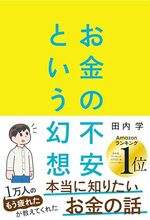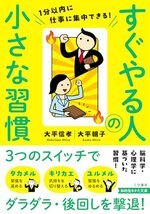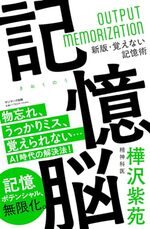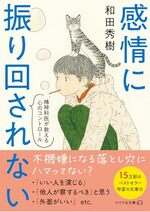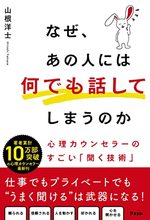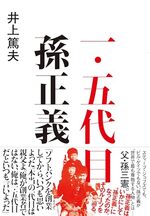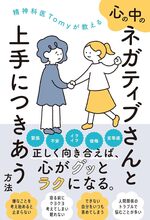ようこそ! ラテラルシンキングの世界へ
ラテラルシンキングとは?
まずは、ラテラルシンキングの特徴について説明していく。ラテラルシンキングは、イギリス人のエドワード・デ・ボノ博士が1967年に提唱した考え方で、一般的には「どんな前提条件にも支配されない、発想の枠を広げる思考法」と理解されている。
これとよく対比されるロジカルシンキングとは、物事を順番に積み上げながら筋道立てて正解を導く「論理的な思考」を指す。常識や経験から妥当だと思われる「正解」を導くためにロジックを掘り下げていくので、垂直思考(Vertical Thinking)と呼ばれることもある。
これに対し、ラテラルシンキングは、解決策を導くための順番や過程を問わない。ラテラル(Lateral)は「水平」という意味を持ち、ラテラルシンキングは、水平方向に視点を広げる思考法なのである。問題の解決につながる選択肢はすべて正解であるため、常識から離れて、自由自在に発想すればよい。
ラテラルシンキングによって生まれる具体的な効果は、次の4点である。
①あらゆる前提から自由になれる。
②異質なもの同士を組み合わせたり、既存の価値を逆転させたりして、まったく新しい
ものが生まれる。
③問題を解決する「最短ルート」を見つけやすくなる。
④結果的に、お金や時間、手間を大幅に節約できる場合がある。
問題解決において、ロジカルシンキングで問われるのは「過程」であるのに対し、ラテラルシンキングで問われるのは「結果」である。両者は相互補完の関係にあり、思考の順番としては、最初にラテラルシンキングで選択肢を広げ、実行段階でその選択肢に問題がないかどうかをロジカルシンキングで考察するのが望ましい。
ラテラルシンキングの必要性

社会はロジカルシンキングに支配されている。物事を論理的に進めなければ世の中が混乱するので仕方がない。しかし、ロジカルシンキング一辺倒になると、発想が貧しくなるだけでなく、本来なら共存できるはずの他の考えをすべて否定することになるため、窮屈で排他的になるおそれがある。