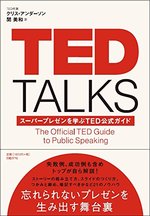菊とポケモン
グローバル化する日本の文化力
著者
アン・アリスン(Anne Allison)
文化人類学者。デューク大学ロバート・O・コヘイン研究室教授。現代日本の日常生活における政治経済と想像的な無双世界との相互関係を研究。著書に、東京でホステスとして働いた経験をもとに、サラリーマンの夜の社交生活を考察した “Nightwork: Sexuality, Pleasure, and Corporate Masculinity in a Tokyo Hostess Club” (University of California Press, 2000) がある。上智大学で教鞭をとっていたことがあり、調査のために現在も頻繁に来日。現在は21世紀の日本と日本人の調査をもとに、不安定な状況に置かれている労働者の実態と社会不安が、未来にどのような希望(もしくは絶望)をもたらしているか、という問題に関する著書を執筆中。
文化人類学者。デューク大学ロバート・O・コヘイン研究室教授。現代日本の日常生活における政治経済と想像的な無双世界との相互関係を研究。著書に、東京でホステスとして働いた経験をもとに、サラリーマンの夜の社交生活を考察した “Nightwork: Sexuality, Pleasure, and Corporate Masculinity in a Tokyo Hostess Club” (University of California Press, 2000) がある。上智大学で教鞭をとっていたことがあり、調査のために現在も頻繁に来日。現在は21世紀の日本と日本人の調査をもとに、不安定な状況に置かれている労働者の実態と社会不安が、未来にどのような希望(もしくは絶望)をもたらしているか、という問題に関する著書を執筆中。
本書の要点
- 要点1日本のポップカルチャーの特徴は、現実世界と異世界が複雑に絡み合い、さまざまなモノの形がいったん崩され、新たにハイブリッドなものとして組み立て直されている点にある。
- 要点2日本にとっても米国にとっても、ポケモンを米国展開することは大きな冒険だった。日本側は「ポケモンの美学」を守ることを第一に考え交渉に赴いたが、いくつかの点ではローカライゼーションを承認した。
- 要点3ポケモンの本質はゲームであるところだ。双方向的で流動的な面白さを提供するからこそ、今日の人気に繋がった。
要約
ポケモンという衝撃
米国の牙城を切り崩したポケモン
米国における日本のポップカルチャーの隆盛は、すでに一時的な流行の範囲を超えている。しかも、日本のポップカルチャー製品は、米国市場を席巻しているだけでなく、米国の国民的想像力にも大きな影響をおよぼしはじめている。その中でも1996年にゲームボーイソフトとして発売されたポケモンは、その後のメディアミックス展開も相まって、1999年までには巨大産業へと発展、世界市場でもっとも売れている子供向け商品にまで成長を遂げた。
それまで、米国の子供たちを魅了したおとぎの世界のキャラクターは、もっぱらディズニーやハリウッドだった。しかし、そこにポケモンが食いこんできた。文化産業における日本の地位が高まっていくなかで、米国の覇権は次第にゆらぎはじめた。
テクノ―アニミズムが日本の美学
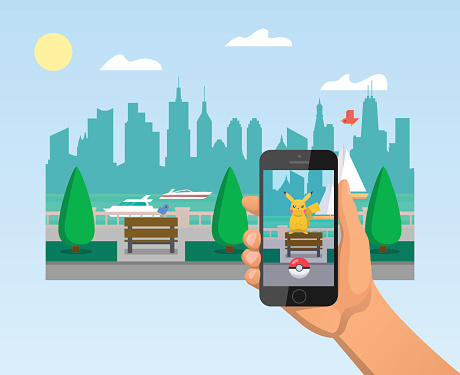
MagicVectorCreation/iStock/Thinkstock
日本のポップカルチャーの大きな特徴は、現実世界と異世界が複雑に絡み合い相互に行き来しあっていること、そして、モノの形がいったん崩され、新たにハイブリッドなものとして組み立て直されている点にある。民族的で宗教的な伝統によって育まれた日本のアニミズム的な感性は、米国にはない日本独自のポストモダン的なものをつくりあげた。そしてそこでは、テクノロジーが大きな役割を担ってきた。
日本のもつこの独特な美学を、ここでは「テクノ-アニミズム」と呼びたい。ポケモンは人工的につくられたものだが、その「虚構性」や「非現実感」は、伝統的な妖怪や精霊とあまり変わらない。ポケモンはまさに、現代のテクノロジーと商品を通して、伝統的文化をよみがえらせたものだといえる。
このような日本人の世界観は、人間が世界の中心的存在であり、生と死がより明確に区別されているとする西欧に共通する世界観とは大きく異なっている。モノに生命を与え、精神性を見出し、遊びであると同時に、とても真面目なものとして、その世界をとらえる――それが現代日本の美学なのである。
【必読ポイント!】 ポケモンが米国で天下を獲るまで
ポケモンの美学を守れ

Ingram Publishing/Thinkstock
ポケモンはそもそも、当初日本国外に輸出することなどまったく考えられずにつくられた。任天堂が、ポケモンの生みの親である田尻智氏の会社からポケモンのゲームソフトを買ったときも、米国もふくめて他国に輸出することは想定されていなかった。その意味で、ポケモンの海外展開は日本側にとって、大きな挑戦だった。
日米間の交渉は当初、とても厳しいものだった。はじめてポケモンに関心を示した米国側の人間は、ニンテンドー・オブ・アメリカ(NOA)のCEO兼会長の荒川実氏だった。日本でブレイクしていたポケモンに刺激を受けた荒川氏は、NOAの米国社員にテストさせるため、ゲームを米国に持ち帰った。しかし、当時のゲーム市場といえばアクションゲームが主流だった。米国人はポケモンのRPG形式に惹きつけられないし、ゲームのおもしろさがわかるまでに時間がかかるのは大きな問題だという声があがった。ポケモンのデザインが「クール」というよりは「キュート」だったことも、米国で受けいれられないと言われた原因の1つだった。
そのため、キャラクターを米国人の嗜好に合わせて変更をしたらどうかという提案がなされたのだが、ポケモンのデザイナーたちは明確にこれを否定した。ポケモンをマンガやアニメ、映画にした立役者である小学館の久保雅一氏は、インタビューのなかで、「私はポケモンを育てて来ている」と話している。久保氏にとって、ポケモンは子供のような存在であり、「厳密にビジネスとしてだけ見ていた」米国側の主張は受け入れられなかったと当時を振り返った。

この続きを見るには...
残り2139/3640文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2016.08.10
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約